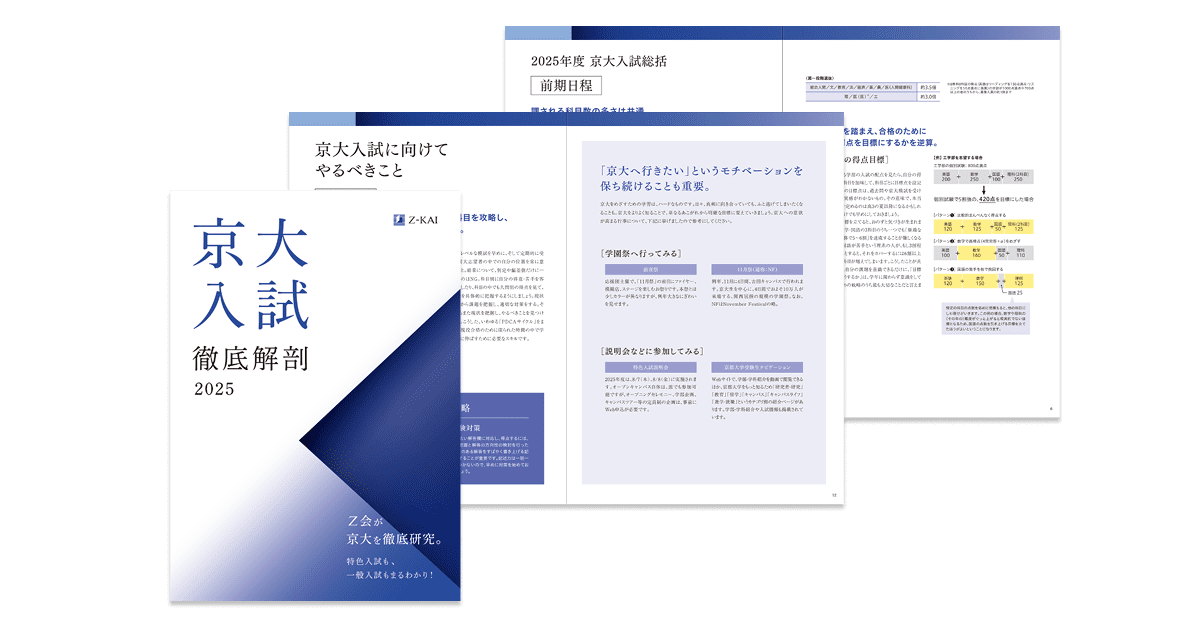Z会の大学受験担当者が、2024年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会数学担当者からのメッセージ
京大数学では数式処理力、発想力、観察力、論述力がバランスよく問われる出題構成であることが多いです。
また、受験生が苦手とする見方を敢えてつく出題も多く、これは「数学をきちんと勉強してきたか?」を見るのが狙いです。解法の暗記や、身についてないテクニックを用いるなどのうわべだけの学習に対する警鐘ともいえます。
Z会の京大講座では、京大数学で問われる頻出テーマや分野を網羅するだけでなく、添削指導や豊富な解説で真の理解と応用力を育むことができます。1問1問を味わい尽くすように1年間取り組むことで、1年後には想像以上の学力が身につきます。
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化
- 難易度は2023年度からやや難化
- 分量は2023年度からやや増加
2024年度入試の特記事項
- 中問に分かれての出題はなかった。
- 第2、3、6問は誘導となる小問がない単問構成であった。
- 第1問は文系と題材が共通。
- 第5、6問の配点が40点と、高く設定されている。
合否の分かれ目はここだ!
- 得点しやすい問題とそうでない問題で差が大きくついていた。そのため、問題の難易を見きわめてきちんと得点することが非常に重要である。
- まずは第1問(1)、第2問を確実に得点しておこう。また、空間図形、とくに四面体の問題は京大では頻出であるから、第3問もしっかり対策し得点できることが求められていると考えてよいだろう。
- 第4問も答え自体は求めやすいため、次に取り組むものとしておすすめ。論述の正確性が問われる出題であるため、時間配分には注意しよう。第1問(2)は得手不得手が出やすいが、できれば手を付けておきたい。
- ここまでを確実に得点できるとよいが、手詰まりになる問題があるようなら第5問へ。第5問は積分法の分野では頻出のタイプであるため、解法のあらすじは立てやすいだろう。方針を書いて部分点をねらうところまでは進めておきたい。
- 第6問は発想もストーリー構築力も必要とされるため、優先して解く問題とはいえない。これ以外の問題を中心に、確実に点数を重ねるのがよい。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
第1問
- 確率と極限の融合問題。(1)は数え上げの正確さを見るための問い。これは確実に得点しておきたい。
- (2)は極限さえわかればよいので、実はpnを具体的に求める必要はなく、このことに気づくと早い。
第2問
- 複素数平面上の複素数が動く領域に関する問題。複素数平面における図形的解釈に精通していれば、どのような図形になるかを判断することは難しくない。
第3問
- 空間図形に関する問題。「ねじれの位置」について問われることは、高校数学では少ないが、否定に着目すれば扱いやすい条件に落とし込める。必要十分条件の扱いについても重要となる。
第4問
- anの偶奇によってan+1の定まり方が異なる数列について考える問題。(1)における実験の結果を(2)に応用すればよく、いずれも具体的な状況について問われているので答え自体を出すことは難しくない。論証が問われる問題と思われるため、適切に論述できたかどうかがカギとなる。
第5問
- 積分法を用いて面積を求める問題。(1)の面積を求めるところには特別な発想などはなく、やることは見通しやすい。ただし、文字で式が煩雑になりがちなので、計算ミスに注意して解き進める必要がある。
- (2)で問われている内容は定番の極限の形ではあるものの、式が見づらいため「定番の形である」と見抜くことに苦労した人が多かったと思われる。
第6問
- 桁数を題材とした極限の問題。NnやLnを不等式を用いて評価する、すなわち □<(評価したいもの)<△ の形で表現することが最大の関門。これをもとに、はさみうちの原理を利用できる形を目指す。
攻略のためのアドバイス
京大理系数学を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 手早く正確に計算をする力
京大では煩雑な計算を行う出題は多くないが、着想、論理展開に時間を奪われる出題が多い。それだけに、方針が立ったあとの計算は手早く正確に行うことが重要で、計算時間を短縮できれば、ほかの問題を解く時間に使うことができる。
計算力は日々の計算練習で身につく。日々の問題演習において、最後まで計算し、確認する習慣をつけることが大切である。
●要求2● 問題の構造を捉える力
京大理系数学において頻出の分野として、図形問題がある。図形問題には、初等幾何、ベクトル、座標幾何などいろいろな解法があり、どの解法を取ればよいのかをまず考えてから解く必要があるものが多い。どの解法を使うのか、見方を変えてほかの問題に帰着させることができないかなどを発想できる力をつけることが、京大理系数学攻略のポイントの1つである。
発想力は、京大の過去問など発想力を鍛えられる問題を解き、考える訓練をすることで身につけられる。
●要求3● 採点者に自分の考えを伝える力
京大では、 証明問題だけでなく、 求値問題においても、 結論に至る過程を丁寧に説明する力が要求されるものが目立つ。記述式の試験においては、自分の頭の中では分かっていてもそれを採点者に伝えることができなければ、点数に結びつかない。論理的に無理なく、より簡潔に答案を書くための論証力をつけることが、京大理系数学攻略のポイントとなる。
論証力は自分一人で勉強を進めても身につきにくい。 この力は、 Z会の通信教育で別の人に採点・添削をしてもらい、その結果を復習することで身につけられる。
対策の進め方
まずは、各分野の完成からである。京大入試では様々な考え方が必要とされるので、苦手分野があれば、遅くとも高3の夏休みまでには克服したい。Z会の通信教育では、入試に必要な考え方を幅広い分野の演習を通して身につけることができるようになっている。
高3の秋以降は、それまでに身につけた考え方を、実戦的な問題演習を通して使いこなせるようにしていこう。受験生用のZ会の講座では、微積分、図形、整数、確率といった京大頻出分野の問題を中心に、論証力も養成されるように学習を進めていく。
共通テストが終わったあとは、これまでの学習の総まとめである。京大入試に即応したZ会の問題で、入試に使える計算力・発想力・論証力を完成させよう。
Z会でできる京大対策
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!