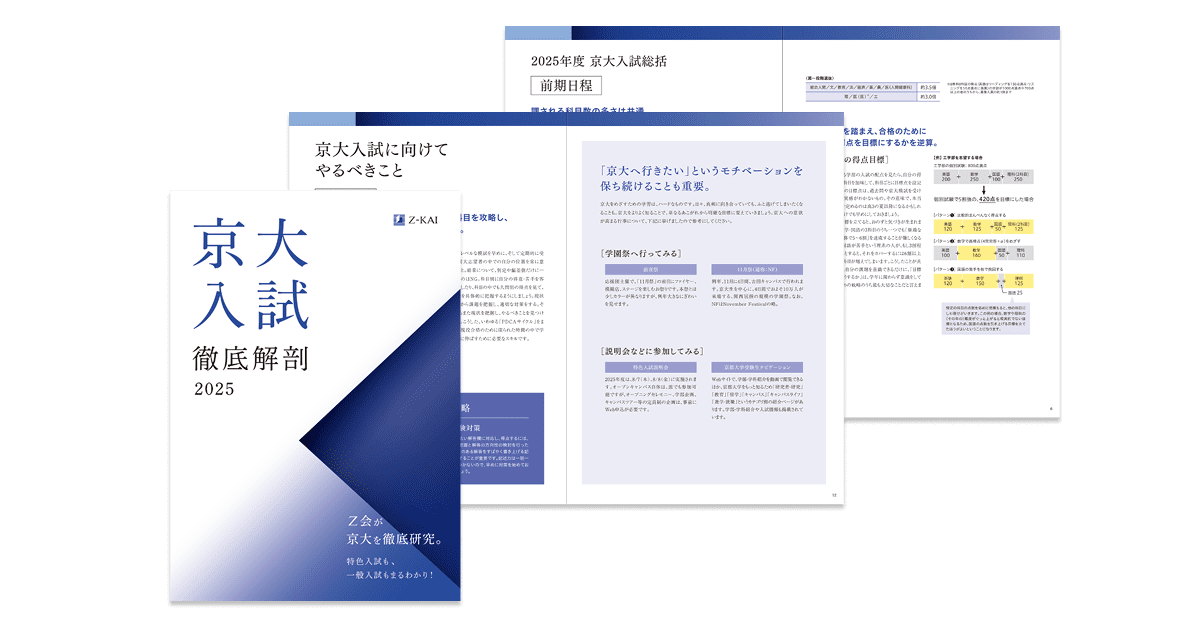Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会生物担当者からのメッセージ
2023年度以降、ケアレスミスが許されない高得点での競争になる出題が続いています。理解があいまいな分野を残してしまうとかなり苦しくなります。出題範囲全体について正確な理解を身につけて臨む必要がありました。例年だと、考察問題は、設問に沿って考察を深めていく構成のことが多く、ある設問で勘違いをするとその後も間違えてしまいます。条件の見落としがないように、要点を押さえた速読を演習時から意識しましょう。
論述問題では、設問の要求を正しく理解したかどうか、要求に対して的確に論述できたかどうか、といったところで、差が開きます。学習時間が限られてくると、生物の問題演習では、考察論述問題も要素だけ挙げて答え合わせ・・・となりがちです。しかし、個別試験に向けては、実際に手を動かし、文どうしのつながりも意識して論述する演習を、一定量取り入れるようにしてほしいところです。そして、それにはZ会の添削問題が最適だと、自信をもっておすすめします。
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化 (理科…1科目90分、2科目180分)
- 難易度は2024年度からやや易化
- 分量は2024年度からやや減少
2025年度入試の特記事項
- 設問数や論述問題の数が減り、また複雑な計算などを求める設問もなく、難易度は2024年度からさらに下がった。
- 生物問題Ⅱは論述問題がない大問であった。
合否の分かれ目はここだ!
2023年度以降、解ける設問でケアレスミスせずに確実に得点することが重要な出題構成が続いている。生物問題Ⅱ問1、生物問題Ⅲ問5・問6、生物問題Ⅳ問1・問2・問5のような教科書レベルの知識で解答できる問題、また、生物問題Ⅱ問5・問6のような典型的な遺伝・計算問題、そして生物問題Ⅰ問1・問2・問4〜6、生物問題Ⅱ問2、生物問題Ⅲ問1〜4、生物問題Ⅳ問3・問6のような取り組みやすい考察問題は、条件の見落としなどのミスをせずに、確実に解くようにしたい。そうして生物問題Ⅱ問7や生物問題Ⅲ問8のような考察問題に取り組む時間を作り出そう。生物問題Ⅱ問2の計算が必要な選択肢は、時間配分次第ではとりあえず先に進み、時間が余れば戻る選択もありだろう。
なお、以前のような難易度の高い設問を織り交ぜた出題だと時間内に解答作成をすべて終えるのは難しくなる。難しい出題であっても、解ける設問で確実に得点を重ねることが必要である。論述問題では、わかっていないことまで無理に踏み込まず、読み取れる内容を設問の要求に沿って簡潔に記し、無駄な失点を防ぐこと。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
生物問題 I
(A):プラスミドの切断と連結 [標準]
プラスミドをいくつかの切断酵素で切断し、再結合することが題材である。問2について、BamHⅠとBglⅡの切断片には、5’-3’の方向を入れ替えると同じ配列の粘着末端がある。
(B):サイトカインの受容と情報伝達の分子機構 [標準]
サイトカインの受容とその後のリン酸化カスケードに関わる分子の相互作用が題材である。図4はリン酸化状態を示しており、サイトカインがなくとも受容体Xはリン酸化していることが読み取れる。
生物問題 II
(A):ゲノムと反覆配列の多型解析 [やや易]
リード文はヒトゲノムと非コード領域の反復配列を取り上げており、設問は転写・翻訳の基本的な知識を問うものと多型解析をめぐる考察問題があった。問4は、図5より読み枠がずれることから選ぶ。
(B):変異遺伝子の遺伝 [標準]
近交系マウスを用いた、突然変異を誘発したマウスの戻し交配と、別系統との交雑が題材である。問7は子の表現型が雄親の遺伝子型と連動していることに気づきたい。遺伝子座Cはゲノムインプリンティングによって雄親の遺伝子のみが発現すると考えられる。
生物問題 III
(A):春化と各種ジベレリンの生合成と代謝 [やや易]
種子春化と植物体春化の遺伝、また春化にかかわるジベレリンの生合成と代謝が題材である。生合成・代謝経路は、表3で処理した標識ジベレリン誘導体が、検出された標識ジベレリン誘導体の上流にあることからあてはめていく。
(B):ヒトの三半規管での回転の感知と前庭動眼反射 [標準]
ヒトの耳での刺激の受容と前庭動眼反射が題材である。問8では、「検査2の結果」の記述から、半規管中のリンパ液は耳に入った水の温度によって温められれば上に・冷やされれば下に沈むことを踏まえて検討する。
生物問題 IV
気孔での蒸散調節と寄生、陸上植物の系統と形質の獲得 [やや易]
リード文は(A)・(B)などに分かれていないが、3パートあり、それぞれ、寄生植物ストライガで気孔が閉じにくいこと、寄生植物ストライガの栄養分・水分収奪と実験、陸上植物の系統と気孔などの獲得した形質・性質を取り上げている。
攻略のためのアドバイス
京大生物を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1●関連分野と連動した知識
ハイレベルな勝負になる京大生物では、教科書レベルの知識で対応できる用語問題や論述問題での失点は許されない。教科書と図説を参照する習慣を身につけよう。教科書で太字になっている語については単純に暗記するだけでなく、関連する生命現象と合わせて、自分の言葉で説明できるようにしておくこと。
●要求2● 実験データの読解力
京大生物は、初見の題材の出題が多く、見慣れない実験の手法やデータを的確に読み解く必要がある。そのためには、条件や結論を箇条書きにして整理する訓練が有効。まずは標準レベルの実験考察問題に取り組むところから始め、徐々に京大レベルに近づけていこう。
●要求3● 考えたことを的確に伝える論述力
論述力は自分の手を動かして答案を書き上げることが何よりも大切。実戦演習を重ねる中で、仮説→実験→結果→考察→仮説という一連の流れを自分なりに整理する癖を身につけ、論述に必要なキーワードを集めることから始めよう。書き上げた後は、独りよがりな答案になっていないか、添削してもらうとよい。
Z会でできる京大対策
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!