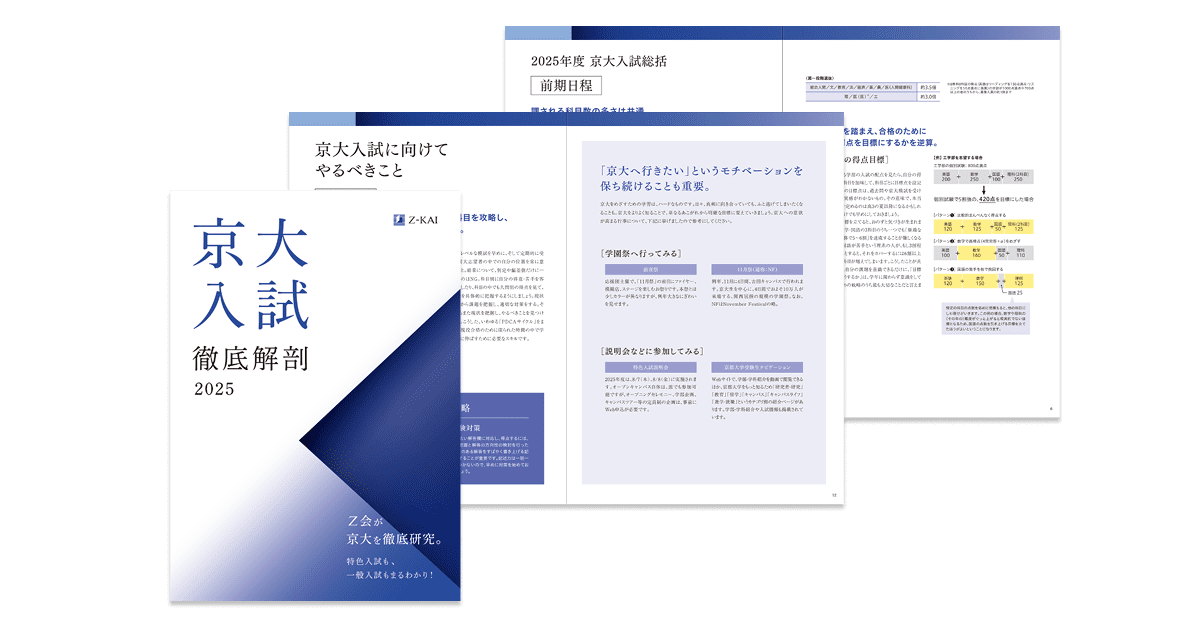Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会世界史担当者からのメッセージ
・2025年度の入試問題は、試験時間90分で大問4題、うち大問2題が300字論述という大きな枠組みは例年通りであったものの、思考力や記述力を要する設問の割合が高くなりました。教科書の流れに沿って用語の内容、因果関係、世界史上の意味・意義などを丁寧に学習した上で、京大だけでなく他の国立大学の入試過去問も解いてみるなど、様々なタイプの論述問題に取り組んで、実力アップをはかるとよいでしょう。
・京大世界史で出題される300字論述で高得点を獲得するためには、盤石な知識に加え、問題の要求を正確に読み取る読解力、要求に沿った解答を組み立てる論理的思考力・文章表現力が必須です。こうした力は一朝一夕には身につきません。Z会の通信教育 本科「京大講座 世界史」では、100字程度の基礎的な事項を問う論述問題から始まり、入試問題と同じ300字の論述問題まで多様な論述問題を出題。さらに、一人一人の答案に応じた添削指導を行い、論述問題への対応力を徹底的に鍛え上げます。早期からの論述対策で、京大合格をめざしましょう!
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化 (時間:90分)
- 難易度は2024年度からやや難化
- 分量は2024年度からやや増加
2025年度入試の特記事項
- 例年同様、大問〔Ⅰ〕・〔Ⅱ〕がアジア史中心、大問〔Ⅲ〕・〔Ⅳ〕が欧米史中心の出題であった。
- 2025年度の大問〔Ⅱ〕・〔Ⅳ〕は、2022年度〜2024年度に引き続き語句記述問題と小論述問題のみから構成され、2021年度に見られたような4文正誤問題は出題されなかった。
- 大問〔Ⅱ〕・〔Ⅳ〕では、小論述問題が例年1〜6問程度出題される。2024年度は大問〔Ⅳ〕で1問出題されたのみであり、2023年度の6問から大きく減少したが、2025年度は8問と大幅に増加した。
- 2023年度は戦後史からの出題が目立ったが、2024年度・2025年度は古代から戦後までの幅広い時代から、大きな偏りなく出題された。
合否の分かれ目はここだ!
大問〔Ⅰ〕・〔Ⅱ〕は概ね取り組みやすい問題であり、ケアレスミスや問題の要求の見落としなどに注意し、失点は最小限に留めたい。大問〔Ⅲ〕の論述問題は、必要となる知識は教科書レベルであったが、問題の条件に沿って書くべき内容をしっかりと見極め、まとまりのある解答に仕上げる工夫が必要であった。大問〔Ⅱ〕・〔Ⅳ〕の語句記述問題では、空欄や下線部の前後、設問文からヒントを的確に見つけ出してスピード感を持って解答し、論述問題に割ける時間をしっかり確保することがポイントである。
また、大問〔Ⅳ〕(18)(ア)のような抽象的なテーマの問題への対策としては、個別の歴史的事象についての知識を身につけるだけでなく、時代や地域を俯瞰的にとらえる視点を持つことを意識して学習を進めることが不可欠であろう。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
〔Ⅰ〕
オスマン帝国のヨーロッパ諸勢力との抗争、支配領域の変化(論述300字) [標準]
定番といえるテーマの論述問題である。まずは提示された時期における重要な出来事を洗い出そう。その上で、それぞれの出来事によってオスマン帝国の支配領域がどのように変化したのかを整理してから、時系列に沿って説明していけば及第点を得られるだろう。
〔Ⅱ〕
北京をめぐる歴史/中国・ロシア関係史(長文下線部・空欄補充) [標準]
Aでは戦国時代から清の時代までの北京の歴史、Bでは19世紀〜現在の中国とロシア(ないしソ連)の関係をテーマとして、いずれも中国史を中心に出題された。(1)では戦国時代の中国について、やや細かい知識が必要とされたが、戦国の七雄の支配地域を想起し、正解に至ってほしい。(8)は「十進法にもとづき」が大きなヒントとなる。(22)は史料を読み取った上で、当時の国際情勢全般から判断して答える必要のある問題であり、苦戦した受験生もいただろう。
〔Ⅲ〕
スペインのラテンアメリカ植民地経営の特徴・変遷 [やや難]
必要となる知識は概ね教科書レベルの基本的なものであるものの、「アジア産商品とラテンアメリカ産商品を具体的に対比」という設問要求にどう応じるかで悩んだ受験生が多かったのではないだろうか。思い浮かんだキーワードを用い、「植民地経営の特徴とその変遷」という主題に沿って的確に説明するとともに、「労働力の供給源の変化」について具体的に記すことにより、300字という字数を意味のある内容で埋められたかどうかで、答案の完成度に差がついたと思われる。
〔Ⅳ〕
農耕のあり方と土地支配・政治/近代憲法(長文下線部・空欄補充) [やや難]
Aでは農耕のあり方をテーマに古代オリエント史・中世ヨーロッパ史を中心に出題され、Bでは近代憲法をテーマに18〜20世紀の世界について出題された。小論述問題は、基礎的な語句説明から、史料の読解力や思考力を要する問題まで多彩であり、(14)では初見の史料を読み比べて共通点と相違点を見抜く力が求められた。(18)(ア)はBのリード文を踏まえて非欧米世界の人々が「憲法を求めた(あるいは外来者が憲法を与えた)理由」を考察・説明するという、難度がかなり高い小論述問題であった。
攻略のためのアドバイス
京大世界史を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 教科書全範囲の基礎的知識を網羅する「知識力」
京大世界史では、教科書レベルの基本的な知識を問う問題が多くを占めている。但し、現代史や文化史、周辺地域史など、学習が手薄になりやすい分野に関しても満遍なく出題されるので、教科書の全範囲について手を抜かずしっかり学習する必要がある。
●要求2● 問題の要求を的確に捉える「読解力」
とくに論述問題で必要となる力である。京大世界史の論述問題ではさほど細かい知識は必要とされないことが多いが、問題文の複数の要求を漏れなく把握した上で、解答に盛り込むべき史実の取捨選択を的確に行い、まとまりのある解答を作成する必要がある。300字という制限字数の中で、すべての要求にバランスよく対応することができているか、文章の構成や字数配分への工夫も重要である。
●要求3● 短い時間の中で最大限の結果を出す「処理力」
京大世界史の試験時間は90分。300字論述に各25分、長文下線部・空欄補充に各15~20分程度(=小問1問当たり30~45秒)が解答時間の目安になる。わからない小問は潔く諦めるなど、得点を上げるための時間配分も戦略的に行っていく必要がある。小論述に関しても論じるべき内容を素早く把握し、あまり時間をかけずに簡潔にまとめあげなければならない。
対策アドバイス
基礎力の完成
まずは、「知識力」の養成を。遅くとも受験生の夏休み終了までには、全時代の概略と、教科書の太字語句の意味を押さえることを目標にしよう。語句はただ覚えただけでは力にならない。既習範囲は問題演習を行い、自分が理解したはずの知識が、本当に得点につながる力になり得ているかを、確認しながら学習を進めよう。並行して論述問題にも取り組み、「知識を文章でまとめる」ことにも慣れていきたい。
読解力の養成→表現力へつなげる
京大世界史攻略のためには、上で述べたように、知識力の養成と並行して既習範囲については論述問題にも取り組み、本番まで定期的に問題演習を行う習慣をつけてほしい。問題の要求を的確に捉える「読解力」を身につけるためには、問題文を丁寧に読むことが重要である。何となく知っていることを羅列するのではなく、問題文中の時代・地域の指定、「意義」「背景」「経緯」「変化」「特徴」「影響」などといった問いかけに対して、最も適した解答が提示できているか、常に意識しながら解答を作成しよう。復習時に自分の解答作成の過程を確認するために、草稿メモをノートに記録しておくことも有効である。
上手な時間の使い方を身につける
京大世界史は制限時間に比して分量が多いため、時間の使い方も重要である。模試を受験する際に、問題に取り組む順番を工夫したり、試験時間の最後の5分間は見直しのために確保したりするなど、限られた時間内で最大限の成果に結びつける訓練を積むとよい。本番同様の構成の問題を時間を計って解き、「知識力」・「読解力」を土台とした表現力に磨きをかけつつ、本番での時間配分を想定して「処理力」を鍛えていこう。
Z会でできる京大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!