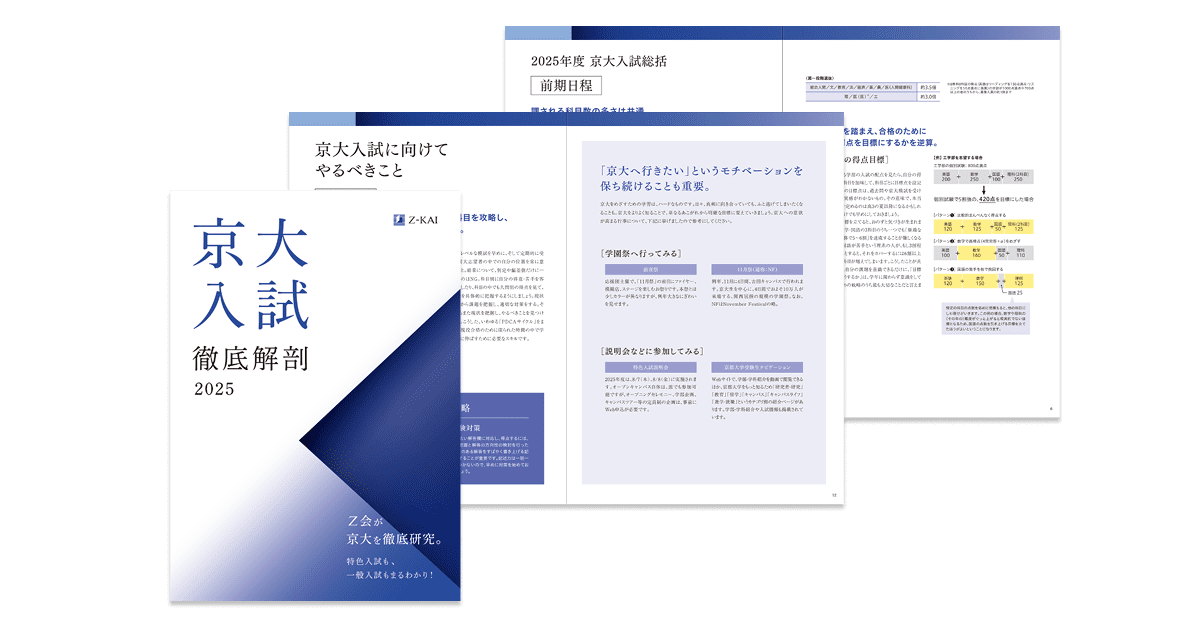Z会の京大講座担当者が、冬〜直前期にかけての「京大生物」の学習ポイントをご紹介。【今から共通テストまでにやるべきこと】【共通テスト後→個別試験本番までにやるべきこと】を解説します。
今から共通テストまでにやるべきこと
共通テスト対策と個別試験対策のバランスに迷っている方も多いと思います。生物に限っては以下のように、共通テストは個別試験に似ています。
- 共通テストでは分野を超えた知識やその運用が問われる。
- 「受験者にとって既知ではない」題材が出題される。
ある程度、書いて答える問題演習の機会をもつことも必要ですが(やらないでいると、生物用語の漢字が思い出しにくくなります!)、「共通テスト対策は個別試験につながっている」ととらえてほしいと思います。共通テスト型の演習でみつかった知識のあいまいな分野を補強し、初見で捉えられなかった考察を解説を読みながら考え方を整理して見直すことは、共通テスト対策であるとともに、個別試験に向けて必要な力を養うことにもなります。
共通テスト後〜個別試験本番までにやるべきこと
知識の確認、考え方は共通テスト攻略に通じますので、追加して必要な
- 論述力の確認
- 過去問を踏まえた時間配分
を、集中して仕上げていきましょう。
論述力の確認
論述問題では、近年基本的な知識を問う論述も出題されていますから、教科書傍用問題集などを利用して今一度見直しておきましょう。
また、考察論述問題ではとくに、設問文を注意して読み、「問われていること」と、踏まえるものや指定語などの条件を確認してから解答しましょう。そして書き終わったら、一度読み直し、問われたことに答えているか、条件に対応し忘れてないかのチェックを。
なお、京大は解答欄が概して広めに用意されています。解答欄が余っているからといって、解答と関係ないことや、リード文などから判断できないことを書いていると、時間をロスするうえ、間違いなどがあれば減点されてしまいます。与えられた条件を踏まえ、問われていることに答える簡潔な論述を意識してください。
過去問を踏まえた時間配分
京大入試の理科は2科目あわせて3時間です。もう1科目の選択科目の出題傾向や、自分の得意不得意を踏まえて、得点を最大化するように考えます。
生物は、時間があればほぼ全問解ける出題内容の年度もありましたが、そんな時も実際に全問に丁寧にあたっていると、時間を使ってしまいます。したがって、共通テスト後はとくに時間を意識した問題演習を重ねましょう。出題をざっと通して見て、すぐに解けるか、解答方針はたつけれど時間がかかるかを見分けて、答案を作成するようにしてください。
一方、年度によっては、リード文が一読では理解しがたい題材が出題されます。このような問題でも、知識問題など取り組みやすい設問がついていることが多いですから、リード文が難解でも設問文に一通り目を通し、とれる問題を落とさないようにしてください。
論述力の面でも、時間配分の演習面でも、Z会の通信教育「直前予想演習シリーズ」の京大生物が、添削者による丁寧な論述内容の確認も受けられて、お役に立つことでしょう。
Z会の京大講座・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!