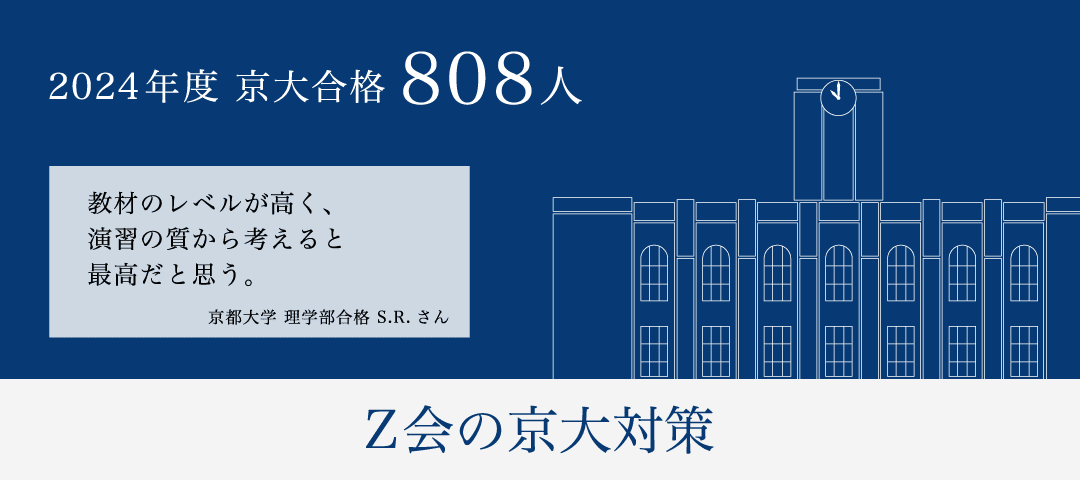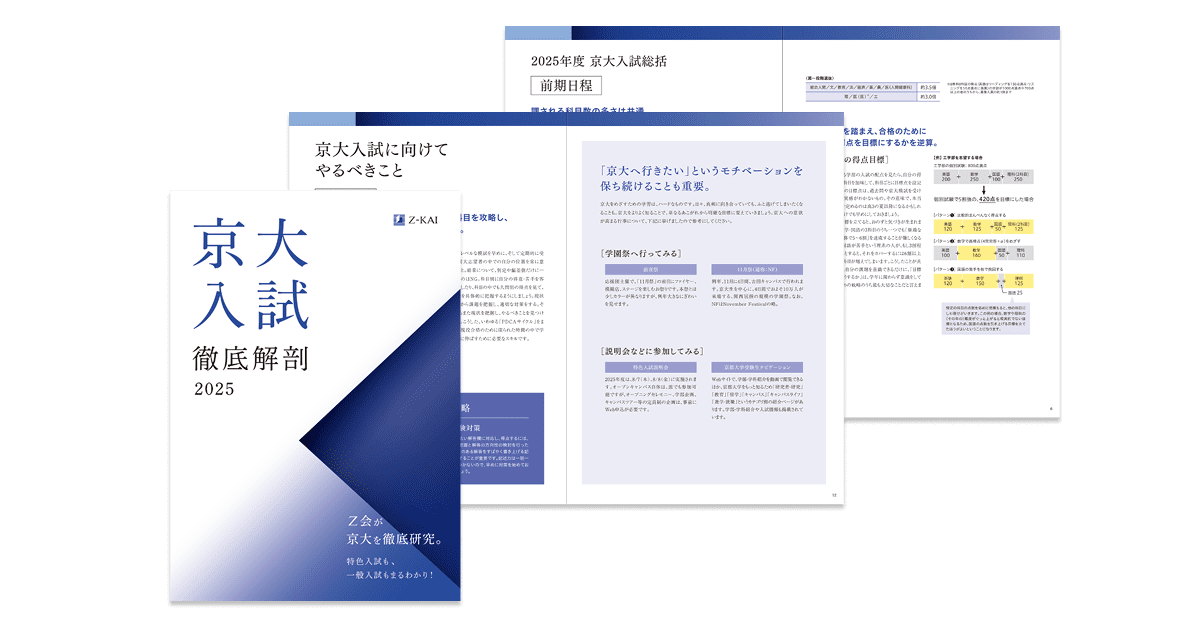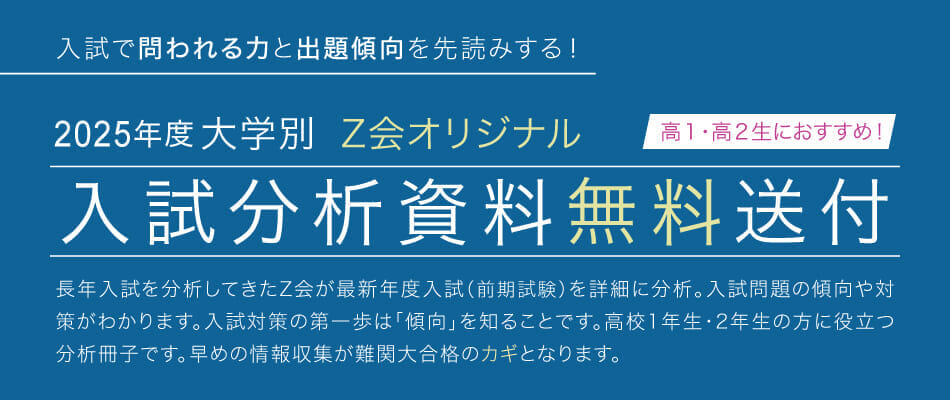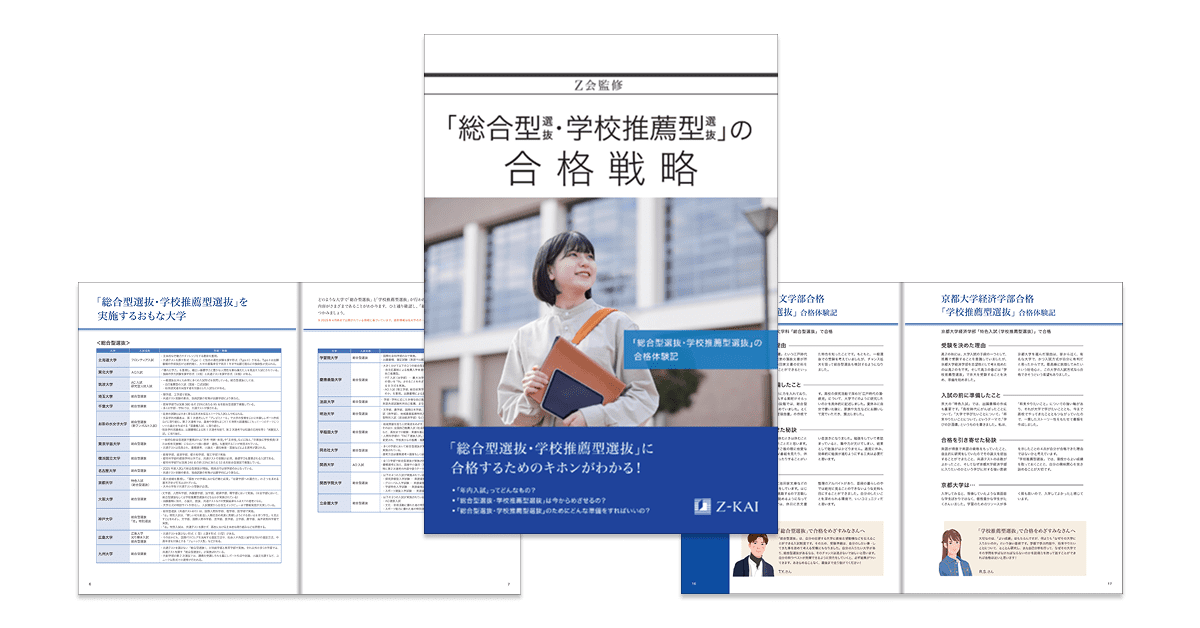Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会地理担当者からのメッセージ
2025年度の京大地理も、頻出のテーマ・形式での出題となりました。字数の少ない論述問題や単答問題が多数出題されたものの、基礎的な内容が多いため、平易な問題でミスをせず、着実に得点を重ねることが点差を分けるポイントとなりました。また、大問Ⅴの地形図の読図問題は、京大地理の定番といえます。新旧地形図の比較を含めて、様々な地形図に触れ、図から起伏や土地利用の変化を読み取る練習を積んでいれば、難なく解答できたでしょう。これらの問題に対応するためには、早めに高校地理の学習内容を押さえ、過去問を初めとする様々な演習問題に取り組む必要があります。
Z会の「最難関講座 地理」では、京大地理攻略に役立つよう、図表の読み取りをもとにした論述問題や、基礎知識を確認する単答問題など、様々な形式の問題を、幅広い分野から多数出題しています。京大をめざすみなさん、Z会と一緒に頑張っていきましょう!
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化 (時間:90分)
- 難易度は2024年度からやや難化
- 分量は2024年度からやや増加
2025年度入試の特記事項
- 地形図の読図問題は毎年出題されており、2023年度以降は、大問〔Ⅴ〕での出題となっている。
- 解答数は単答問題が30で2024年度の38から減少した。空欄補充問題は見られなかった。
- 論述問題は字数指定がある問題が15で、2024年度の13より2増加した。最大字数は50字で、総字数は500字となり2024年度の415字から増加した。字数指定のない論述問題は6であり、2024年度より1増加した。想定字数は20字~50字程度である。
合否の分かれ目はここだ!
全体的に取り組みやすい問題が多く、十分に対策を行った受験生であれば解答できる論述問題が大半であったため、確実に得点を重ねたい。また、単答問題での失点は絶対に避けたい。問題数が多いので、問題全体を見渡し、解答しやすそうな問題から取り組むなど、時間配分を考えながら効率的に解答できたかどうかが合否を分けたと思われる。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
大問 I
ロシア地誌(50字×1、30~50字程度×3、単答) [標準]
ロシアの地誌的な理解を問う問題である。解答しづらい問題も含むが、概ね基本的な知識で対応できる。
(2) ウラル山脈は古期造山帯、カムチャツカ半島は新期造山帯に属することを前提に、特徴とその成因を明らかにしたい。
(4)エネルギー資源の分布について問われた。「エネルギー資源」とあるため、名称を絞りやすい。パイプラインの長所や短所はしばしば取り上げられるテーマである。
(5)ロシアと周辺国との位置関係と言語分布を正確に把握していないと正解しづらい問題である。
大問 II
地域区分(20字×3、50字×1、単答) [やや難]
地域区分の基準に関して説明したリード文をもとに出題された。
(2)①経済水準に基づく地域区分が国を単位として行われる理由が問われた。どこに着眼するか迷うが、②の問題文にある「そのことによって見えづらくなる地域差」が、ある程度ヒントになる。
(3) (4)国家間の経済連携に関する問題である。関連する用語の正確な意味や、比較的新しいRCEPを含む経済連携の枠組みについて理解できているかが問われた。
大問 III
貿易(30字×1、50字×1、20~30字程度×1、単答) [やや易]
設問文から該当する国名を予測しつつ解答していく、近年京大地理で定着している形式の問題である。国名も判定しやすく、問題も基礎的な内容なので取り組みやすい。
(2)安価な労働力を背景とする先進国の生産拠点の移転という頻出事項を、産業および貿易構造の国際的な変化という題意に沿った形でまとめたい。
(4)D国におけるイギリス植民地時代の茶のプランテーションは確実に解答したい。
(5)E国における、原油のモノカルチャー経済からの脱却に関して問われた。「多角化」がキーワードとなるが、観光業など他産業の具体例も挙げながら説明するとよい。
大問 IV
農村人口と農業(20字×1、30字×4、単答) [標準]
国名判定自体は問われない、〔Ⅲ〕と同じ形式の問題である。総人口に占める農村人口の割合の変化を示したグラフをもとに各国の農業について出題された。
(2)①は、国内の過疎地域で生じている生活上の問題を、字数も考慮し複数挙げるとよい。
(5)②は、共通農業政策が重視する農業生産以外の役割が指摘しづらい。ヨーロッパは環境意識が高いことを思い出しながら考えたい。
(6)バターの生産が多いニュージーランドは、南半球にあり市場から遠いことがポイントとなる。
大問 V
大分市の地形図の読図(40字×3、20~30字程度×2、単答) [標準]
新旧地形図を比較し、土地利用の変化とその背景などを問う論述問題中心の大問である。基本的な知識で十分対応可能であるため、確実に得点したい。
(1)集落が立地する地形について問われた。集落Aは等高線を丁寧に読み取って解答したい。集落の立地は、水利と洪水回避という要因がポイントとなる。
(2)市役所や裁判所などの地図記号を読み取る基本的な問題である。
(6)②グラフの20歳代後半~30歳代と0歳~10歳代前半の人口が突出していることから、核家族がポイントとなる。一方、高齢者が極端に少ないことにも着目したい。
攻略のためのアドバイス
京大地理を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 幅広い分野についての知識力
京大地理は、自然(地形図の読図を含む)、産業、社会(都市・人口・民族など)、地誌などといった幅広い分野から出題される。細かい知識が問われることは少ないが、高校地理の全分野にわたって基本的な知識を押さえておく必要がある。また、基本用語は、40~50字程度で簡潔に説明できることが望ましい。
●要求2● 正確な資料読解力
京大地理では、多数の資料が提示される。資料の判読を行い、その判定結果をもとに論述するという出題構成が見られるので、資料判読を誤ると大量失点につながりかねない。例年、出題されている資料の中には読み取りが難しいものも見られるため、正確な資料読解力が求められる。
●要求3● 簡潔に論述する表現力
論述問題の1問当たりの指定字数は40字前後のものが最も多いが、いざ書いてみると、字数の調整が難しい。また、2015年度から出題されている字数指定なしの論述問題に取り組む場合にも、解答欄に合わせて適切な分量を見極める必要がある(解答欄の大きさから20~60字程度)。様々な角度から解答できるよう、基礎的な知識と簡潔にまとめる表現力が必要である。
対策アドバイス
基礎力の完成
まずは、要求①を満たすことをめざそう。授業での教科書学習を中心にして幅広い知識を正確に獲得することに努めよう。Z会の通信教育の講座を利用するなどして、高校3年生の夏までに、各分野の基本事項を理解しながら学習を進めていこう。基礎知識で対応できる問題も出題されるので、基礎固めを疎かにせず、知識を確実に自分のものにしておきたい。また、要求②を満たすためにも、日頃の学習では、資料集・統計集・地図帳などをこまめに確認することを心掛けよう。
論述力の養成
習得した基礎知識を使いこなしながら、京大型の論述問題に対応できるようになろう。Z会の通信教育の「最難関 地理」では、受験生の夏までの間にも取り組めるよう、論述問題を段階的に出題している。また、Z会の通信教育の講座では資料問題も数多く出題しているため、京大地理攻略の大きなポイントでもある資料読解力も磨くことができる。
実戦演習
制限時間を意識して、素早く正確に資料判読を行うとともに、短い指定字数の中で、的確に論述をまとめられるようになろう。Z会の通信教育の「最難関 地理」では、京大地理にも対応できる、資料の判読を行い、その判定結果をもとに論述するという構成の問題も出題しているので、自分の得意不得意、問題の難易度を意識し、時間内で得点を最大化できるよう取り組み方を身につけてほしい。
Z会でできる京大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!