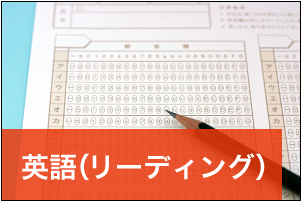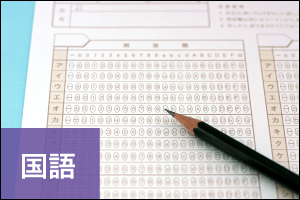化学基礎 – 共通テスト(2022年度)の分析&対策の指針
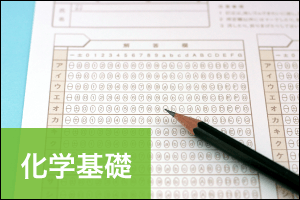
投稿日時:2022年2月8日
Z会の大学受験生向け講座の化学担当者が、2022年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。
共通テスト「化学基礎」の出題内容は?
まずは、科目全体の傾向を把握しましょう。分量、問題構成、難度などを解説します。
試験時間と配点
時間 / 配点:30分 / 50点
全体の傾向
● 難易度は、2021年度と比較して同程度であった。答えるべき問題の数も15と同じであったが、読解の負担がやや増加したため、全体の負担感は2021年度と比較してやや増加した。
●出題形式は、2021年度と同様、第1問が幅広い分野からの小問集合、第2問がリード文を読解した上で考察する問題が出題された。第2問は、化学基礎の知識はもちろんであるが、実験内容を正しく理解し、それを活用できるかが問われた。
●全体を通して、物質の性質や実験内容を正しく理解できているかを問う問題が多く出題されていた。
化学基礎の「カギとなる問題」は?
次に、化学基礎で「カギとなる問題」を見てみましょう。共通テスト特有の問題や、合格点をとるうえで重要な問題を取り上げ、攻略ポイントを解説します。
第1問 問6
強酸と弱酸の水溶液に関する問題。モル濃度ではなく質量パーセント濃度が与えられている点や、酸の強弱が中和の量的関係には影響しないことなど注意するべき点がいくつかあり、酸と塩基について正確に理解できているかが問われた。
第2問 問3a
正確な質量パーセント濃度の水溶液をどのように調製するかを問う問題。あるモル濃度の水溶液の場合は頻出であるが、質量パーセント濃度となると目新しい。落ち着いて考えれば平易だが、化学の問題集などではあまり見かけない問題なだけに、戸惑った受験生も少なくないだろう。
大問別ポイント/設問形式別ポイント
次に、化学基礎の出題内容を詳しく見ていきましょう。各問の難度や求められる知識・考え方を解説します。
大問 1:物質の構成、物質の変化 [標準]
・化学基礎の学習範囲を網羅した小問集合形式の出題であった。
・知識問題は平易な問題もいくつかあったが、物質の性質を細かく理解しておく必要があり、消去法で選びづらい問題も出題された。問4は洗剤に関する問題であり、化学基礎としてはやや発展的な内容であった。問8は各物質が何に使用されているかだけでなく、その目的まで理解しておく必要があった。
・計算問題のうち、問7は平易であり、問9もやや複雑ではあるが頻出の問題であるため確実に得点したい。一方、問6は酸と塩基について正確に理解していないとやや難しい。
大問 2:物質の構成 [やや難]
・「蒸留」をテーマとした問題が出題された。全体的に読解の負担感が大きかった。
・問1はエタノールの性質に関する問題。基本的な性質ではあるが、エタノールの性質について深く学習している受験生はそう多くないだろう。ただ、エタノールが電離しないことを知っていれば正解の選択肢を選べたかもしれない。
・問2はエタノール、水、エタノール水溶液それぞれを加熱したときの温度変化を比較する問題。比較のグラフおよびその説明文があり、見慣れない受験生にとってはそれを理解するだけで少し時間がかかっただろう。グラフの形と熱量の関係が理解できればさほど難しくはないが、選択肢もそれぞれ読解が必要となるため正答を導くためにやや時間がかかる。
・問3はエタノール水溶液の蒸留実験に関する問題。まず実験の説明文があり、それに関する問題が3問(a、b、c)出題された。aは水溶液を調製する方法についての問題であるが、正確な質量パーセント濃度の水溶液の調製法を問う問題はあまり見かけないため、決まったパターンの学習しかしていないと答えにくい。b、cは蒸留液の質量パーセント濃度を求める問題であり、実験内容を正しく理解し、それを活用できるかが問われた。
攻略へのアドバイス
最後に、次年度以降の共通テストに向けた攻略ポイントを確認しましょう。化学基礎で求められる力をふまえて、必要となる対策を解説します。
基本的な知識を確実に押さえる
2022年度共通テストでは、物質の性質について問う出題がいくつか見られ、いずれもやや発展的な内容や、受験生が学習を後回しにしてしまいそうな内容である印象であった。ただし、教科書に載っている知識が中心であるため、まずは教科書の知識を中心に学習していくとよいだろう。
文章読解にも慣れておこう
2021年度と同様、第2問では目新しいテーマの読解問題が出題された。見慣れないテーマの場合、説明文や実験操作を読解するためには想像以上に時間がかかる。2022年度の第2問 問3も、化学基礎の内容としては決して難しくないが、受験生は実験内容や結果を理解することに多くの時間を費やしただろう。初見のテーマであっても対応できるよう、模試や問題集で読解問題の演習を積んでほしい。
◆[専科]共通テスト攻略演習
共通テストの傾向をふまえた教材に取り組みます。毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
同じカテゴリの人気記事
共通テスト分析「傾向」と「対策」(2022年度)
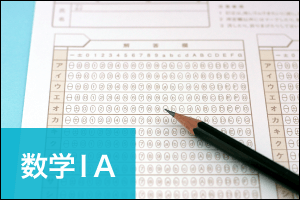
数学Ⅰ・A – 共通テスト(2022年度)の分析&対策の指針
Z会の大学受験生向け講座の数学担当者が、2022年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。 共通テスト「数学Ⅰ・... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む