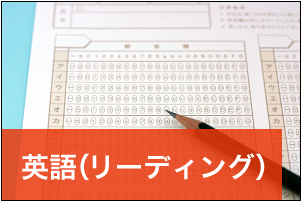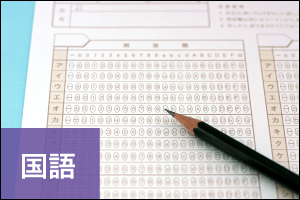生物基礎 – 共通テスト(2022年度)の分析&対策の指針
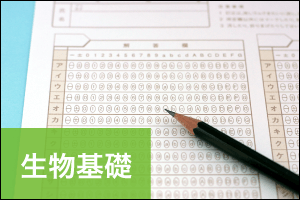
投稿日時:2022年2月8日
Z会の大学受験生向け講座の生物担当者が、2022年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。
共通テスト「生物基礎」の出題内容は?
まずは、科目全体の傾向を把握しましょう。分量、問題構成、難度などを解説します。
試験時間と配点
時間 / 配点:30分 / 50点
全体の傾向
●難易度は、2021年度共通テスト第1日程よりもやや高い。考察問題の比率は増加したが、設問数は同等だったため、負担感は2021年度と同等だった。
●各大問は基本的に1つの大分野からの出題だった。
●実験結果を考察する文において、生物用語を正しく理解して活用できているか問う形式が目立った。
●第1問文Bではリード文に会話が取り入れられていたほか、第2問の光学式血液酸素飽和度計や第3問の下水処理場での窒素除去などの身近な話題について考える問題も出題された。
生物基礎の「カギとなる問題」は?
次に、生物基礎で「カギとなる問題」を見てみましょう。共通テスト特有の問題や、合格点をとるうえで重要な問題を取り上げ、攻略ポイントを解説します。
第2問A
教科書に掲載されていない光学式血中酸素飽和度計とその根拠となるグラフを題材に、計測方法の原理や活用法を考察していく問題。問1と問2はいずれもグラフの活用がカギとなった。とくに問1では縦軸が相対値で表されているため、グラフの形状から概念的に考察を進めていく必要がある。
2022年度共通テストでは、他にもグラフを活用した数値計算・考察問題が出題され、数学的な思考力が身についているかどうかで点数に差がでるだろう。
大問別ポイント/設問形式別ポイント
次に、生物基礎の出題内容を詳しく見ていきましょう。各問の難度や求められる知識・考え方を解説します。
大問 1:(A)ATP量の計測 (B)DNAの抽出実験 [標準]
・文Aは、ATPを利用した細菌検出キットが題材だった。問1・問2の内容は確実に答えておきたい。問3は、ATP量から細菌数を推定するために前提となる条件を考察する。
・文Bは、DNAの抽出実験が題材だった。問4は、頻出の観点なので必ず押さえたい。問5は、グラフからDNAの濃度を推測した後に、DNA量を算出する必要があり、ミスをしやすい構成だった。問6は、仮説を証明するために必要な実験結果を考察する問いだった。試薬Yの特徴を先入観なく捉えて落ち着いて答えよう。
大問 2:(A)光学式血中酸素飽和度計の仕組みと高地での血中酸素濃度の測定 (B)免疫 [標準]
・文Aは、血中酸素飽和度の測定方法とその活用に関する出題。問1は図2のグラフを丁寧に読み取る必要があるだけでなく、光の透過実験で得られる結果について深く考えを進める必要があり、難易度が高かった。問2は、全Hbに対するHbO2の割合から酸素濃度を求める計算問題で、条件の見落としに注意。
・文Bは、免疫に関する問いが並んだ。問3と問4は、それぞれ基本的な知識が問われた。問5は、毒素を無毒化する「抗体」を注射したことでマウスが生き残れた理由を選択しよう。
大問 3:(A)ブナ林の生態系 (B)窒素循環のバランスと富栄養化 [やや難 ]
・文Aは、ブナの葉を食うガと、それを食う甲虫や菌類の関係が題材となった。問1は、確実に解答したい。問2は、陽葉に比べて陰樹の二酸化炭素吸収速度が遅いこと、また陽葉に比べて陰葉が初期に食われることから、木全体の二酸化炭素吸収速度の変化を考える。グラフには具体的な数値が示されていないので、傾向を掴むのが難しい。問3は、文Aの内容を先入観なしに読み込んで答えたい。
・文Bは、窒素循環の乱れにより生じる河川や海の富栄養化が題材だった。問4は、下水処理場における窒素除去の順序を窒素循環の流れから抜き出して考えるが、難易度が高かっただろう。問5は、森林植生の大部分が消失した後に流れ出す河川水の窒素濃度の変化を推測する問いだった。
攻略へのアドバイス
最後に、次年度以降の共通テストに向けた攻略ポイントを確認しましょう。生物基礎で求められる力をふまえて、必要となる対策を解説します。
地道な知識習得を大切にしよう
2022年度の共通テストでは、様々な問い方で知識を問う問題が出題された。グラフや図を使った問題も、基本となる知識がなければ太刀打ちできない。学習のはじめの知識習得を大切にするのはもちろんのこと演習をしていて点数が伸びないときにも自分の知識に穴がないか、立ち戻って確認しよう。
初見の問題に対する問題演習を積み重ねよう
2022年度共通テストでは、教科書に掲載されていない物質や実験、現象を題材にした問いが目立った。こういった問題も、特別な知識が必要ということはなく、自分のもつ知識や教科書に掲載されている実験の考え方を応用させて取り組めばよい。「[専科]共通テスト攻略演習」や共通テスト対策用書籍などで多くの問題に触れ、初見の題材にも取り組める自信をつけてほしい。
◆[専科]共通テスト攻略演習
共通テストの傾向をふまえた教材に取り組みます。毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
同じカテゴリの人気記事
共通テスト分析「傾向」と「対策」(2022年度)
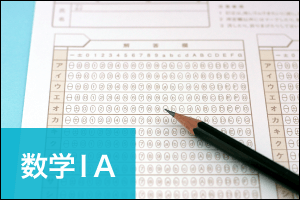
数学Ⅰ・A – 共通テスト(2022年度)の分析&対策の指針
Z会の大学受験生向け講座の数学担当者が、2022年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。 共通テスト「数学Ⅰ・... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む