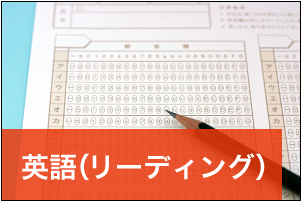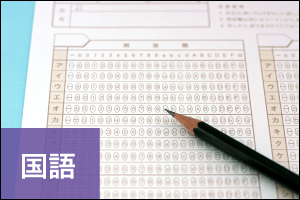日本史B – 共通テスト(2024年度)の分析&対策の指針
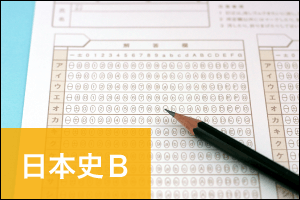
投稿日時:2025年1月13日
Z会の大学受験生向け講座の日本史担当者が、2024年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。
共通テスト「日本史B」の出題内容は?
まずは、科目全体の傾向を把握しましょう。分量、問題構成、難度などを解説します。
試験時間と配点
時間 / 配点:60分 / 100点
出題内容
●大問数は6題、小問数は32問であり、いずれも2023年度共通テストと同数であった。
●出題構成は、テーマ史、原始・古代、中世、近世各1題、近・現代2題で変動はなく、2023年度共通テスト同様、近・現代からの出題が全体の3割を超えている。また、昭和戦後史単独の設問は、2023年度共通テストから1問増えて3問見られた。なお、1980年代以降の出題は見られなかった。
●2024年度共通テストにおいても多数の資・史料などを用いた出題が見られ、文献史料や表・グラフ、写真に加えて、リード文や会話文の読解を要する問題が全体の半数近くを占めた。一方、2023年度共通テストで出題された、地図や模式図などは出題が見られなかった。
●提示された文献史料は17点であり、そのうち2点が現代語訳(大意)であった。2023年度共通テストと比較すると5点増加しており、受験生が見慣れないものも含まれていたが、教科書レベルの文献史料が例年よりも多かった。そのため、全体的な読解の負担感としては、2023年度共通テストと同程度であった。
●正誤問題は19問、年代整序問題は5問出題され、どちらの形式も2023年度共通テストと同数であった。また、空欄補充問題は5問出題され、2023年度共通テストの3問から増加した。
●多様な資・史料の読み取りが求められ、時間配分に注意を要する試験であったが、解答に必要な情報を汲み取りやすい出題が多かったため、2023年度共通テストと同程度の難易度であった。
日本史Bの「カギとなる問題」は?
次に、日本史で「カギとなる問題」を見てみましょう。共通テスト特有の問題や、合格点をとるうえで重要な問題を取り上げ、攻略ポイントを解説します。
第2問:問4
蘇の納入について、会話文・写真・文献史料を読解して解答を導く問題である。当時の国名や行政区画に関する知識と、複数資料から読み取った情報の両方を活用することがカギとなった。選択肢を先に読んでから正誤判定に必要な情報を探すなど、解答根拠を手際よく発見する必要があった。
第3問:問2
文献史料2点の読解問題である。永仁の徳政令(史料1)は頻出史料であり、取り組みやすかったかもしれないが、名主・百姓の事例(史料2)の読解に苦戦しただろう。本問は、史料1に記されている「非御家人」の規定を踏まえて、史料2の事例がどのように対処されるべきか考える必要があり、限られた時間の中で正確に史料を読み解けるかがカギとなった。
第6問:問1
3つの文献史料の中から、X・Yの説明に合致するものを選択する6択の問題。新たな出題形式であったが、ワシントン会議に関する知識をもとに、各史料のキーフレーズに着目していけば解答できただろう。なお、第3問問4においても同様の形式の出題が見られた。
大問別ポイント/設問形式別ポイント
次に、日本史の出題内容を詳しく見ていきましょう。各問の難度や求められる知識・考え方を解説します。
第1問:印刷の歴史 [標準]
・印刷の歴史に関する2つのリード文が提示された。未見の文献史料の読み取りを要する問題が2問出題され、問3は史料の内容を正確に読解する必要があった。その他の問題は日本史の基本知識で解答可能であった。なお、2023年度に見られた、大問の最後の問で他の設問の史料や会話文を再度読み取らせる形式の出題はなかった。
・問1は、知識を用いて下線部ⓐの兵乱の内容を特定し、兵乱が起こった時期を判定することが求められた。初出の形式であったが、奈良時代の政権担当者を時系列に沿って整理できていれば解答できた。
・問3は、文献史料2点の読解を要する問題であった。どちらの史料も分量は多くないが、内容を正しく把握することが求められ、正誤判断に苦戦した受験生は多かったと思われる。とくにYの「税免除の特権を撤廃」は、史料2中の「諸役あるべからず」の意図を正しく掴む必要があった。
・問6は、文献史料の内容と近代の印刷・出版に関する知識が問われた。選択肢a・bは、文献史料が読みやすかったため、正誤を判定しやすかった。選択肢c・dでは、明治・大正期の文化史の知識が求められた。
第2問:古代の食物 [標準]
・木簡の写真を用いた会話文形式の出題であった。文献史料や表、写真、会話文を読み取る問題が大問の大半を占めた。一部で判断に迷う問題も見られたが、ほとんどの問題は教科書レベルの知識で対応可能であった。
・問1では、2枚の写真が提示され、土器に関する説明の正誤を判定することが求められた。設問文にて2つの土器が甕(かめ)と甑(こしき)であることは明記されているが、写真や知識を活用してそれぞれの機能について考察する必要があったため、判断に迷った受験生も多かっただろう。
・問4では、複数資料から手際よく情報を取捨選択することが求められたが、解答根拠は見つけやすかった。
・問5は、表中の3つの空欄に当てはまる内容を知識を使って判断する8択の問題であった。木簡の資料としての性格、古代の文化・外交について問われたが、どれも基本的な知識があれば解答を導けただろう。
第3問:中世社会の特色 [標準]
・中世の政治権力や法令に着目した会話文を用いた出題であった。問2で永仁の徳政令、問4では『朝倉孝景条々』『今川仮名目録』『甲州法度之次第』といった、見慣れた文献史料が出題された。問2で史料の精読が求められた以外は、基本事項が中心の大問であり、全体として標準的な難易度だった。
・問2は永仁の徳政令に関する史料が2つ出題された。選択肢a・bでは史料1の内容について問われたが、頻出史料からの出題であったため、確実に正誤を判定したい。選択肢c・dは、史料1の規定を踏まえて、史料2(大意)の内容を正確に把握することが求められた。会話文中の「鎌倉幕府の出した法令は主に御家人を対象とした」という点も活用して考察する必要があり、やや難しかった。
・問4は、分国法に関する3つの文献史料のうち、X・Yの説明に合致するものを選ぶ6択の問題であった。どの文献史料も教科書レベルのものであったため、内容を特定することは難しくなかっただろうが、Xの「領国外の武士と結びつくこと」について、具体的にどのような事例をさすのか想起する必要があった。
・問5は、実力行使による問題解決という観点を設問文から読み取れば、「用水の取り入れ口の破壊」の事例が合致すると判断できただろう。
第4問:近世の輸出入品と社会・経済の関係 [標準]
・会話文形式の出題であった。未見の文献史料の読解を要する問題が出題されたが、読み取りの難度は高くなかったため、丁寧に目を通していけば、要点を掴むことはできただろう。一部の問題でやや細かい知識が問われたが、全体としては標準的な難易度であった。
・問2は、鎖国政策に関する並び替え問題であったが、Ⅰの「寄港地を平戸と長崎に限定した」時期を特定するのが難しかった。島原の乱(Ⅱ)後にポルトガル船が来航禁止となったことを踏まえて、寄港地の制限→来航禁止という順で、徐々に厳しい対策が採られるようになっていったと推測する必要があった。
・問5では、未見史料の読解が求められた。選択肢a・bは、史料から、多くの人が機織業を生業としたこと、結果的に農業がなおざりになったことを読み取ることができれば、解答を絞り込めた。選択肢c・dは、史料が「1835年」に作成されたことを設問文から読み取れば、時期の観点から正誤を判断できただろう。
第5問:幕末から明治期の洋服・銀行 [標準]
・「明治はじめて物語」というテーマをもとに作成された発表原稿を用いた大問であった。発表原稿や文献史料、グラフの読み取りが必要な出題がいくつか見られたが、どの設問も基本知識があれば解答可能であった。
・問1の空欄イは、発表原稿中の『洋服論』で指摘されている内容に注目すれば解答できた。
・問2では、1865年と1867年における日本の輸入に関するグラフが出題され、グラフから輸入額の変化を読み取ることが求められた。改税約書に関する知識を用いるか、関税率の引き上げが及ぼす貿易への影響を考慮すれば、正誤は判断できただろう。
第6問:二度の世界大戦後の日本と国際社会の関係 [標準]
・世界大戦後の日本と国際社会の関係についてまとめたプリントが2つ提示され、外交に関する問題が多く出題された。問6に苦戦した受験生が多かっただろうが、それ以外の問題は標準レベルのものであった。
・問1は、日本が締結した3つの条約のうち、ワシントン会議で締結されたものと廃棄されたものをそれぞれ選ぶ問題であった。条約は文献史料の形式で提示されたが、条約を特定するための情報が拾いやすかったため、ワシントン会議に関する基本知識を漏れなく押さえられていれば、解答できただろう。
・問6は、第二次世界大戦後にアメリカと結んだ条約・協定に関する並べ替え問題であった。MSA協定(Ⅱ)と日米新安全保障条約(Ⅲ)を特定するのが難しく、苦戦しただろう。各条約・協定の内容を押さえておくだけでなく、戦後の日米関係の変遷を整理して理解しておく必要があった。
攻略へのアドバイス
最後に、次年度以降の共通テストに向けた攻略ポイントを確認しましょう。日本史で求められる力をふまえて、必要となる対策を解説します。
2025年度共通テストで「歴史総合、日本史探究」を選択する場合も、以下の点を意識して学習に励みましょう。
基本的な知識を確実に押さえる
共通テストでは、資・史料読解力や思考力をはかる問題も出題されるが、多くの問題で、知識の確認や活用が求められる。まずは、教科書レベルの知識を押さえていることが重要である。教科書や用語集などを活用して基本的な知識をしっかり固めよう。
資料(史料)読解力を磨く
共通テストでは、教科書などに掲載されていないような文献史料や絵図、グラフなど初見の資料を、その場で読み取り、設問に即して解答することが求められる。資・史料問題対策の第一歩は資料(史料)に慣れることである。日頃から史料集や図説を活用し、「資料(史料)を読むこと」に慣れておこう。
問題演習を積む
共通テストでは、知識の活用などを求める問題が出題される。このような形式の問題は、一問一答的な学習では対応しきれない。様々な形式の問題に取り組み、実戦力を養おう。
ご案内
来年(2025年度)の共通テストに臨む方へ
![[専科]共通テスト攻略演習(高3生向け)](https://www.zkai.co.jp/kyotsu-test/wp-content/uploads/sites/34/2024/01/24kyotsu_pc.png)
本番を想定した質の高い演習で得意科目9割突破へ!
本講座では、9割突破に向けて、毎月着実にレベルアップできるカリキュラムをご用意。
毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
受験に役立つ情報をLINEで配信中!
Z会では、「Z会の通信教育」LINE公式アカウントで共通テストをはじめとする大学受験に役立つ情報を配信中。学習アドバイス記事やお得なキャンペーンのご案内、おすすめ講座情報などを随時お届けしています。ぜひご登録ください。
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!
同じカテゴリの人気記事
共通テスト分析「傾向」と「対策」(2024年度)
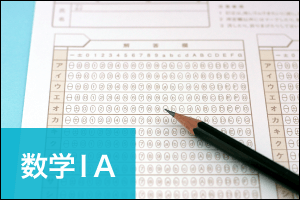
数学Ⅰ・A – 共通テスト(2024年度)の分析&対策の指針
Z会の大学受験生向け講座の数学担当者が、2024年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。 共通テスト「数学Ⅰ・A 」の出題内... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む