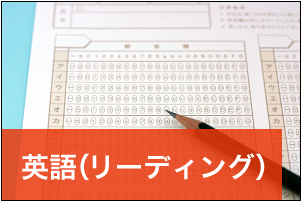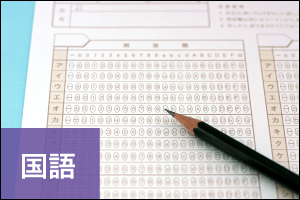生物基礎 – 共通テスト(2023年度)の分析&対策の指針
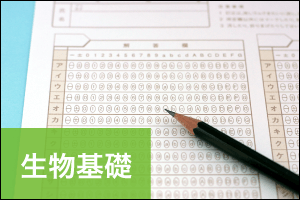
投稿日時:2023年2月1日
Z会の大学受験生向け講座の生物担当者が、2023年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。
共通テスト「生物基礎」の出題内容は?
まずは、科目全体の傾向を把握しましょう。分量、問題構成、難度などを解説します。
試験時間と配点
時間 / 配点:30分 / 50点
全体の傾向
●難易度は、2022年度共通テストと同等であるが、知識問題・考察問題ともに検討を要する設問が多く、負担感は2023年度の方がやや重い。
●実験結果を考察する文において、生物用語を正しく理解して活用できているか問う形式が目立った。
●第2問文Aでリード文に会話が取り入れられていたほか、第3問文Aでは水槽の生態系内の物質循環という身近な話題について考える問題が出題された。
●各大問は基本的に1つの大分野からの出題だが、第2問・第3問では別の大分野の知識が必要な問題も出題された。2021年度にも同様の出題があった。
生物基礎の「カギとなる問題」は?
次に、生物基礎で「カギとなる問題」を見てみましょう。共通テスト特有の問題や、合格点をとるうえで重要な問題を取り上げ、攻略ポイントを解説します。
第2問問5
免疫系を操作した3系統のマウスそれぞれに対する実験について、マウスが生存した理由として正しいものを選択する正誤判断問題である。選択肢は各マウス・実験に対する二択問題が3つ続く構成となっており、1つ間違えると-3点となる(正解で4点、1つ間違えた選択肢は1点の配点)。設問文にある各マウスの特徴を正確に押さえ、実験でマウス体内で起こることを推察して選択肢を検討したい。
大問別ポイント/設問形式別ポイント
次に、生物基礎の出題内容を詳しく見ていきましょう。各問の難度や求められる知識・考え方を解説します。
大問 1:(A)原核細胞と真核細胞 (B)DNAの複製と細胞周期 [標準]
・文Aでは、原核細胞と真核細胞の比較(問1)と、葉緑体が共生した際の代謝に関する遺伝子の発現の変化(問2)が出題された。問1は、選択肢を丁寧に読む必要がある。
・文Bでは、DNAの複製に関する計算問題(問1)と、複製の進行と細胞周期の関連を踏まえた問題(問2 ・3)が出題された。問3は、体細胞は2n・精子はnであることに気をつけたい。問5は、DNA量が2であり物質Aを取り込んでいない細胞は、DNAの複製は終わっているが分裂は終わっていない細胞であることから考える。
大問 2:(A)脂肪の消化における胆汁の作用 (B)免疫 [標準]
・文Aは、胆汁による脂肪の分解促進の作用を考える実験考察問題である。問1は「生物の特徴および遺伝子」で学ぶ酵素の実験を踏まえると解きやすい設問であった。問2は、図の界面の高さの修正が入った。化学基礎や家庭科で学ぶ界面活性剤を想起できれば、層Zと、得られる結果の理解が容易だっただろう。
・文Bは、2021年度第1日程・2022年度本試験に続き、免疫からの出題である。問3は第1問問1と並び、選択肢を丁寧に読む必要がある。問4は、抗原提示の場と、B細胞以外の体液性免疫に関わる免疫細胞が問われた。問5は2択が3つ並んだ設問である。
大問 3:(A)水槽内の物質循環 (B)世界のバイオームと植生の季節変動 [やや難 ]
・文Aは、水槽の生態系内の物質循環が題材となった。問1の空欄イ・ウは、二次同化が問われた。単純な物質から複雑な物質をつくるという同化の定義に即して選択する。問2は、水槽内の出来事として語られているが、消費者の排泄物などに含まれる有機窒素からの窒素循環と考えればよい。問3は設問文の説明をよく読んでから選択肢を検討したい。
・文Bは、気候とバイオームの関係を正確に理解していなければ解けない問題が並んだ。問4は植生に関する知識問題で、第1問問1・第2問問3と並んで選択肢を丁寧に読む必要があり、またバイオームの世界分布も理解している必要があった。問5は指定のバイオームの植生の季節変動を踏まえたグラフ選択問題である。
攻略へのアドバイス
最後に、次年度以降の共通テストに向けた攻略ポイントを確認しましょう。生物基礎で求められる力をふまえて、必要となる対策を解説します。
地道な知識習得を大切にしよう
2023年度の共通テストでは、様々な問い方で知識を問う問題が出題された。計算問題や、グラフや図を使った問題も、基本となる知識がなければ太刀打ちできない。知識習得を大切にするのはもちろんのこと、演習をしていて点数が伸びないときにも自分の知識に穴がないか、立ち戻って確認しよう。
初見の問題に対する問題演習を積み重ねよう
共通テストでは、教科書に掲載されていない物質や実験、現象を題材にした問いが目立つ。こういった問題も、特別な知識が必要ということはなく、自分のもつ知識や教科書に掲載されている実験の考え方を応用させて取り組めばよい。「[専科]共通テスト攻略演習」や共通テスト対策用書籍などで多くの問題に触れ、初見の題材にも取り組める自信をつけてほしい。
◆[専科]共通テスト攻略演習
共通テストの傾向をふまえた教材に取り組みます。毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
受験に役立つ情報をLINEで配信中!
Z会では、「Z会の通信教育」LINE公式アカウントで共通テストをはじめとする大学受験に役立つ情報を配信中。学習アドバイス記事やお得なキャンペーンのご案内、おすすめ講座情報などを随時お届けしています。ぜひご登録ください。
同じカテゴリの人気記事
共通テスト分析「傾向」と「対策」(2023年度)
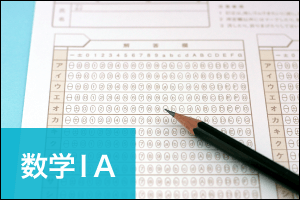
数学Ⅰ・A – 共通テスト(2023年度)の分析&対策の指針
Z会の大学受験生向け講座の数学担当者が、2023年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。 共通テスト「数学Ⅰ・... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む