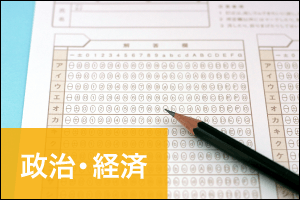「物理」2020年度センター試験分析
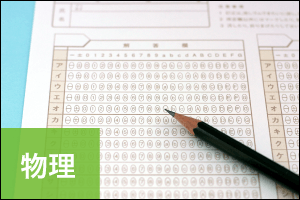
投稿日時:2020年1月23日
Z会の大学受験生向け講座の科目担当者が、2020年度のセンター試験を分析。出題内容・各問の分析、攻略ポイントを詳しく解説します。
2020年度センター試験「物理」の出題内容
試験時間と配点
- 時間 / 配点:60分 / 100点
全体の傾向
- 第1問から第4問が必答問題で、分野は小問集合、電磁気、波動、力学であった。また、選択問題は2019年度と同様に、第5問は熱力学、第6問は原子であった。合計で大問5問、小問20問を解答する形式であり、小問数は昨年の22題から少し減った。しかし、全体を通して組合せの問題が多かったため、全体の分量は昨年並みであった。また、難易度も昨年並みであった。
- 共通テストの試行調査で出題されたような実験や実験結果の考察を中心とする問題は出題されず、典型的な問題が多く出題された。
- 計算量は昨年に比べてやや減った。また、設問ごとの難易度のばらつきが、昨年に比べて大きくなった。
2020年度センター試験「物理」の各問の分析
第1問(25点):<必答>小問集合[やや易]
問1 剛体のつり合い(力学)
問2 2本の直線電流が作る磁力線(電磁気)
問3 音波の干渉(波動)
問4 理想気体の状態変化(熱力学)
問5 小球の衝突(力学)
第2問(20点):<必答>電磁気 [A:標準 B:標準]
A. 円筒形の素子を用いたコンデンサー回路
問1 素子に電池をつないだときの回路図
問2 回路中の二点間の電圧
B. 電場、磁場中での荷電粒子の運動
問3 荷電粒子の軌道、運動エネルギー
問4 荷電粒子の電場による加速
第3問(20点):<必答>波動[A:やや難 B:標準]
A. 水面波のドップラー効果
問1 観測者が運動するときの波長、周期
問2 波源が運動するときの波形
B. 光の干渉
問3 ヤングの実験における光の色と明線間隔の関係
問4 ニュートンリングの干渉条件、媒質を変化させたときの明環半径の変化
第4問(20点):<必答>力学 [A:やや易 B:標準]
A. 衝突、鉛直面内の円運動
問1 2物体の衝突
問2 円運動するための条件
B. ばねにつながれた2球の運動
問3 力のつり合い
問4 落下直後の2球の加速度
第5問(15点):<選択>熱力学 [やや難]
水中に逆さに立てられた容器で封じられた気体
問1 浮力を受ける容器のつり合い
問2 容器を沈めたときの気体の状態変化
問3 容器が水底から浮かぶ条件
第6問(15点):<選択>原子 [やや易]
原子核・放射線
問1 核反応
問2 結合エネルギー
問3 電場中での放射線の軌道
2020年度センター試験「物理」の攻略ポイント
・出題分野、難易度、分量は昨年と同程度。この3、4年で大きな変化は見られない。
→特定の分野に偏ることなく、教科書全体を幅広く学習するとよい。
・図の選択問題、物理量の変化を定性的に問う問題のようなセンターに特徴的な設問については、その数は例年並みで大きな変化はなかった。また、2019年度に出題があった正誤、語句選択といった設問は無かった。
→センター試験から共通テストに変更されても、図の選択や定性的な設問は引き続き一定量出題されることが予想される。物理を勉強する際はただ解法を覚えたり計算練習に終始したりするのではなく、どのような物理現象が起きているのかを頭の中でイメージできるようにすることを心がけたい。
同じカテゴリの人気記事
センター試験分析
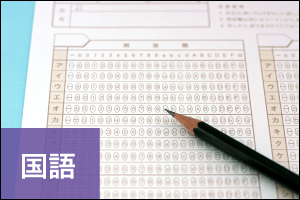
「国語」2018年度センター試験分析
2018年度センター試験分析速報 ■分量と難度の変化(時間/配点:80分/200点) 全体の難度は昨年度よりやや易化したが、センター試験としては標準的な出題である。時間に対しての負担感も標準的なも... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む