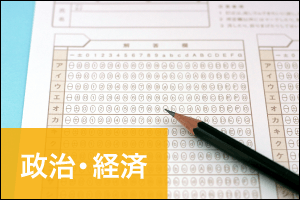「地理B」2020年度センター試験分析
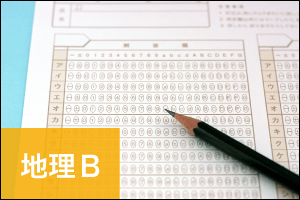
投稿日時:2020年1月25日
Z会の大学受験生向け講座の科目担当者が、2020年度のセンター試験を分析。出題内容・各問の分析、攻略ポイントを詳しく解説します。
2020年度センター試験「地理B」の出題内容
試験時間と配点
- 時間 / 配点:60分 / 100点
全体の傾向
- 大問6題、小問数35は2019年度と同様。分量は図表が減少したものの、例年並みである。テーマも大きな変化はない。
- 単答問題が大幅に増加したことで解答がしやすくなった。また、統計数値や知識を「知っているか知らないか」のみで解答可能な問題が散見された。
- 難易度は、2019年度に比べて資料の読み取りがしやすい問題が多く、また組合せ問題も減少したため、全体的にやや易化した。平均点も2019年度に比べ高くなっており、ケアレスミスをしないことと、確実な資料読解力が求められた。
2020年度センター試験「地理B」の各問の分析
第1問(17点):世界の自然環境と自然災害 [やや易]
・問2のハイサーグラフは、北半球と南半球の区別がつきやすい図となっており、判別がしやすかったと思われる(第4問問2の雨温図の判別も同様)。
・問3の地震の震源と火山の両方が分布する地域を答える問題は、クのアラスカ半島南部からアリューシャン列島の地域は判別できても、もう1地域で迷った受験生も多かったと思われる。
・問5は、Sの南アメリカの気候分布が複雑な地域であったため、判別がしにくかったと思われる。
・問6の南北アメリカ大陸の自然災害については、ハリケーンの襲来や、カリフォルニア州の森林火災など、ニュースでも頻繁に取り上げられていた内容でもあったため、迷わず判定できたと思われる。
第2問(17点):資源と産業 [標準]
・問1は4カ国のマンガン鉱の輸入量の推移を示したグラフであった。マンガン鉱の輸入量について、具体的な数値や順位までは押さえきれていない受験生がほとんどであったと思われる。しかし、問題文に「鉄鋼の生産など様々な工業で用いられている」とあることから、工業生産の発展度合いなどからも類推することが可能である。
・問5の風力発電の割合が高い国は、恒常風帯に位置する国かどうかが判断のポイントとなった。また、各国の鉱業の特徴からも判別できる。
・問6は日本の1人当たりGNIのおおよその数値を知っていれば解答可能な問題であるが、人口1人当たりの研究開発費が高い2カ国(スイス・日本)のうち、金融・保険業の従業者割合からもスイスが特定でき、もう一方を日本と判定できる。
第3問(17点):都市と村落 [標準]
・問1は、有名な大都市はどこにあるか、人々が暮らしやすい気候帯はどこの地域か、を考えれば判定しやすい。
・問4は地理では珍しいテーマからの出題。1996年はホンコンの中国返還前であることも思い出したい。また、フィリピンは英語が公用語の1つであることからも類推できる。
・問5は、東日本と西日本の都市に分け、各都市の人口規模と併せて考えたい。
・問6は栃木県宇都宮市の統計が取り上げられた。核家族世帯の分布の判定が難しいが、消去法でも解答できる。
第4問(17点):東南アジアとオセアニア地誌 [標準]
・問1は、第1問問3と同様、プレート境界の位置を押さえられていれば容易である。
・問3は、オーストラリアにサバナ気候区が分布していること、世界に占める生産の集中度合いから判別できる。
・問4は、各鉱産資源の主産地を思い出しながら判定したい。
・問5は、貿易大国である中国は判別しやすい。そこを起点にして、各国との貿易品の特徴などから判断したい。
第5問(14点):中国とブラジルの比較地誌 [標準]
・問1は、図2の判定で迷う受験生が多かったと思われる。河口から3,000kmまでの各国の地形の特徴をまず判断したい。
・問2は、中国における牛乳と小麦の生産地の区別が難しい。一方のブラジルは、北部が熱帯に属することと、小麦は寒冷地での栽培が多い、という知識から判断できる。
・問3は、図の読み取りに少し迷うものの、図が生産額の割合を示していることを思い出し、軽工業は割合が低くなると考えたい。また、国ごとの鉱工業の特色を思い出したい。
・問5は、1990年に日本の出入国管理法が改正されたことにより、ブラジルを初めとする日系人の入国が容易になったことで居住者が増加したことを思い出せばよい。
第6問(18点):甲府盆地とその周辺の地域調査 [やや易]
・問1は、東京はヒートアイランドで夜でも気温が下がらない、冬季は雪が降って交通が混乱する、などの情報から、判定に迷った受験生が多かったと思われる。
・問3の地形図の読図は、地図を立体的に捉える選択肢は少なく、地図記号や土地利用の読み取りが中心であったため、判読がしやすかったと思われる。
・問4と問6は、文章で書かれていることがグラフではどのように表現されるのかを推測しながら判定したい。資料読解力を必要とする問題であった。
同じカテゴリの人気記事
センター試験分析
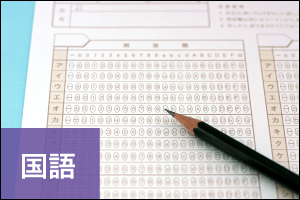
「国語」2018年度センター試験分析
2018年度センター試験分析速報 ■分量と難度の変化(時間/配点:80分/200点) 全体の難度は昨年度よりやや易化したが、センター試験としては標準的な出題である。時間に対しての負担感も標準的なも... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む