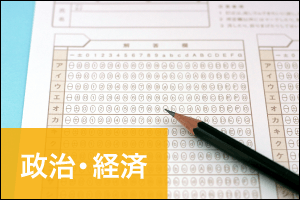「国語」2020年度センター試験分析
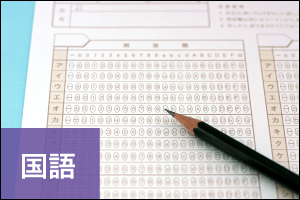
投稿日時:2020年1月25日
Z会の大学受験生向け講座の科目担当者が、2020年度のセンター試験を分析。出題内容・各問の分析、攻略ポイントを詳しく解説します。
2020年度センター試験「国語」の出題内容
試験時間と配点
- 時間 / 配点:80分 / 200点
全体の傾向
- 全大問で問題文の字数が減少し、設問数も2019年度から1問減少した。一部に目新しい出題が見られるものの、センター試験としてはオーソドックスな難度の出題。
- 第1問(評論)の問5で〈文章の内容に関する生徒間の会話〉をもとにした出題がなされた。同様の出題は2016年度、2018・2019年度にも同じく第1問で見られたが、本文の趣旨を踏まえて具体例を考える必要がある点に注意を要する。
- 第4問(漢文)では漢詩が出題された。問3は、漢詩中の情景描写を表しているイラストを選択させる新傾向の出題だった。
2020年度センター試験「国語」の各問の分析
第1問(50点):現代文(評論)河野哲也『境界の現象学』[やや易]
・「レジリエンス」という概念の変遷と現代における意義について、生態学・環境システム、社会福祉・ソーシャルワーク、エンジニアリングなど様々な分野の実例を踏まえて述べた文章。2019年度に比べて問題文の字数が1,000字近く減少しており、述べられている概念も難解なものではないため、比較的時間上の余裕をもって問題に取り組めただろう。
・問2~4は部分読解に関する設問。該当箇所の大意そのものはいずれも難しくないが、一部の紛らわしい選択肢を吟味するのに力を要する。問6は文章の表現と構成に関する出題だが、誤りを含む選択肢の根拠がいずれも明確なため、正答を選ぶのは比較的容易であった。
・問5は生徒の対話場面からの出題であることに加え、〈問題文中の内容を、異なる具体的事例に適用する〉点で複数のテキスト・文脈を比較検討する必要があり、その意味でも目新しい出題。とはいえ、〈環境の変化に対して流動的に自らの姿を変更しつつ適応する能力〉としての「レジリエンス」の意味合いを正しくつかめていれば、正答を選ぶのは難しくない。
第2問(50点):現代文(小説)原民喜「翳」[標準]
・2019年度と同様、男性作家による1940年代の作品。70年以上前の作品で注も多く、読みにくく感じた受験生もいるかもしれない。時代背景を念頭に、登場人物の心情を丁寧に読み解いていく必要がある。
・問1は定番の語句の意味問題だが、文脈ばかりを重視すると誤答選択肢にひっかかってしまう。判断の基準はあくまで辞書的な語義におくこと。
・問2~問5も例年のように心情を問う問題となっていた。問2の選択肢は1行、問3と4は2行、問5は3行だが、選択肢の読み取りに困難はなかったはずだ。
・問6は「文章の表現に関する説明として適当でないもの」を二つ抜き出す問題で、消去法で二つ残せるはずだが、正解肢も「明らかにこれが正しい」という内容ではないので、少々苦労する可能性がある。
・選択肢の瑕疵を確実に見抜くためには、本文に関わる幅広い常識や素養が必要で、その修得には時間がかかる。常日頃から幅広い読書や、幅広い年齢層の人との会話を心がけておくとよいだろう。
第3問(50点):古文 『小夜衣』[標準]
・中世の擬古物語からの出題。2019年度に比べ問題文の分量は減少した。一文が長く、やや読みにくく感じられたかもしれないが、リード文・注で詳しく場面状況が説明されているので見落とさずに、丁寧に一文一文の主語を押さえて読解していけばよい。
・問2の文法問題では、2019年度同様敬意の方向を問う問題が出題された。登場人物・場面設定を正確に把握することが求められている。
・傍線部の説明問題である問3・問4は、傍線部前後の文脈・ 傍線部の正確な逐語訳を踏まえて各選択肢を吟味する必要がある。
・問6は、問題文全体に目を配る必要がある設問で難度が高いが、問題文の分量が減少した分、時間をかけて丁寧に取り組みたい。
第4問(50点):漢文 『文選』[標準]
・六朝時代の詩人謝霊運の五言詩からの出題。センター本試験での漢詩単独の出題は実に1992年度以来なので、ノーマークの受験生も多かったかもしれない。結果、内容以前に形式で「難しい」と感じてしまった受験生もいたかもしれないが、落ち着いて読めば、内容的には必ずしも難しくないことがわかったはずである。複雑な構文・句形があるわけでもなく、景物に託した心情を読み取らせようとしているわけでもない。与えられた漢文の中に既知の語彙や句形を探して得点を稼ぐ、という姿勢ではなく、全体としてまとまりをもった一つの作品として漢文を読む、という姿勢ができていれば、おのずと正解にたどりつける出題となっている。
・とはいえ、基本的な語彙や句形などの漢文知識が重要でないと言っているわけではない。問1(語の読み)や問4(押韻、対句)は、それらを問うものであった。
・選択肢がイラストの問3が話題となったが、形式は目新しいものの、特に解答に迷うほどのものではない。
・基本語彙・文法の知識は必須だが、設問の過半が本文の解釈に関わるもののため、知識だけを丸暗記するのではなく、内容理解まで踏み込んだ演習に丁寧に取り組めたかどうかで、差がついたと思われる。
2020年度センター試験「国語」の攻略ポイント
・全体の難度は昨年度と同程度で、センター試験としては標準的な出題である。問題文の分量が減少し、選択肢の長さも短くなったため、演習を積んだ受験生であれば十分時間的な余裕を確保できただろう。一部に共通テストを意識したと思われる新傾向の設問も見られたが、全体としてオーソドックスな内容読解を問う設問が中心であり、演習量によって差がつく出題であった。
・共通テストを意識したと思われる〈文章と図を関連付けた理解〉〈言語活動場面の読解〉といった設問が出題された。文中から読み取れる情報を整理して理解する力が問われているといえる。
同じカテゴリの人気記事
センター試験分析
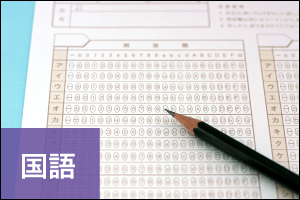
「国語」2018年度センター試験分析
2018年度センター試験分析速報 ■分量と難度の変化(時間/配点:80分/200点) 全体の難度は昨年度よりやや易化したが、センター試験としては標準的な出題である。時間に対しての負担感も標準的なも... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む