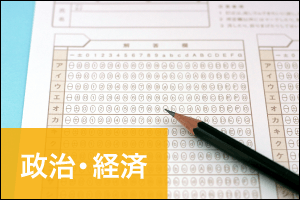「日本史B」2020年度センター試験分析
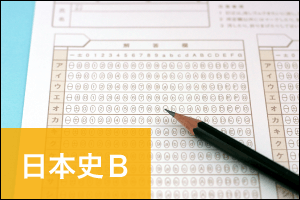
投稿日時:2020年1月23日
Z会の大学受験生向け講座の科目担当者が、2020年度のセンター試験を分析。出題内容・各問の分析、攻略ポイントを詳しく解説します。
2020年度センター試験「日本史B」の出題内容
試験時間と配点
- 時間 / 配点:60分 / 100点
全体の傾向
- 出題構成は、例年通り大問6題(テーマ史、原始・古代、中世、近世各1題、近・現代2題)、小問36問であった。
- 例年通り、近・現代の出題割合が高く、全体の約3割を占めた。但し、明治・大正期からの出題が中心であり、昭和戦後期からの出題は2019年度より減少し、1問のみであった。
- 例年に比べて文化史の出題が多く、また、社会・経済史を中心とした大問もあったことから、各分野を満遍なく学習できていたかどうかで、出来に差がついただろう。しかし、基本的な事項についての出題が中心で、戦後史の出題が少なかったこともあり、標準的な難易度の試験であった。
- 2019年度に出題されなかった図版(写真・絵画・地図)を用いた問題が、3問出題された。統計資料を用いた問題は、2018年度・2019年度に続き出題されなかった。
- 史料問題が、2018年度・2019年度に続き4問出題された。いずれも史料の記述内容を判断する問題で、史料の読み取りが求められた。
- 年代整序問題は、2019年度より1問増加して5問出題された。
2020年度センター試験「日本史B」の各問の分析
第1問(16点):教育史と歴史書の意義 [標準]
・2018年度・2019年度に続き会話文の形式であった。
・問2は、図(平安京左京)と写真(『続日本紀』の写本)が出題されたが、問われたのは藤原氏の大学別曹と金沢文庫についての基本的な知識であった。
・問6は、初見史料が出題され、史料の内容と、大正期の思想家について問われた。史料読解については、注も含めて丁寧に読めば判断できる。思想家については、吉野作造から大正デモクラシーを想起できれば解ける問題である。
第2問(16点)::古代国家の辺境支配 [標準]
・問3は、国府と城柵の遺構を描いた図が出題された。戸惑ったかもしれないが、注を含めて丁寧に読み取れば正誤の判断は容易である。
・問6は、初見史料が出題された。知識からは正誤を判断できないので、注を含めて丁寧に読み取る必要がある。
第3問(16点):中世社会と入浴の歴史[標準]
・問2は、受験生にとってなじみのある「阿氐河荘百姓等訴状」が出題された。史料の読解が求められているが、史料の主旨を把握していると解きやすかっただろう。
・問6は、中世から近世初期にかけての流通経済についての年代整序問題である。キーワードから大まかな時期を判断できれば解ける問題である。
第4問(16点):中世末から近世における銀と鉄の生産・流通 [標準]
・問6は、初見史料を読み取る問題であり、見慣れない語句に戸惑ったかもしれないが、第2問問6と同様に、注を用いて丁寧に読み取れば判断できる。
第5問(12点):幕末から明治前期の民衆運動 [標準]
・問4は、自由民権運動の激化事件(1880年代)と同時期の出来事についての問題である。二科会や日本郵船会社の設立といったやや細かい知識が求められ、判断に迷っただろう。
第6問(24点):近・現代の風刺漫画 [標準]
・問2は、「台湾出兵」「日露戦争」「西南戦争」の語から時期を判断しよう。台湾出兵と西南戦争は時期が近く、前後関係の判断に迷ったかもしれない。
・問8は、唯一の戦後史からの出題である。風刺漫画が示されたが、設問文や書き添えられた文字から、農地改革についての問題であることは容易に判断できる。問われている内容は基本的なもので、解きやすい問題であった。
2020年度センター試験「日本史B」の攻略ポイント
・センター試験は、基本的に教科書から出題されているが、本文だけでなく、図版や注などを含めた内容の理解が求められる。新しく始まる共通テストでも、教科書レベルの知識・理解は必須である。教科書の重要語句や説明をしっかりと理解するという基本的な学習を怠らないようにしたい。
・近年のセンター試験では、1問の中で分野をまたがる事項を扱った問題や、古代〜近・現代など、時代をまたいだ問題が出題される傾向にある。共通テストでも、「推移・変化」「時系列の理解」や「歴史的事象のつながり」を問う出題が予想される。同時代の横のつながりや、同一テーマでの変遷を意識した学習は、共通テスト対策ではより重要になる。
【史・資料問題】
・近年のセンター試験で見られる史料問題は、初見の文献史料について、史料の内容理解を問う問題が中心になっている。史料を読み取る問題では、史料本文と注を照らし合わせながら丁寧に読解していくことがポイントとなる。共通テストでも、史料読解問題の出題が予想されるので、史料を読み取る練習を積んでおきたい。
・写真・絵・地図・統計資料など、多様な資料を用いた問題は、共通テストでも出題されることが予想される。ふだんから各種資料に親しみながら学習することが大切である。また、統計資料を確認する際には、統計資料の数字の変化や、変化の背景にある歴史事項を考えるということを意識しておこう。
同じカテゴリの人気記事
センター試験分析
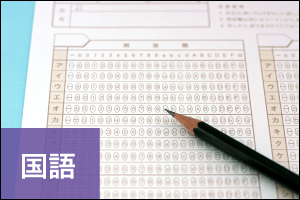
「国語」2018年度センター試験分析
2018年度センター試験分析速報 ■分量と難度の変化(時間/配点:80分/200点) 全体の難度は昨年度よりやや易化したが、センター試験としては標準的な出題である。時間に対しての負担感も標準的なも... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む