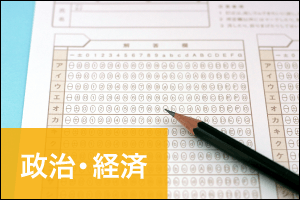「生物」2020年度センター試験分析
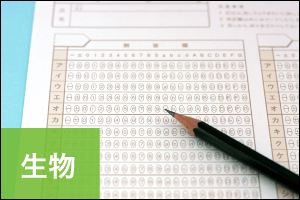
投稿日時:2020年1月23日
Z会の大学受験生向け講座の科目担当者が、2020年度のセンター試験を分析。出題内容・各問の分析、攻略ポイントを詳しく解説します。
2020年度センター試験「生物」の出題内容
試験時間と配点
- 時間 / 配点:60分 / 100点
全体の傾向
- 考察問題の比率はやや下がり、正確な知識を問う設問がやや増えた。難易度は2019年と同等である。
- 設問数、ページ数、選択肢数が増え、全体の分量・負担感はやや増えた。
- リード文や設問文、選択肢などの分量が多く、解答時間内にすべてを解き切るには効率的な読み取りが欠かせない。
- 選択問題は、2020年度も第6問はミクロ的な分野、第7問はマクロ的な分野からの出題であった。
2020年度センター試験「生物」の各問の分析
第1問(18点):<必答>生命現象と物質 [A:やや易 B:標準]
・A. 転写調節
・B. 細胞分裂
A.は原核生物の転写調節と真核生物の転写に関する知識問題である。問3は確実に得点したい。
B.は細胞分裂に関する計算問題とグラフ読み取りの問題である。50時間はサンプル採取の時間である、求めるのは分裂期の時間であるなどの点に注意して、ケアレスミスを防ぎたい。
第2問(18点):<必答>生殖と発生 [A:やや難 B:標準]
・A. 細胞の分化
・B. ABCモデルと減数分裂
A.は動物の発生の知識問題とホヤの卵を用いた細胞分化の実験考察問題である。問1は確実に得点したい。問2では「黒卵片のみに」の「のみ」を見落とさないこと。
B.はアサガオの変異をABCモデルに結びつける考察問題と減数分裂に関する知識問題である。ABCモデルの理解があいまいでも、リード文から各遺伝子の役割は推定できるので、確実に得点したい。問5は、組換えと乗換えの違いに注意したい。
第3問(18点):<必答>生物の環境応答[A:標準 B:やや易]
・A. 動物の刺激受容
・B. アブシシン酸と乾燥耐性、休眠打破
A.はヒトの眼の遠近調節、伝導・伝達と筋収縮の知識問題と、カイコガ雄の性フェロモン受容と雌への接近に関する実験考察問題である。
B.は植物の乾燥耐性に関する変異とアブシシン酸との関係についての実験考察問題と、種子の休眠打破に関する知識問題である。実験考察はグラフが明確で選択肢も少なく、取り組みやすい。
第4問(18点):<必答>生態と環境 [A:やや易 B:標準]
・A.間接効果、絶滅の渦、種内関係
・B.物質生産、植物の特性と生産量
A.は間接効果を、実際の外来種と在来種・栽培植物の関係にあてはめる問題と、絶滅の渦、社会性昆虫などの種内関係に関する知識問題である。
B.は植物の物質生産の知識問題と、環境への適応と被食防御に関する実験考察の穴埋め問題である。
第5問(18点):<必答>生物の進化と系統 [A:標準 B:標準]
・A. 進化のしくみ、ハーディ・ワインベルグの法則、分子進化
・B. 植物の分岐・分類と進化
A.は進化のしくみに関する知識問題、ハーディ・ワインベルグが成立する集団の遺伝子頻度を求めるグラフ選択問題、そして、非同義置換・同義置換の頻度から遺伝子産物の影響の大きさを考える、大小関係の数式選択問題である。問2はグラフの縦軸に注意したい。問3は設問文にある非同義置換、同義置換の説明を見逃さず、同じペプチドができるのはどちらかを踏まえて考える。
B.は各植物種の分岐を推定する問題、維管束植物の出現時期を問う知識問題、乾燥したコケの復活に関する計算問題である。分岐で検討する植物種は、身近な種、教科書にある種、名称から何植物か明白な種なので、分類の知識があれば迷わないだろう。問2はやや細かい知識だが、3億年前は木生シダの栄えた石炭紀であると思い出したい。
第6問(10点):<選択>生命現象と物質、生態と環境 [標準]
・選択的プライシングと転写調節
タンパク質の輸送に関する考察の穴埋め問題、選択的スプライシングに関する図選択問題、環境からの刺激とタンパク質の転写調節に関する考察の穴埋め問題である。丁寧な読み取りと、遺伝子の発現に関する正確な知識が問われた。
第7問(10点):<選択>生物の進化と系統 [標準]
・生命の初期進化と分類
生命の初期進化、無脊椎動物の分類に関する知識問題、藻類と植物の光合成色素のクロマトグラフィーに関する考察の穴埋め問題である。問1・2では地質時代と動物分類の細かい知識が問われた。問3の実験考察問題も、陸上植物の分類に関する知識を踏まえて考えるものであった。
2020年度センター試験「生物」の攻略ポイント
・大問7題(第1問~第5問:必答、第6問と第7問:どちらか1題を選択)の出題。
必答の5題が生物の全5分野に対応しており、選択問題の2題は複数分野の融合問題である。必答の5題は2017年度まで、A問題が標準的な知識問題、B問題に発展的な実験考察問題や計算問題が含まれる場合が多かった。しかし、2018年度以降は、大問ごとに知識問題と考察問題の比率が大きく異なる(2019年度の第1~4問、2020年度の第2・3・5問は、A問題・B問題ともに考察問題があった)。
・2020年度の知識問題と考察問題の比率はおよそ4:6。
考察問題の比率は2020年度、2019年度に対して下がったが、知識問題では少し踏み込んだ知識が問われたので、負担感は選択肢が増えたことも相まって重くなったといえる。知識問題に関しては、全範囲について満遍なく問われる。文章の正誤判断での出題が多いため、選択肢内の文全体で誤りがないかどうかを正確に判断する必要がある。選択肢が増えると負担が重くなる所以である。考察問題は、題材は教科書や図説にないものであっても、リード文と実験結果を読み取れば理解できる。ただし、時間に対して設問数・リード文・図表が多いので、普段の演習を通じ、実験の条件や結果のポイントをすばやく抽出できるようにしておきたい。
・解答時間に十分な余裕はない
各大問にそれなりのボリュームがあり、知識問題では細かい正誤判断、考察問題では実験条件や結果の読み取りと整理を行わねばならないため、高得点を狙うには効率的に読解し、解答していく必要がある。そのため、問題演習を通じて、要点を把握・整理しながらリード文を読み取る訓練、各選択肢をすばやく判定する訓練を重ねておきたい。
・共通テストに向けて
試行調査から想定される共通テストは、5題必答で選択問題がなくなる分、苦手分野を残すことはますます許されなくなる。例えば2020年度の第1問問1〜3で発現調節にかかわる分子や領域の名称に迷っているようだと、読解や理解に時間をとられてしまうので、なるべく早く全範囲の学習をひととおり終えておきたい。共通テストは分野融合問題が出題されることが想定されるが、分野融合の実験考察問題も、理解の基になるのは各分野の基礎知識である。また、仮説・実験・結果・考察という流れや、対照実験を設けるなどの、実験考察の考え方自体は各分野でも分野融合でも共通している。考察問題についても、まずは学習を終えた分野内での問題演習を通して、素早く要点をつかみ取る訓練などを進めていきたい。
同じカテゴリの人気記事
センター試験分析
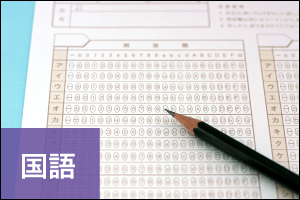
「国語」2018年度センター試験分析
2018年度センター試験分析速報 ■分量と難度の変化(時間/配点:80分/200点) 全体の難度は昨年度よりやや易化したが、センター試験としては標準的な出題である。時間に対しての負担感も標準的なも... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む