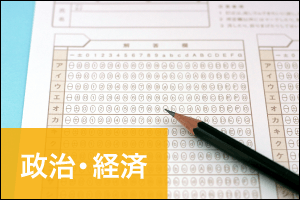「数学I・数学A」2020年度センター試験分析
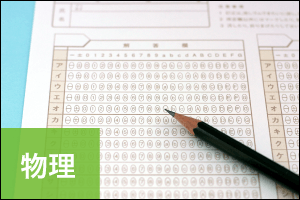
投稿日時:2020年1月23日
Z会の大学受験生向け講座の科目担当者が、2020年度のセンター試験を分析。出題内容・各問の分析、攻略ポイントを詳しく解説します。
2020年度センター試験「数学I・数学A」の出題内容
試験時間と配点
- 時間 / 配点:60分 / 100点
全体の傾向
- 大問形式、選択問題などに大きな変更はなかった。
- 第2問〔2〕、第3問の冒頭で出題された正誤問題は目新しい。
- 多岐選択式問題の選択肢の正誤の検証の仕方次第で、時間不足に陥る懸念がある。誤りの部分を素早く見極め、消去法的な考察の仕方で効率よく解くことも重要。時間節約のため、数学的な直感力も必要であり、数学を苦手とする生徒(とくに文系)の得点は伸びないだろう。
- 昨年に比べ平均点は5点を超えて下がると思われる。
2020年度センター試験「数学I・数学A」の各問の分析
第1問〔1〕(10点):数と式 [標準]
・1次関数の傾き、グラフのX切片に関して2次不等式、式の値を求める問題。
第1問〔2〕(10点):集合と論理 [やや易]
・自然数の倍数に関する条件と、真理集合に関する問題。多岐選択式問題が多く、選択肢の正誤を素早く見極める力が問われる。必要以上に時間を費やすと時間切れになる恐れのある問題。
第1問〔3〕(10点):2次関数 [標準]
・2次関数のグラフの平行移動を題材とした問題で、線分との共有点についてグラフを用いて考察するもの。
第2問〔1〕(15点):図形と計量[標準]
・角の二等分線を絡めた三角形の計量問題。余弦定理・正弦定理を駆使して各辺の長さや外接円の半径を計算する典型的な内容である。
第2問〔2〕(15点):データの分析 [標準]
・(1)の四分位数に関する正誤問題で時間を費やした人が多いだろう。(2)以降も図表の選択問題などが中心で、計算量は少ないため、逆に戸惑ったかもしれない。
第3問(20点): 【選択問題】場合の数と確率[やや難]
・〔1〕の確率に関する正誤問題が目新しい。選択肢0でコインの表裏が出る確率が明記されていないので、深読みしてしまった人もいたようだ。選択肢③の確認に少し手間取るので、この部分で時間のロスが懸念される。
・〔2〕(3)、(4)では、“途中で終了してしまう場合を除くこと”を考慮していないミスも少なくないだろう。
第4問(20点):【選択問題】整数の性質 [標準]
・循環小数の分数表示と、記数法の融合問題。
・(2)(i)、(ii)は最初に表を書いてしまえばまとめて解答できる。時間に追われていると条件「aとbは異なる」を見落とすかもしれない。
第5問(20点):【選択問題】図形の性質 [やや難]
・線分比とメネラウス・チェバの定理や面積比、円に内接する四角形と方べきの定理を絡めた問題。
・前半はメネラウスの定理、チェバの定理などを利用した計算問題で、線分比と面積比の関係も基本レベルだが、「4点B、D、F、Gが同一円周上にある」という条件や一部の線分の長さを与えられての求値問題辺りから難易度が上がる。この10点分で差がつく内容だろう。
同じカテゴリの人気記事
センター試験分析
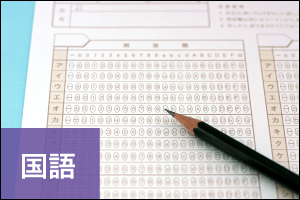
「国語」2018年度センター試験分析
2018年度センター試験分析速報 ■分量と難度の変化(時間/配点:80分/200点) 全体の難度は昨年度よりやや易化したが、センター試験としては標準的な出題である。時間に対しての負担感も標準的なも... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む