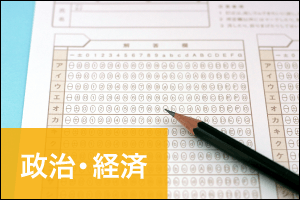「数学II・数学B」2019年度センター試験分析
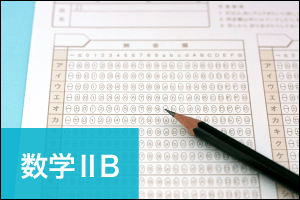
投稿日時:2019年11月5日
■分量と難度の変化(時間/配点: 60分 / 100点 ) 難易度は昨年並みだが、分量は増加した。典型的な問題が多いが計算量が多く、時間の工面に苦労するかもしれない。 ■今年度入試の特記事項 ・2018年度の弧度法の定義のように、見慣れない問題はなかった。 ・第1問は〔1〕、〔2〕ともに典型的な問題で、確実に解いておきたい。 ・2018年度に中問2つに分かれた第2問は、大問1題の構成に戻った。問題自体の難易度は高くないが、計算量が多いと感じた受験生が多いだろう。 ・第3問は(3)の計算が大変。誘導にうまく乗れなかった受験生も多いだろう。 ・第4問は見かけの割に計算量はそれほどでもない。 ・全体的に丁寧な誘導がされているが、問題の分量や計算量は多いといえる。 ■いま解いておきたい問題:第3問 数列 (3)はbnの定め方は問題文で与えられているが、これ以外に誘導はなく、とくにセンター試験特有の途中式の穴埋めの形式での誘導ではなかったため、戸惑った受験生も多いだろう、思考力が必要な問題であったといえる。穴埋め形式だからといって自分で解法を考えなくてよいというわけではないので、記述式の問題と同様しっかり考察するようにしたい。 ■大問別ポイント 第1問〔1〕 2倍角の公式や合成を用いて三角関数を含む方程式を解く典型問題。確実に解いておきたいところ。 第1問〔2〕 対数関数、指数関数を含む連立方程式を解く問題。典型的な内容で誘導が丁寧なので方針は迷わないだろう。 第2問 3次関数の極値や、放物線の接線と囲む図形の面積計算、共通接線など、微積分の基本知識を幅広く問う問題。方針はわかりやすいが、計算が多いと感じた受験生もいるだろう。 第3問 等比数列、階差数列の一般項と、漸化式の解法を問われる問題。センター試験特有の誘導が少なく、また計算量も多いため、苦戦した受験生が多いだろう。 第4問 空間ベクトルを利用して四角錐の辺の長さや角度といった条件を定めたり、体積を求めたりする問題。典型的な内容で計算量もそれほど多くないので、得点はしやすいだろう。
攻略へのアドバイス
Z会の通信教育の本科などで個別試験対策を進めつつ、並行してセンター試験対策にも早い時期から取り組んでおきたい。 本科では「必修テーマ」を通じて数学II・Bの入試頻出事項を体系的に押さえられるため、センター試験・個別試験の両方に有効である。 また、Z会の通信教育の専科「センター攻略演習セット」を用いるなどして、さまざまなジャンルの問題演習を重ね、本番でどのような文章が出題されても対応できるようにしておくことも大切。さらに、直前に本番形式でまとまった数の問題をこなしたい人は、『センター試験実戦模試 数学II・B』(Z会)を使うとよいだろう。
2021年度からは大学入学共通テスト! 共通テスト対策もZ会なら安心!
「共通テスト専用の対策教材が見つからない…」とお悩みのあなたにおすすめなのが、Z会の『共通テスト攻略演習』です。Z会の独自分析により、思考力や判断力が求められる「新傾向」の問題にもしっかり対応。センター試験から共通テストへの変更点をふまえて、万全の対策を進められます。
同じカテゴリの人気記事
センター試験分析
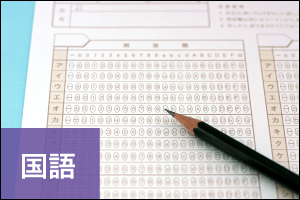
「国語」2018年度センター試験分析
2018年度センター試験分析速報 ■分量と難度の変化(時間/配点:80分/200点) 全体の難度は昨年度よりやや易化したが、センター試験としては標準的な出題である。時間に対しての負担感も標準的なも... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む