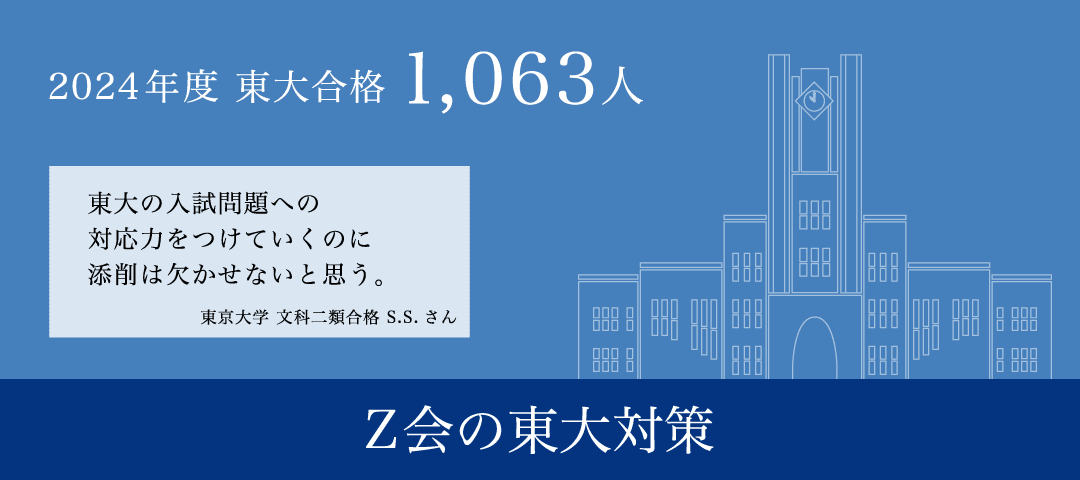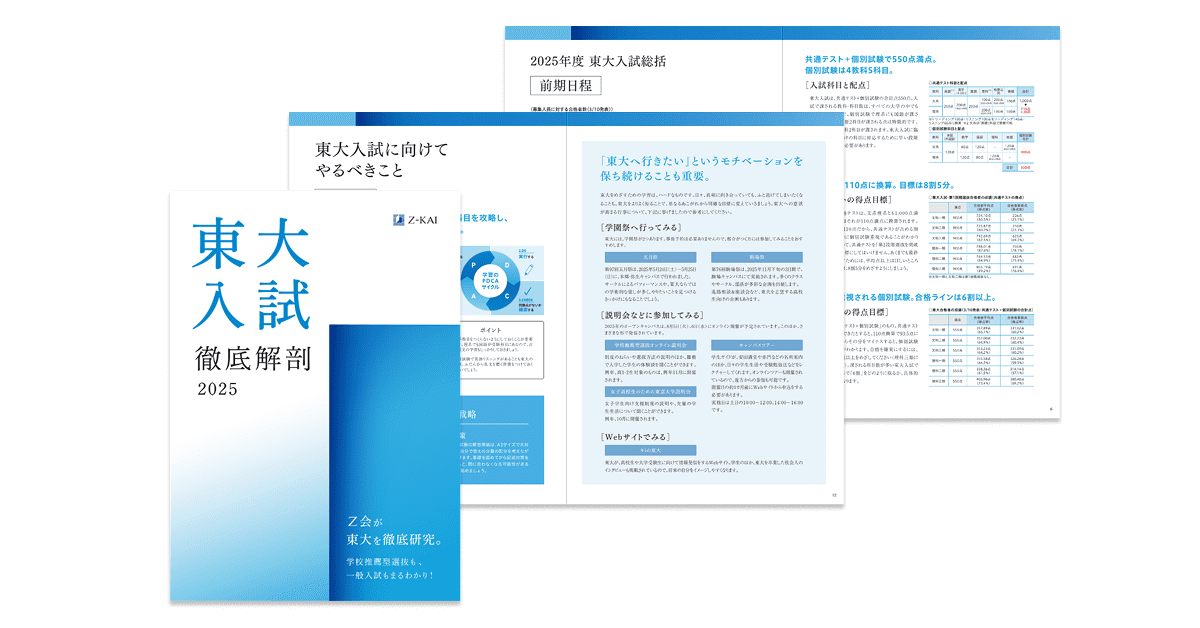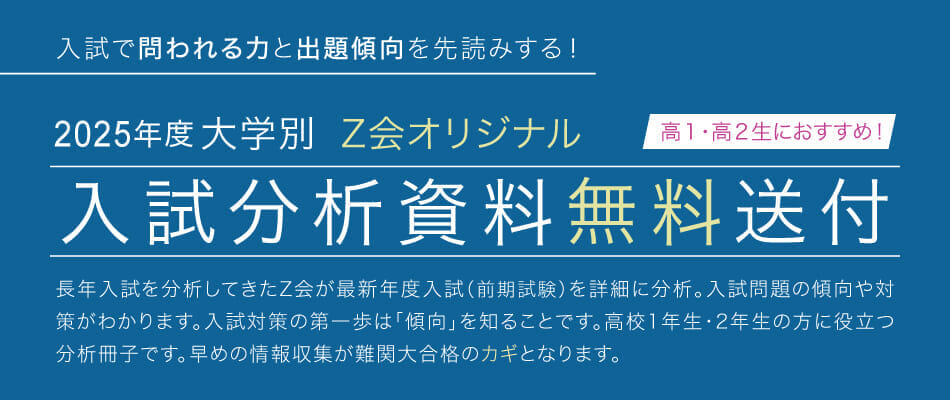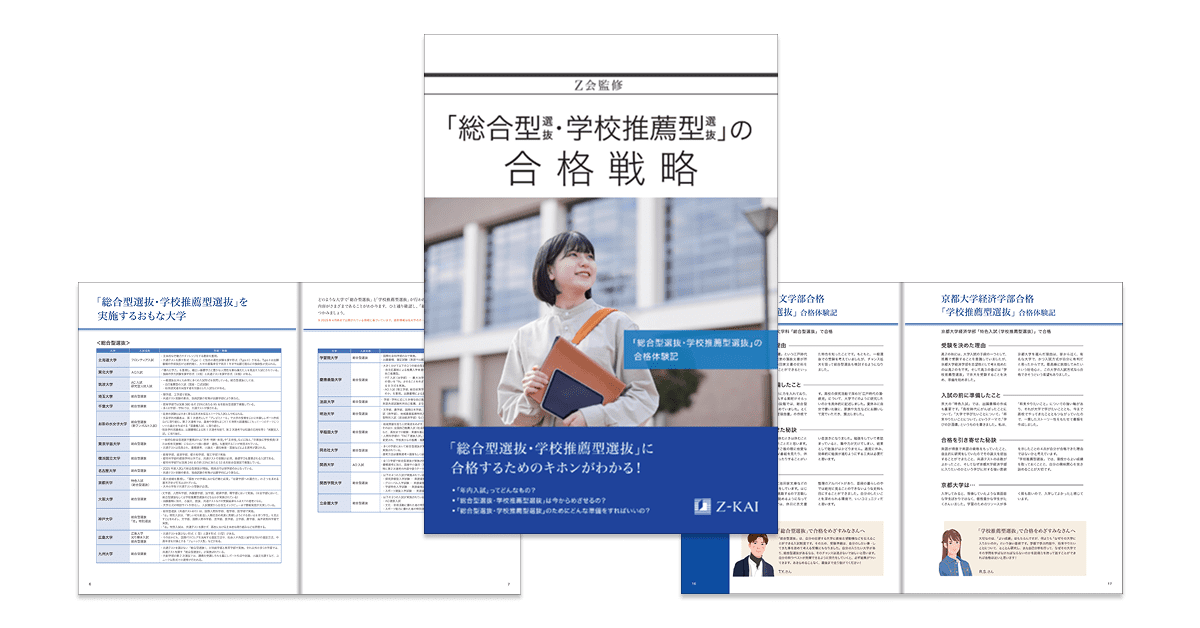Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会日本史担当者からのメッセージ
2025年度の出題は、設問数が6問、総字数が600字と、例年より分量はやや少なくなりました。しかし、教科書的ではない視点からの問いに、限られた字数で端的に答える必要があり、難易度は例年と大きく変わりません。例年、知識の比重が高い第4問を含めて、すべての設問が提示文型であり、東大日本史対策をきちんと積んできたかどうかが大きく影響する試験でした。
東大日本史は特徴的な出題形式であり、一般的な論述問題の演習を積むだけでは対応しきれません。提示文型の東大日本史特有の出題に慣れること、さらに頻出テーマについて理解を深めておくことが、合格への近道です。また、各設問での少しずつの失点を防ぐことが、高得点を取るためのカギになります。教科書を精読するなどして、基本的な知識・理解の習得を怠らないことも重要です。
Z会の通信教育 本科「東大講座」では、東大日本史を解けるようになるために取り組んでほしい問題や、東大日本史の出題形式や設問の傾向、頻出テーマを踏まえた問題を豊富に出題しています。Z会オリジナルの、東大日本史に即した問題演習を積み、個々の解答に応じた添削指導を受けることで、東大日本史への対応力を着実に養っていきましょう!
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化 (時間:2科目150分)
- 分量は2024年度からやや減少
- 難易度は2024年度から変化なし
2025年度入試の特記事項
- 2025年度の論述総字数は600字で例年よりやや少なく、2024年度からは60字減少。小問の最小字数は60字、最大字数は150字であった。
- 第1問・第2問は小問にわかれておらず、全大問の設問数合計は6問。2024年度より2問減少した。
- 第1問〜第3問は従来通りの提示文型。第4問は、2022年度以来出題が続いていたグラフは示されず、史料と4つの提示文が出題された。
- 提示文の読み取りと基本的な知識で対応できる問題が多く、全体として標準的な難易度の試験であった。
合否の分かれ目はここだ!
東大日本史では、各設問での少しずつの失点を防ぐことが合格へのカギになる。いずれの大問も最低限の基本的な知識・理解を前提とした出題ではあるが、とくに第4問は例年、知識の比重が高く、近・現代史の学習状況によって差がつきやすい。さらに、東大頻出テーマへの理解を深められているかどうかが、問題への取り組みやすさや解答の完成度に影響する傾向にある。
2025年度は、教科書では見慣れない切り口から問うた問題が多く、解答の方針を立てた後もどのような言葉を用いて解答をまとめるか、苦戦した受験生も多かっただろう。東大日本史特有である、提示文から情報を読み取り設問要求に沿って考察し、的確に表現できたかどうかがポイントになった。
また、第4問を含め、全体として知識量や東大頻出テーマへの理解の度合いでは差がつきにくい出題であった。初めて触れる視点であっても、提示された情報を活用して考え、解答をまとめるという、東大日本史特有の提示文型の問題への慣れ、すなわち過去問演習、東大日本史対策をきちんと積んできたかどうかが、そのまま得点の差として現れる試験であったといえるだろう。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
第1問
7世紀から8世紀における中国文化の受容 [標準]
150字。7世紀から8世紀における、中国文化の受容のあり方や担い手について、変化とその背景が問われた。7世紀については提示文⑴⑵から朝鮮半島の国々を経て中国文化を受容していたこと、8世紀については⑶⑷から中国文化を中国から直接取り入れるようになったことを読み取り、「受容のあり方」の変化として述べていきたい。「背景」としては⑶の記述がポイントになる。提示文から読み取れる情報を羅列するのではなく端的な表現に置き換えることで、「変化」とその「背景」が明確に伝わる解答にまとめよう。
第2問
土一揆の蜂起に対する室町幕府の対応 [標準]
150字。土一揆の蜂起に対して室町幕府がどのように対応したかが問われた。留意点を踏まえて、まずは提示文⑴⑵と⑶⑷それぞれについて、土一揆の構成や基盤の違いを考えていく。その上で、⑴⑵、⑶⑷それぞれの土一揆の蜂起に対して幕府がとった対応を提示文から読み取り、両者の違いや共通点を意識しつつ述べていけばよい。⑴⑵については「沙汰人」から惣村を想起し、⑶⑷は「地侍」と守護の関係に注目しよう。
第3問
江戸時代初期の東海道整備と参勤の変化 [標準]
A
90字。関ヶ原の戦い後の東海道整備の特徴を、徳川家康の意図に留意して述べることが求められた。提示文⑴⑶から当時の家康の政治状況を推測し、東海道整備の「意図」を考えていく。⑵で述べられている「伝馬の制度」や「譜代大名」の配置については、そのねらいを解答に盛り込みたい。
B
60字。提示文⑶⑷から大名の参勤に対する意識の変化を読み取り、その背景を含めて論じることが求められた。設問Aでは豊臣家が存続している時期、設問Bでは大坂夏の陣後、つまり豊臣家滅亡後について問われていることから、「背景」として、豊臣家が滅亡して江戸幕府の支配が確実なものになったことを明らかにしたい。大名の意識については、「変化」を明確にするために、変化の前・後それぞれを説明しよう。
第4問
唱歌教育の歴史 [標準]
A
60字。学制公布当初に「唱歌」教育の実施が見送られた理由が問われた。史料として示されたお雇い外国人の著書『日本事物誌』から、西洋の音楽と比較した日本の音楽への評価を読み取ることは難しくない。提示文⑵でその後に唱歌教育の整備が進められたことにも注目しよう。
B
90字。提示文⑵の『小学唱歌集』から⑷の『尋常小学唱歌』へ内容の変化が見られた事情が問われた。「内容の変化」ではなく、それが生じた「事情」が問われていることに注意しよう。⑶の東京音楽学校の設立に加えて、『尋常小学唱歌』が発行された時期が「1911年から1914年にかけて」である点に注目しよう。
攻略のためのアドバイス
東大日本史を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 全時代・全分野についての正確な知識・理解
当然だが、日本史についての知識・理解があることが問題を解く上での前提となる。学習の際には、歴史事項の正確な意味内容や事項の流れに加えて、律令制や幕藩体制といった、各時代を考える際の本質的な事項の理解も身につけることを心掛けよう。
●要求2●提示文・設問文の把握
東大日本史では、与えられた提示文や史・資料すべてをうまく活用すること、設問文の要求や意図を読み取ることが重要になる。東大型の問題演習を通じて、提示文を利用し、設問の趣旨にあった解答を作成する力をつけていこう。
●要求3● 要求された字数に応じて論をまとめる記述力
東大日本史で出題される字数は30字~180字と幅広い。そのため、設問の要求だけでなく、各設問で指定された字数に合わせて、情報を取捨選択し、論旨をまとめる高度な記述力が必要である。定期的な論述演習で、設問の要求を満たした解答を作成する力を養っていこう。
対策アドバイス
基礎力の完成
高3の夏休み終了までに一通りの通史学習を終わらせることを目標に、要求①を満たしていこう。また、東大で要求される高度な記述力を身につけるためには、早期から定期的に論述演習を行うことも重要である。Z会の通信教育の本科「東大講座 日本史」で、東大入試で必須となる基本的な知識の定着をはかりながら、論述の書き方もマスターしてほしい。
東大型の問題への取り組み
東大日本史攻略のためには、定期的に東大型の問題演習を行い、その形式に慣れることが必須である。Z会の通信教育で、東大日本史で問われる知識の確認をしながら、要求②・③を身につけていこう。
また、過去問演習を積んで、東大型の問題に慣れるとともに、律令体制や幕藩体制など東大頻出テーマを把握し、それぞれのテーマに対する理解を深めていきたい。
実戦演習
冬休み以降は、時間を意識した演習も行おう。東大の地歴は2科目で150分という試験時間のため、時間配分がカギになる。本番同様の4題セットの問題を活用しながら、答案作成にかかる時間や論述にかかる時間、問題に取り組む順番などを考えておこう。
Z会でできる東大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!