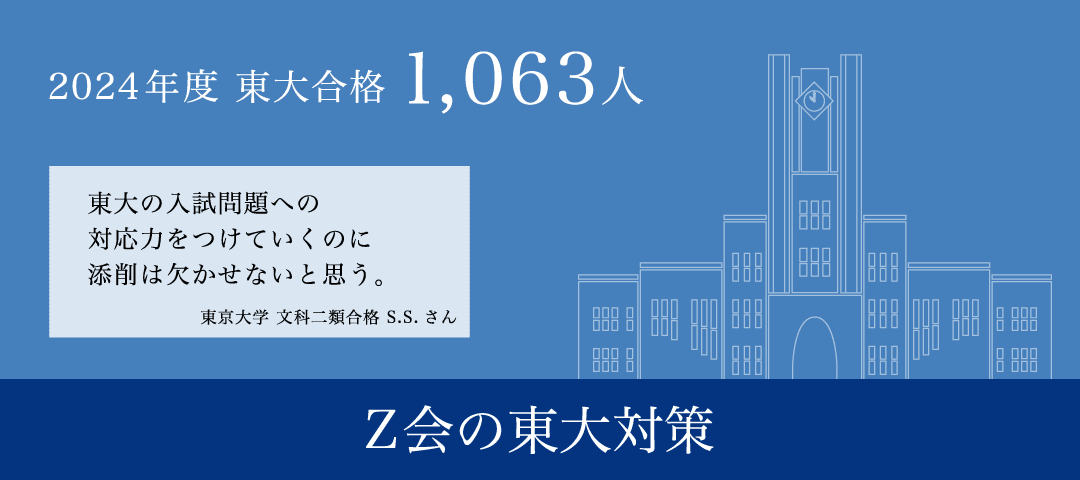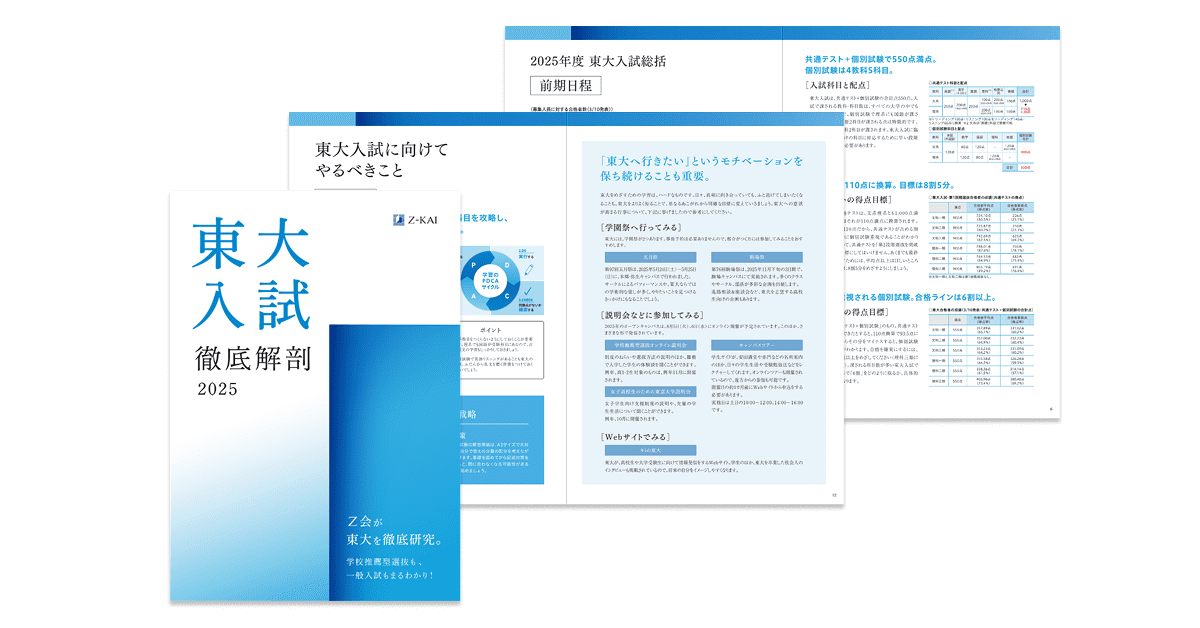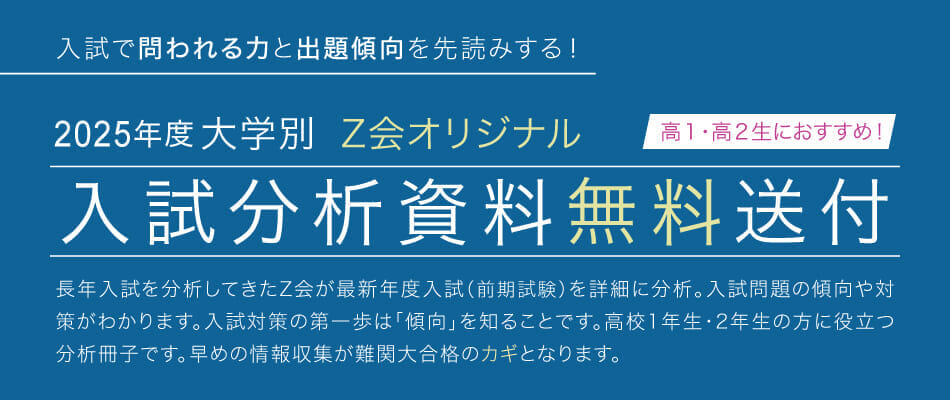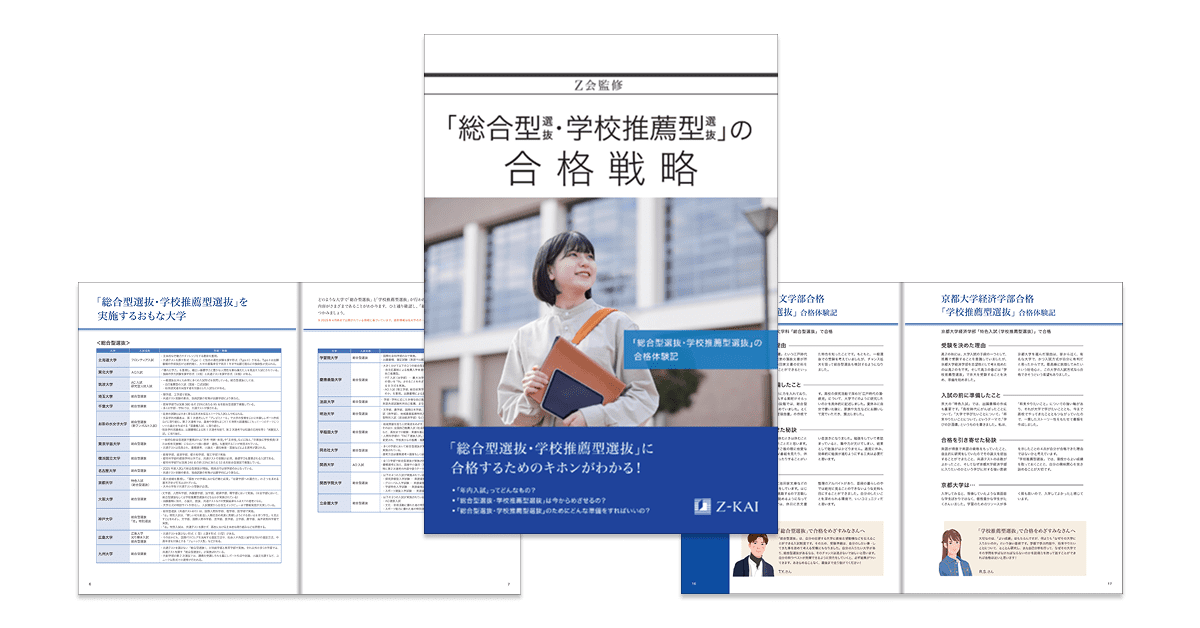Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会化学担当者からのメッセージ
今年の東大化学でも、近年と変わらず見慣れない題材に関する出題がみられ、問題文中で与えられた情報を読み取って適用する対応力が必要となりました。2024年と比較すると、実験操作の目的や課題解決に関する論述問題がいくつか出題されたこともあり、全体として難化しました。また、問題の分量は2016年度以前の水準が続いており、ところどころに高度な思考力や計算力を要する問題も含まれていたため、かつてのように「解かない問題を見抜く力」も必要なセットだったといえると思います。
したがって、まずは標準的な問題を確実に正解したうえで、差がつく問題をできるだけ多く正解して、高得点をめざしたいところです。分量が多いので、解く問題に優先順位をつけ、試験時間内にすばやく処理する力が求められるでしょう。
また、日頃の演習や過去問演習をとおして、通り一遍の学習をするのではなく、「この現象はなぜ?」「この操作は何のために行っている?」ということを常に考えながら、それらを自分の言葉で説明できるか、という点に意識を向けて学習を進めていくとよいと思います。Z会の通信教育講座では、このような盲点になりがちな箇所を突く出題をしていきます。東大受験を目指す方には、表面的な理解にとどまらない、本当の学力を身につけていただきたいと思います。
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化 (理科…時間:2科目150分)
- 難易度は2024年度から難化
- 分量は2024年度から増加
2025年度入試の特記事項
- 形式は例年どおりすべて記述形式で、大問として理論1題、理論(無機)1題、有機1題の順で出題された。ここ数年は第1問が有機であったが、かつてと同じ第3問での出題となった。
- 計算問題では、答に至る過程を書くように要求されることがある。
- 2020〜2024年度はすべての大問が中問に分かれていたが、2025年度はいずれの大問も中問にわかれていなかった。
- 小問数は30問で、2022年度31問 → 2023年度32問 → 2024年度31問と、31問前後の出題が続いている。ただし、1問あたりの負担感は大きくなったといえる。
- 増加傾向にあった論述問題の数がさらに増え(2023年度 6問 → 2024年度 9問 → 2025年度 13問)、かつ高度な思考力を要するものが多く出題された。2024年度にみられた文字数・行数を指定した出題はなかった。
合否の分かれ目はここだ!
- 全体の難度があがっているため、いかに標準的な問題を取りこぼさずに正解できるか、目新しい論述でも諦めずにポイントを押さえて書き上げることができるかで差がつくだろう。試験時間に対して分量が多いため、解ける問題を優先して解き、得点をしっかりと確保することが重要となる。計算問題についても、手際よく、ミスなく解き進められるようにしたい。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
第1問:理論 状態図、結晶構造、蒸気圧、物質の分離 記述形式(論述問題あり) [やや難]
物質の状態変化をテーマに、状態図、結晶構造、蒸気圧、物質の分離などに関する問題が出題された。
- アとイは標準的な問題であるため得点したい。
- ウでは金属の融点を覚えている受験生はあまり多くないと思われる。そのため、知らなくても推測できたかで差がつくだろう。
- エは方針自体は立てやすいが、計算がやや煩雑になるためミスなく計算する必要がある。
- カは求めたい値を明確にしたうえで、与えられた条件をうまく組み合わせる必要がある。また、希薄溶液中のモル分率を溶質/溶媒で表せることに気づくことができるかがポイントである。これは、ラウールの法則に関する問題を解いたことがあるかで差がつきやすい。
- キは目新しい実験であるが、図が非常にわかりやすいために比較的考えやすい。ただし、ポイントを押さえて説明するためには実験の意図を正しく理解しなければならず、決して簡単ではない。
第2問:理論・無機 気体の性質、化学平衡、ヨウ素の反応 記述形式(論述問題あり) [やや難]
火山ガスに含まれる気体の反応や、化学平衡、ヨウ素の反応などに関する問題が出題された。
- アは溶解度が影響するということは想像できるが、硫化水素の溶解度をどのように考えるかが悩ましい。
- イは反応としては定番であるものの、求めるべきものを明確にしたうえで必要な式を選択して変形していく必要がある。
- エ〜カの反応式は、覚えていなくてもその場で作れるようにしてほしい。
- ク〜サは目新しいテーマであり、問題文の内容を正しく理解しながら解き進める必要があった。その中でもクは式変形のみなので得点したい。ケはやや数学的な要素も含まれており、条件にあわせてうまく式変形できるかがポイントとなる。コとサは、問題文の内容を理解したうえで高度な思考力を要するため難度が高い。いずれの論述問題も問題集などでは見かけることがない内容であるため、その場でいかに考察できたかで差がつく。
第3問:有機 ペプチド 記述形式(論述問題あり) [難]
中問に分かれていなかったということもあり、終始ペプチドに関する問題が出題された。脂肪族や芳香族化合物の構造決定はなく、いままでの東大化学ではあまり見られない出題であった。
- イはペプチドを構成するアミノ酸を決定する問題。目新しい条件はないものの、限られた条件から正しくアミノ酸を決定するためには思考力を要する。
- ウの空欄あは用語として知っていないと答えられない。
- エとオは標準的な問題であるため取りこぼさずに得点したい。
- カはアセチル基で保護することでどのような構造をもつかをまず考える必要がある。そのうえで、加水分解により起こる反応の影響を考えることになる。
- キは問題文から固相合成法の仕組みを理解したうえで考察する必要がある。答えは単純でありある程度推測もできるが、見慣れない題材ということもあり自信をもって解答することは容易ではないだろう。
- クは図3−4から結合のしかたは比較的わかりやすいが、水酸化ナトリウムによりチロシンやアスパラギン酸の水素が電離していることに注意。また、くさび型表記を用いる必要があるため、D型とL型を間違えないようにしなければならない。
- ケはなぜニンヒドリン反応を示すかを、まずは考える必要がある。そのうえで、どの工程でどのような操作をするかを検討する必要があるため、考察が多岐にわたり正解することは容易ではない。
攻略のためのアドバイス
ここ数年論述問題が増加傾向にあり、かつ実験操作の目的や課題解決を問うような問題が多く出題されていることから、高度な化学的思考力が求められている。基本的な事項を暗記するだけではなく、深く理解しておくことはもちろん、例年どおりの難度の高い応用問題が出題されても対応できるだけの十分な力をつけておくべきである。
東大化学を攻略するには、次の3つの要求を満たすことをめざそう。
●要求1●難問に対応する思考力と応用力
東大化学では、高校で学習する内容をそのまま答えるだけの問題もあるが、合否の決め手となるのは、高校範囲の知識を応用させて考える問題である。よって、基礎力の確立と、それを柔軟に使いこなせる思考力、応用力の養成が求められる。全分野において法則を正しく使いこなせるようになるのが第一である。
●要求2● 長い問題文を短時間で読み解く読解力
東大化学では、実験操作や高校化学の範囲外の内容などに関する長い問題文を読み、題意を読み取り解答する問題が出題されることがある。限られた時間の中で問題文を読みこなし、正確に理解する力が要求される。見慣れない題材にも臆さないよう、他大学の過去問(京大・阪大といった難関大)にも目を向けて演習しておくとよい。
●要求3●計算問題の解答時間を短縮する計算力
煩雑な計算問題がよく出題される東大化学では、計算力を身につけることが必須である。ふだんの問題演習では、電卓を使用したり、頭の中だけで考えたりするのではなく、実際に手を動かして計算し、計算自体に早いうちからしっかり慣れておこう。
対策の進め方
高校化学の完成
まずは、高校化学の内容を完全に理解することから始めよう。高校化学の内容で曖昧な部分があると、要求①を満たすことはできない。近年の東大化学では、応用問題を解くうえで前提となる標準的な内容を確実に押さえることが、よりいっそう求められている。また、有機の「高分子化合物」の単元は対策が遅れがちなので、とくに意識して取り組んでおきたい。Z会の通信教育などを利用して、基本的な各単元の理解を確認しながら学習を進めよう。
本番形式での演習
高校化学全般の内容を理解したら、次に要求①を満たすために、高校範囲の内容を応用させて考える問題に取り組んでみよう。このタイプの問題は、問題文が長いことが多いため、並行して要求②を満たしていくこともできる。Z会の通信教育でも、さまざまなタイプの添削問題をとりあげていく。
予想問題で総仕上げ
演習を順調にこなしていければ、要求③もある程度は満たされていくであろう。自分の得意不得意、問題の難易度などを意識し、解答時間内で得点を最大化できるような自分の解き方を身につけてほしい。
Z会でできる東大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!