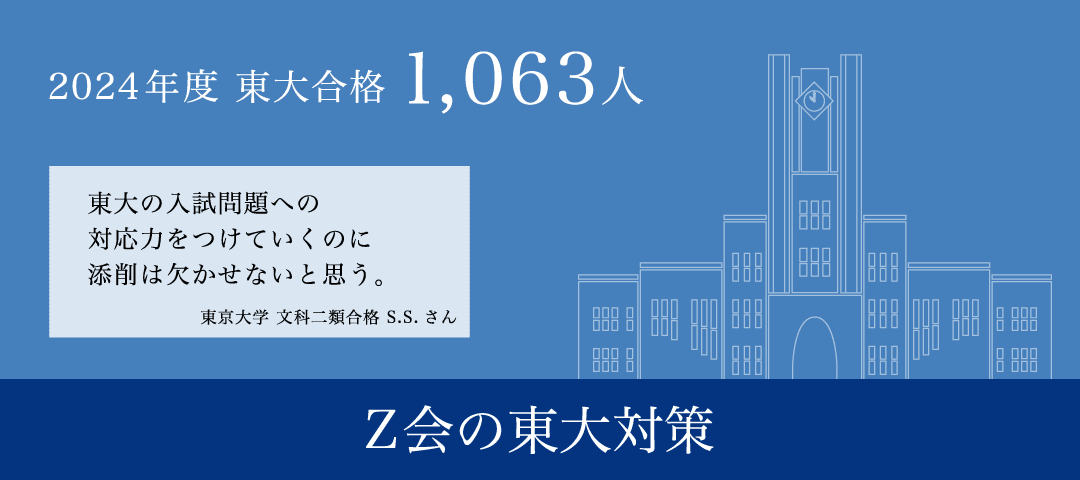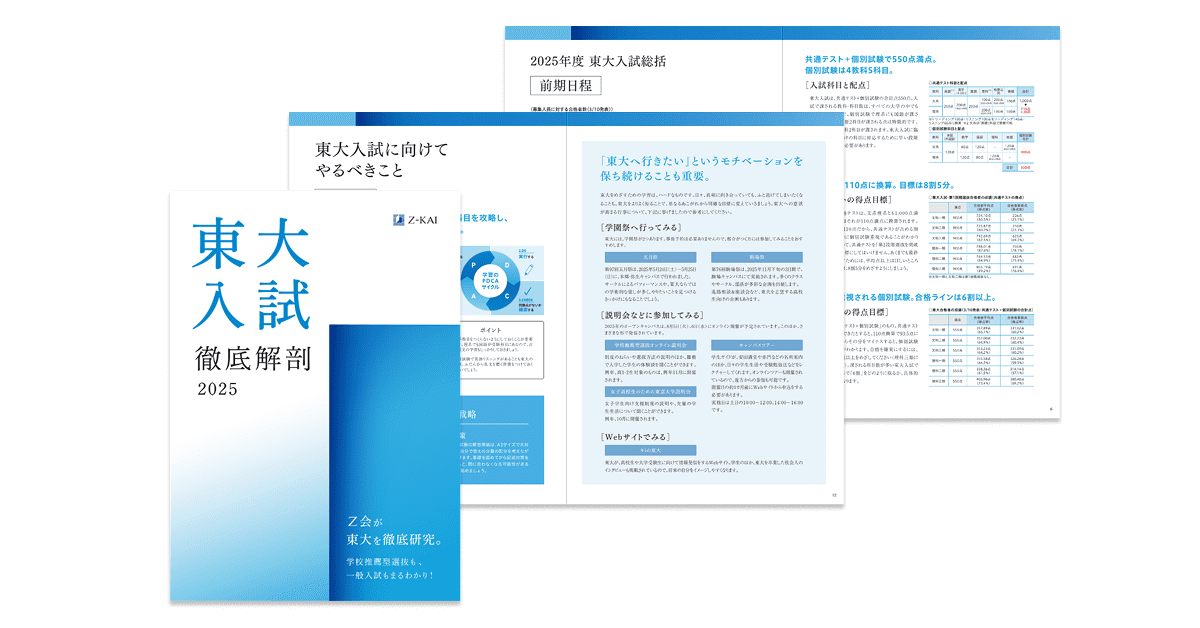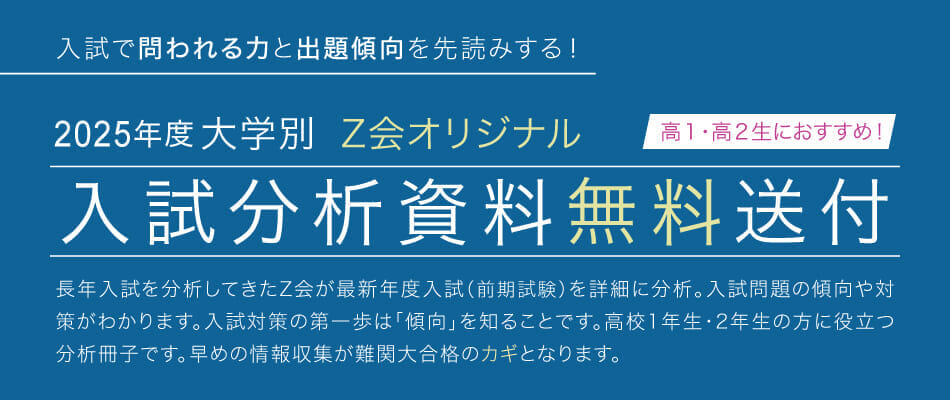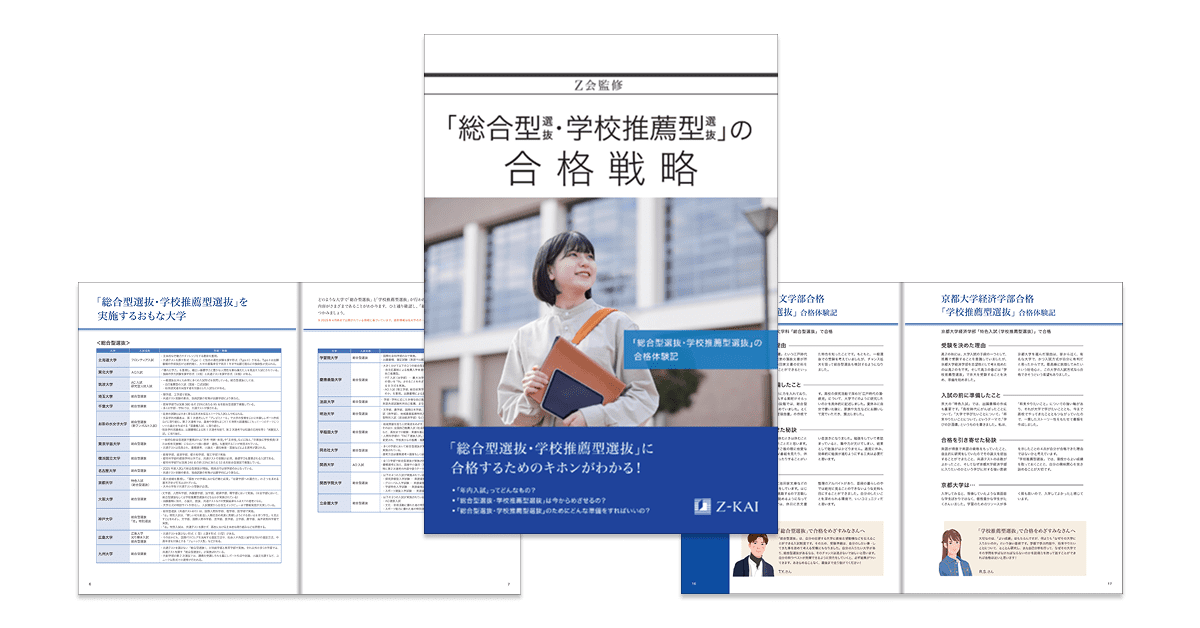Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会世界史担当者からのメッセージ
2025年度の出題では、第1問が2024年度に続き論述2問構成であったり、第2問・第3問で資料が多用されたりと、戸惑いがあったかもしれません。しかし、必要とされる能力はこれまでと変わりません。日常の問題演習から、問題の要求を正確に読み取る「読解力」、広い視点で歴史を捉える「歴史的考察力」、問題の要求に沿った解答を仕上げる「文章表現力」を意識して鍛えておきましょう。
Z会の通信教育 本科「東大講座 世界史」では、東大世界史の出題に倣った構成・視点で作問された演習問題を豊富に出題しています。さらに、一人一人の解答に応じたきめ細やかな添削指導で、字数の多い論述問題にも対応できる実力を着実に身につけることができます。東大に即応した問題演習と、添削指導によるブラッシュアップで、東大世界史に対応する確かな力を養いましょう!
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化 (地歴…時間:2科目150分)
- 難易度は2024年度からやや難化
- 分量は2024年度から増加
2025年度入試の特記事項
- 全体の総論述字数は1020字であり、2024年度よりも増加した。
- 第1問は、2024年度に引き続き、600字の大論述1問ではなく小問2問構成であった。第2問・第3問は例年通りであり、第2問では小論述集合、第3問では単答集合が出題された。
- 第1問では、小問が2問で構成され、論述字数はそれぞれ360字(12行)と240字(8行)で、合計字数は600字となった。第1問が小問に分かれていたのは、2024年度に続いて2度目である。
- 第2問は小論述と単答問題で構成され、総論述字数は420字であった。また、史料・図版が提示された。
- 第3問は例年通り単答問題10問で構成されたが、史料・図版・グラフといった資料が提示され、その読み取りが必要とされた。
- 地域としては、大きな偏りなく出題された。
- 時代としては、古代から戦後史まで万遍なく出題された。
合否の分かれ目はここだ!
2024年度から第1問が600字論述ではなくなったとはいえ、広い視野で世界史を捉えて歴史事項を考察する力が求められていることは変わらない。過去問や即応問題に多く取り組み、東大世界史が求める歴史的考察力を十分に養っていたかで、解答の出来に大きな差がついただろう。また、その歴史的考察力のベースとなるのは盤石な知識である。教科書レベルの知識を抜け漏れなく確実に身につけていなければならない。
第2問・第3問で確実に高得点を獲得した上で、第1問で可能な限り得点を上積みするという戦術が有効であることは例年と変わりない。第2問・第3問を手早く正確に解ききる処理力も重要であった。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
第1問
4つの大陸国家の20世紀前半における変容(論述360字、240字) [やや難]
オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国、ロシア帝国、清という4つの大陸国家の20世紀前半における変容をテーマに、論述問題が2問課された。2024年度と異なり、資料文の提示はなかった。
問(1)
4つの大陸国家の変容について、2つの類型に分けて360字で論じる問題であった。まずは、設問文の「支配領域や民族別人口構成の面で」という文言を手掛かりに、4つの国家をどう分類すればよいかを判断しよう。さらに、2つの類型が、どのような分け方であるのかを解答に明記しなければならない。それぞれの国家の変容の具体については、指定語句をヒントにしつつ、各類型に沿った視点からまとめたい。解答に盛り込むべき内容は難しくないが、問題の要求に沿って2つの類型に的確に分けるためには、正確な知識と歴史的な考察力が求められた。
問(2)
問(1)の内容を踏まえて、国際社会における「新たな原則」と、オーストリア=ハンガリー帝国およびオスマン帝国におけるその事例について240字で論じる問題であった。「新たな原則」が何であるかは指定語句を手掛かりに特定できる。必要な知識は基本的であるが、設問の要求に沿った解答にまとめ上げるには、事項の的確な取捨選択と文章構成力が必要であった。
第2問
各時代・地域の外交(論述120字×1、90字×2、60字×2、単答) [標準]
各時代・地域の外交をテーマに出題された。2021年度以降、小論述問題のほかに単答問題も出題される形式が続いている。
- 問(1)-(a)は仏教に関する論述問題であった。「仏教の名称と特徴」については、資料1中の語句がヒントとなる。
- 問(1)-(b)の単答問題は基本的なので確実に得点したい。
- 問(1)-(c)は取り上げるべき事項の見落としに注意したい。
- 問(2)-(a)は、時期の指定に注意して取り上げるべき事項を取捨選択したい。
- 問(2)-(b)は、提示された図版の読み取りと知識から、「この現代国家」の意図を考察する必要がある、「世界史探究」を意識した出題だった。
- 問(3)-(a)は、資料2中の語句から「ある危機」とその発端となった「ある出来事」の特定は簡単だろう。基本的な経緯説明の論述であるが、取り上げるべき事項が多いので、120字に収まるよう、それぞれの事項について簡潔にまとめたい。
- 問(3)-(b)のアンゴラの旧宗主国は盲点だったかもしれない。
第3問
歴史のなかの都市(単答) [標準]
政治・経済・軍事の中心地や文化の融合・発信の基地として機能した歴史のなかの都市をテーマに単答問題が10問出題された。史料・図版・グラフなどの資料が提示され、例年よりも多少時間がかかったかもしれないが、資料の読み取り・知識ともに難しくない。
- 問(1)は、東大第3問では珍しく、記号選択問題であった。中国の主要な都市や河川について、地図上での位置を理解できているかが問われた。
- 問(3)は文化史からの出題であり、盲点であった受験生もいたかもしれない。
攻略のためのアドバイス
東大世界史を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 第3問は磐石な知識力が必須!9割以上をめざせ!
ほとんどが基本的な知識に関する出題であるため、合格のためには9割以上の得点をめざしたい。但し、文化史や現代史・戦後史など学習が手薄になりやすい範囲の事項も頻出なので、注意が必要である。
●要求2● 第2問は「知識の正確さ」「設問の要求に応じた記述ができているか」に注意!
概ね基本的な内容から問われるが、その分知識が不正確であったり設問の要求を意識できていない解答を書いたりすると、大きく減点されてしまう。日頃から、知識が正確に定着しているか、年代や、“意義”・“影響”といった設問の要求に正しく応えているかを意識して、解答を作成する練習を積みたい。
●要求3● 第1問は「読解力」「論理的思考力」「文章表現力」を鍛えよ!
東大世界史の第1問は、時代・地域を越えた広い視野で世界史を捉え、考察・論述することが求められるので、難度は高い。知識に不足がないことはもちろんだが、問題文から要求を読み取る「読解力」、解答を組み立てるための「論理的思考力」、要求に応じた解答を作成する「文章表現力」が必要となる。こうした力は一朝一夕で身につくものではないので、ほかの受験生に差をつける完成度の高い答案を書くためにも、早いうちから論述対策を始めよう。第三者に添削してもらうことにより、表現力を磨き、文法的にも正しい文章を書けるようにしておきたい。また、近年は資料を用いた出題も散見される。日々の学習から資料読解の練習を積み重ねておこう。
対策の進め方
基礎力の完成
まずは、要求①を満たすために、通史の完成を急ごう。受験生の夏までには、通史を一通り学習しておくことが理想である。教科書の全範囲の基礎的な内容を網羅し、問題演習に取り組もう。また、既習範囲は積極的に論述問題にもチャレンジし、知識を文章でまとめることに慣れていこう。
東大型の問題への取り組み
東大世界史攻略のためには、早期から定期的に論述問題の演習を行い、要求2・要求3の力を伸ばしていくことが必須である。まずは、第2問で出題される60~120字程度の短い字数の論述問題に繰り返し取り組んでみよう。その際、要求2にはよく注意を払い、論述問題への対応力を高めていこう。また、慣れてきたら、第1問のような字数の多い論述問題にもどんどんチャレンジし、要求3の力を養ってほしい。既習範囲の論述問題を演習する時は、最初はあえて何も見ないで解いてみよう。覚えていると思っていた知識の抜けが見つかり、通史の復習を効率的に行うことができる。
実戦演習
受験生の冬以降は、時間を意識した演習も行おう。東大の地歴は2科目で150分という試験時間のため、時間配分がカギになる。本番同様の構成の問題を活用しながら、解答作成にかかる時間や問題に取り組む順番などを考えておこう。
Z会でできる東大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!