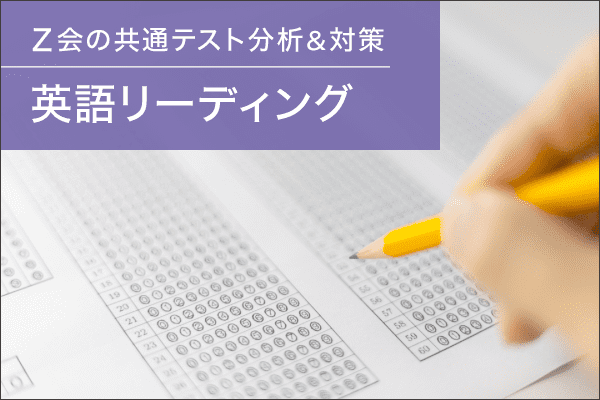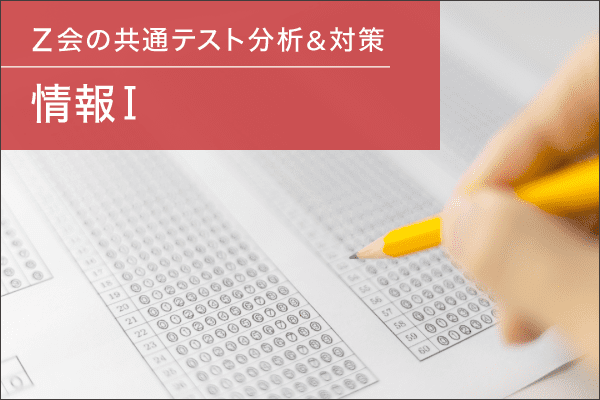物理 – 2026年度共通テストの分析&対策の指針
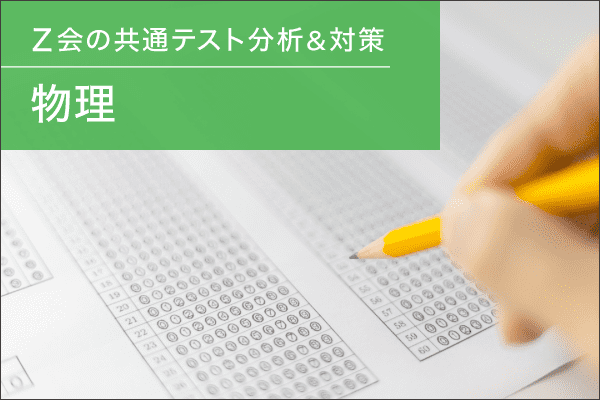
投稿日時:2026年1月19日
Z会の大学受験生向け講座の物理担当者が、2026年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。
共通テスト「物理」の出題内容は?
まずは、科目全体の傾向を把握しましょう。分量、問題構成、難度などを解説します。
試験時間と配点
時間 / 配点:60分 / 100点
全体の傾向
●例年通り、物理の各分野から幅広く出題された。2026年度も原子は第1問の小問集合で扱われた。
●難易度は2025年度と同程度だった。とっつきにくくじっくりと考えさせる設問が多く、受験生の心理的負担感は大きかったと思われる。
●2025年度は例年と比べて、設問数・総ページ数・マーク数ともに多かったが、2026年度は例年並みに戻った。
●2025年度には中問(A・B)に分かれた大問が登場したが、2026年度もこの形式を引き継ぎ、第3問では熱力学(A)と波動(B)という、完全に独立した内容について問われた。
●例年、探究活動や実験に関する設問が多く見られるが、2026年度はあらわに探究活動や実験に言及した設問はなかった。とはいえ、知識や典型問題の定着度ではなく、論理的思考力や情報の運用力を測る共通テストの出題方針に変わりはなかった。
大問別の難易度、配点、テーマ・分野
※難易度は共通テストの受験生を母集団とする基準で判定しています
| 第1問[やや難](配点:25点) | 小問集合 |
|---|---|
| 第2問[標準](配点:25点) | 【力学】2物体の衝突 |
| 第3問[A やや難][B やや難](配点:25点) | A 【熱力学】気体の状態変化 B 【波動】円形波と平面波の重ね合わせ |
| 第4問[標準](配点:25点) | 【電磁気】電場中、磁場中での荷電粒子の運動 |
物理の「カギとなる問題」は?
次に、物理で「カギとなる問題」を見てみましょう。合格点をとるうえで重要な問題を取り上げ、攻略ポイントを解説します。
第1問の問2
回路の中の2つのホルダーに、導線/コンデンサー/コイル/抵抗器のいずれかをはめる設定で、直流電源または交流電源の場合にランプが最も明るくつくケースを考察する。どのように考えるかわからなかった受験生や、つまずいてペースを乱され焦った受験生も少なくないだろう。
第1問の問3
二酸化炭素入りの風船とヘリウム入りの風船を軽い糸で結んで手で持ち、これを加速度運動するバスの中から見た場合について考察する。誘導をもとに、バス内から見た慣性力や遠心力の向きと、空気よりも軽い・重い風船のふるまいを関連づけて考える必要がある。
第3問 A の問2
p–Vグラフの面積から仕事を求めるが、熱サイクルより少し小さい面積と、少し大きい面積の平均値を考えるという、いかにも共通テストらしい設定。設問の意図を素早く読み取りたい。
第3問 B の問5・問6
問5では、x軸上で円形波と平面波が強め合う点の数を数える。前問をもとに数式から考えてもよいが、直線上なので図に経路差0、λ、2λ、…の点を描いてもよい。また、問6は合成波の山がどの方向に進むかを問う、高校物理ではあまり見ない設問だった。1波長後の該当する円形波と平面波の合成を考えてもよいし、2つの波の速度をベクトルとして足し合わせて考えてもよい。
攻略へのアドバイス
最後に、次年度以降の共通テストに向けた攻略ポイントを確認しましょう。物理で求められる力をふまえて、必要となる対策を解説します。
法則や定義の理解の抜け・漏れをなくし、基本問題を確実に解答できる力を身につける
共通テストは思考力が問われる問題が多いが、それ以前に考える武器となる法則や定義、そしてこれらから導かれる公式を正しく身につけていなければ太刀打ちできない。まずは基本問題の演習を通して法則や定義を確実に理解し、公式をすぐに使用できる状態にしておくことが最優先である。
実験を行い、図やグラフを用いて情報を整理したり、議論をしたりする機会を増やす
実験により得られた図やグラフを活用する機会を増やすことが重要である。実験では、教科書の結果と一致することを確かめるだけではなく、誤差が生じた原因はなぜか、予想と反した結果が出たのはなぜか、予想が正しいことを検証するためにはどのような実験を行えばよいか、などの発展的な考察もぜひ行ってほしい。
様々な物理現象を言葉で説明する訓練をする
共通テストでは定性的な理解を問われることが多いため、物理現象を言葉を用いて説明する(書く・話す)訓練が重要である。わからない問題を友達どうしで教え合うなどして、自分の言葉で説明をする機会を増やしてほしい。また、教科書傍用の問題集などに取り組むときも、ただ場当たり的に問題の解き方を身につけるのではなく、「どのような条件のときに運動量保存則が成立するのか」「運動の向きを変化させる原因は何か」など、物理現象の根本的な部分を意識・理解しながら取り組んでほしい。
Z会の講座・お役立ち情報
Z会の資料請求で、
無料プレゼント!
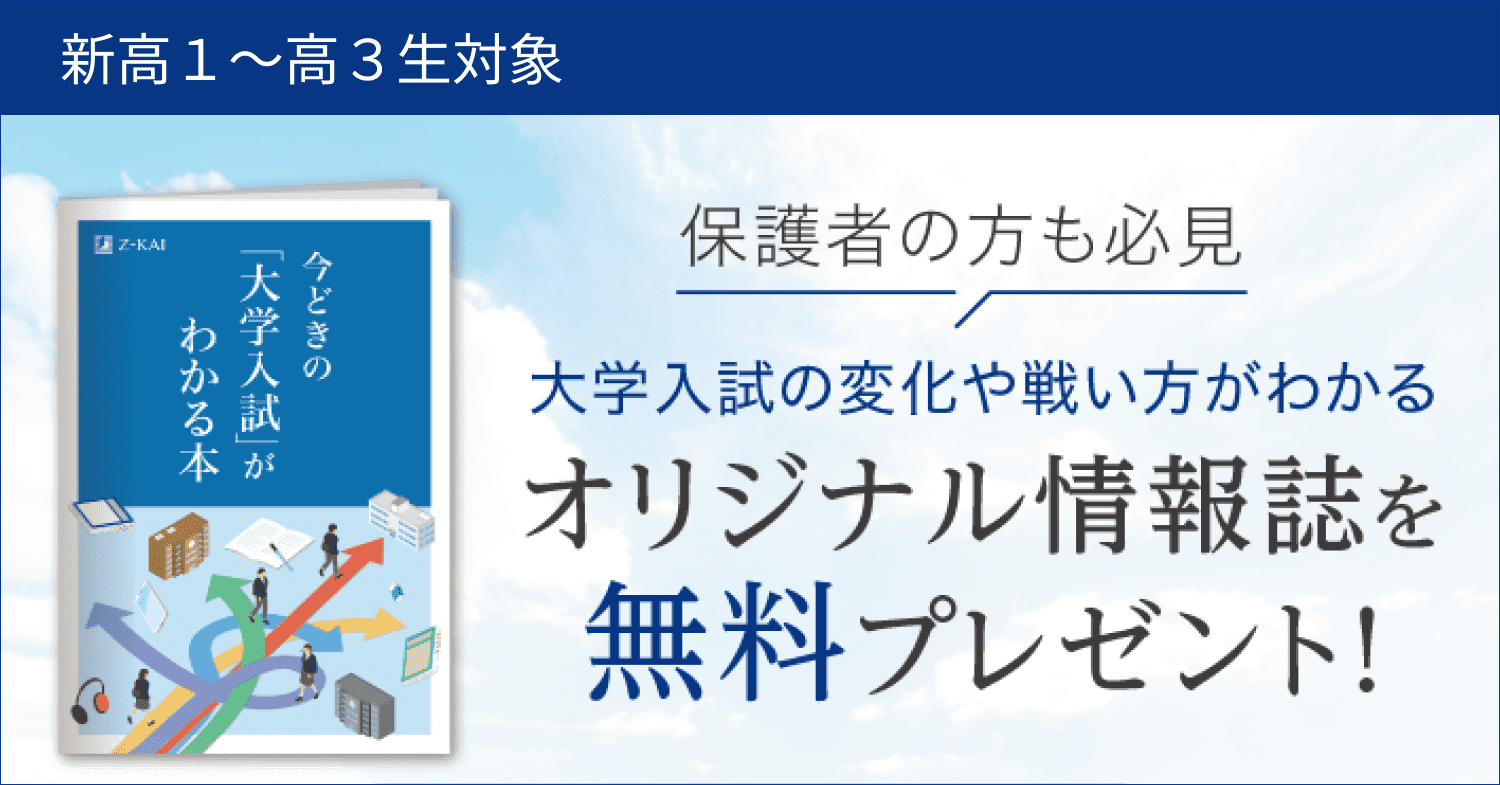
確かな合格実績を誇るZ会が、大学入試の変化と戦い方をまとめました。
志望大合格には、“正しい合格戦略”を練ることが重要です。自信をもって大学受験対策を続けるためにも、「“今どきの大学入試”がわかる」この情報誌をぜひご覧ください。
情報誌と一緒に、Z会の通信教育(高校コース)の資料もお届けいたします。
受験に役立つ情報をLINEで配信中!
Z会では、「Z会の通信教育」LINE公式アカウントで共通テストをはじめとする大学受験に役立つ情報を配信中。学習アドバイス・おすすめ講座情報・お得なキャンペーンなどを随時お届けしています。ぜひご登録ください。
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!
同じカテゴリの人気記事
共通テスト分析「傾向」と「対策」

数学Ⅰ,数学A – 2026年度共通テストの分析&対策の指針
Z会の大学受験生向け講座の数学担当者が、2026年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。 出題内容 カギとなる問題 攻略アド... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む