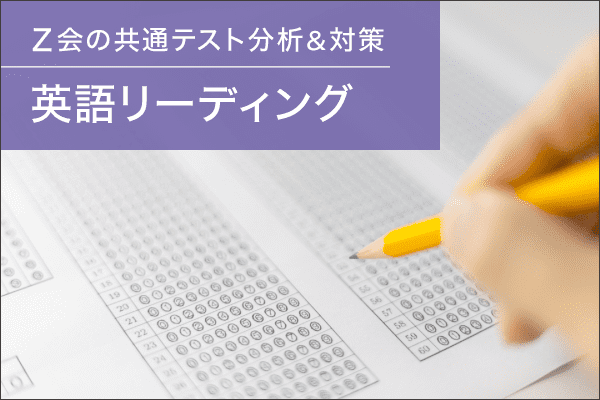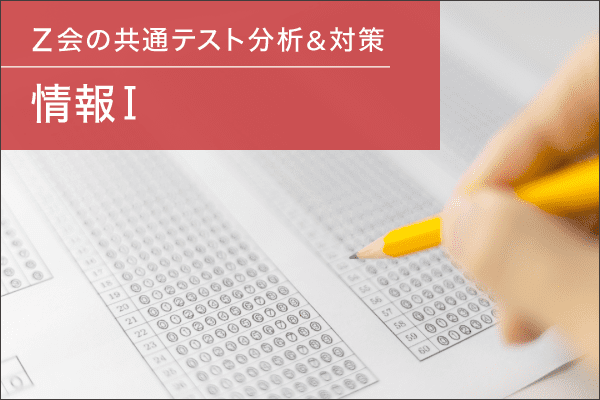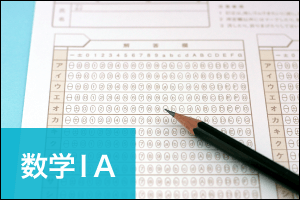地理総合,地理探究 – 2025年度共通テストの分析&対策の指針
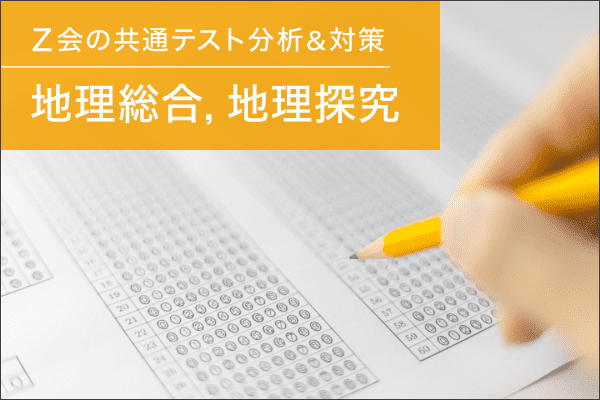
投稿日時:2025年1月19日
Z会の大学受験生向け講座の地理担当者が、2025年度の共通テストを分析。出題内容やカギとなる問題の攻略ポイントなどを解説します。
受験に役立つ情報をLINEで配信中!
Z会では、「Z会の通信教育」LINE公式アカウントで共通テストをはじめとする大学受験に役立つ情報を配信中。学習アドバイス・おすすめ講座情報・お得なキャンペーンなどを随時お届けしています。ぜひご登録ください。
共通テスト「地理総合,地理探究」の出題内容は?
まずは、科目全体の傾向を把握しましょう。分量、問題構成、難度などを解説します。
試験時間と配点
時間 / 配点:60分 / 100点
おもな注目ポイント
●大問数は6題、小問数・解答数は30で試作問題と同じ数であったが、各大問の配点や小問数は変化した。
●これまでの共通テスト「地理B」同様、すべての問題で資料が使用されている。資料の種類は、統計グラフ・統計表・地図・地形図・写真など多岐にわたり、複数の資料が提示された問題も見られた。
●大問テーマは、これまでの共通テスト「地理B」でも見られたテーマが出題された。但し、試作問題で出題された日本の国土像の大問単位での出題は見られなかった。地理総合分野では地域調査が出題された。
●出題形式は、全問題の半分以上の18問が組合せ形式の問題であり、三文正誤の8択問題も出題された。また、単答問題、正誤問題はすべて4択問題であった。
●基礎的な知識をもとに解答する問題が多く、難易度は標準的であった。但し、資料や組合せ形式の問題の多さから、解答には時間がかかる。確実な読解力が求められた。
大問別の難易度、配点、テーマ・分野
※難易度は共通テストの受験生を母集団とする基準で判定しています
| 第1問[標準](配点:13点) | 【地理総合】食料の生産と消費 |
|---|---|
| 第2問[標準](配点:12点) | 【地理総合】東三河地域の地域調査 |
| 第3問[やや難](配点:20点) | 【地理探究】世界の自然環境と自然災害 |
| 第4問[標準](配点:21点) | 【地理探究】エネルギーと産業 |
| 第5問[標準](配点:17点) | 【地理探究】産業構造の変化に伴う都市の変容 |
| 第6問[標準](配点:17点) | 【地理探究】インド洋周辺地誌 |
地理総合,地理探究の「カギとなる問題」は?
次に、「カギとなる問題」を見てみましょう。合格点をとるうえで重要な問題を取り上げ、攻略ポイントを解説します。
第2問問2
豊橋市における製造業の立地特性に関する正誤問題である。資料読解はもちろん、2地区で発達する工業の特徴から正誤を判定するなど、多角的な視点から解答を導き出す必要があった。
第3問問5
北半球と南半球の2つの緯度帯での上昇気温別面積割合の分布に関する問題である。「海氷面積の増減は気温上昇に影響を与える」という問題文もヒントにして考えられたかがカギであった。
第4問問2
工業立地に関する基本的な問題であるが、原料指数など、通常と異なる聞き方をされており、柔軟に考えることができたかがカギであった。
第4問問5
ファブレス企業とサプライチェーンに関する正誤問題である。教科書にも登場する用語であるが、用語の意味だけでなく、仕組みや利点などを幅広く押さえておく必要があった。
攻略へのアドバイス
最後に、次年度以降の共通テストに向けた攻略ポイントを確認しましょう。「地理総合,地理探究」で求められる力をふまえて、必要となる対策を解説します。以下の点を意識して学習に励みましょう。
早めの基礎知識の定着をめざす
共通テストでは、高校地理の幅広い分野からの出題が見られる。高3の夏休みの終わりまでに高校地理の学習範囲を終えたい。単純な知識問題は出題されない傾向にあるが、教科書の本文で太字となっている用語や地名・位置は最低限押さえるようにしよう。
日頃から資料に目を通す
土台となる知識量や地図・統計図表といった資料の読み取りが中心である点は、これまでと変化がないが、扱われている資料は初見のものが多く、多様になっており、資料の読解が複雑化している。さらに、グラフの指標だけでなく凡例についても答える問題や、地図で具体的な場所が示されない問題、複数の資料から経年変化を読み取らせる問題など、事前の資料学習の成果が発揮される出題が見られる。授業や演習で登場した地名・地域や内容について、日頃から地図帳や資料集で位置や範囲を確認し、分布や数値の特徴をつかむ習慣をつけるとよいだろう。
共通テスト特有の問題形式に慣れる
秋以降は、共通テスト特有の出題形式に慣れるため、模試形式の演習に多く取り組み、資料読解力を鍛えるよう心掛けたい。「地理総合,地理探究」では組合せ形式の問題が多い。すべての項目で正しく解答する必要があるため、解答のポイントを理由付けて考えられるようにしたい。また、共通テストでは、多くの設問文や資料文を読み解く必要があるが、これらが解答を考えるヒントとなっていることもあるため、素早く、正確に読解する力も身に付けておこう。
Z会の講座・お役立ち情報
大学受験生向け/毎月、着実に得点力を高める
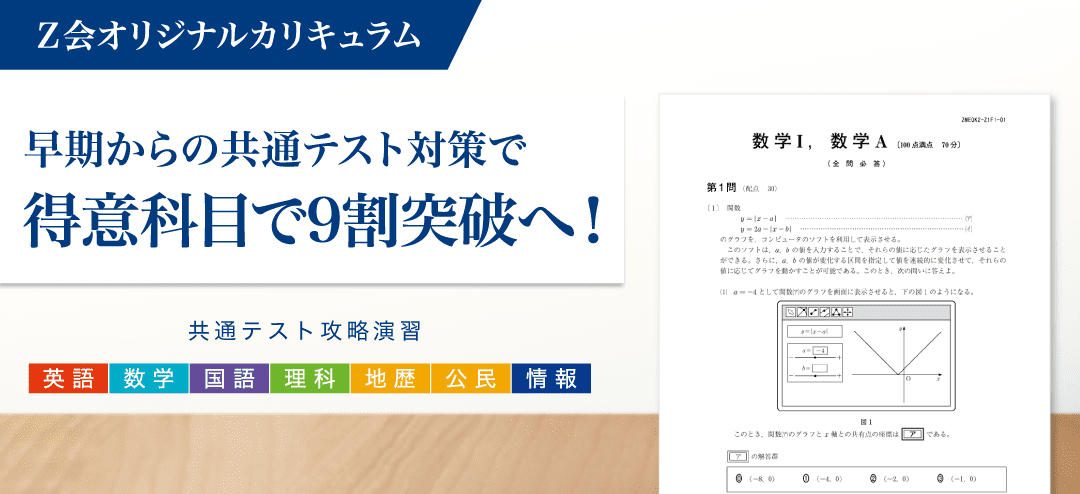
共通テスト対策はいつから何を、どう進めたらよいか悩むもの。
本講座では、試験本番での9割突破に向けて、毎月着実にレベルアップできるカリキュラムをご用意。
時期に合わせて必要な対策が進められます。
受験に役立つ情報をLINEで配信中!
Z会では、「Z会の通信教育」LINE公式アカウントで共通テストをはじめとする大学受験に役立つ情報を配信中。学習アドバイス・おすすめ講座情報・お得なキャンペーンなどを随時お届けしています。ぜひご登録ください。
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!
同じカテゴリの人気記事
共通テスト分析「傾向」と「対策」

数学Ⅰ,数学A – 2025年度共通テストの分析&対策の指針
Z会の大学受験生向け講座の数学担当者が、2025年度の共通テストを分析。出題内容や「カギとなる問題」の攻略ポイント、次年度に向けたアドバイスなどを詳しく解説します。 出題内容 カギとなる問題 攻略アド... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む