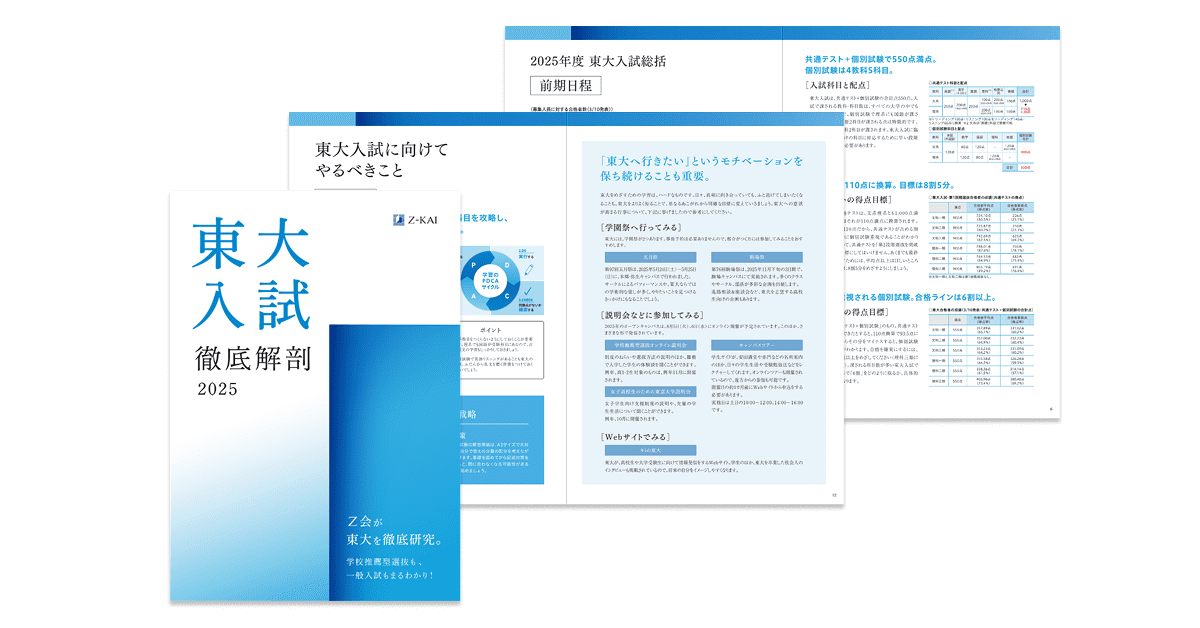Z会の東大講座担当者が、冬〜直前期にかけての「東大日本史」の学習ポイントをご紹介。【今から共通テストまでにやるべきこと】【共通テスト後→個別試験本番までにやるべきこと】を解説します。
今から共通テストまでにやるべきこと
1.苦手な時代・分野を残さない
共通テストでは、すべての時代・分野を満遍なく押さえておくことが重要です。
『歴史総合,日本史探究』では、「日本史探究」だけでなく「歴史総合」の学習も欠かせません。「歴史総合」の教科書を読み返すなど、今一度知識を確認しておきましょう。
「日本史探究」については、原始・古代〜現代まで、全時代から出題されます。戦後史が出題されることもあるので「昭和戦後史」の学習も怠らないようにしましょう。また、受験生が苦手にしがちな「社会・経済史」や、後回しになりがちな「文化史」も要注意です。
学習が不十分な時代・分野が残ったまま試験当日を迎えることのないよう、少しでも知識に不安がある箇所は、冬休みのうちにきちんと補完しておきましょう。
2.共通テストの予想問題に取り組む
基本的には、個別試験対策が共通テストのための学習を兼ねますが、共通テストでは特有の出題形式も見られます。また、知識・理解の確認に留まらず、知識を活用して思考する力を求める問題も出題されます。
試験当日に、落ち着いて問題に取り組むためにも、必ず、共通テストに対応した問題で演習を行い、出題形式に慣れておきましょう。
3.定期的に論述問題を解く
共通テスト対策が大事な時期ではありますが、その後の個別試験に向けて、論述力もキープしておく必要があります。毎日ではなくてよいので、今までに取り組んだ問題を解き直すなど、定期的に論述問題に触れるようにしましょう。
共通テスト後〜個別試験本番までにやるべきこと
1.知識を再確認する(とくに近・現代)
東大日本史は、独特の提示文から考えさせる問題が中心ですが、考えるための知識があってこそ、得点につながる解答が書けるものです。知識・理解で不安が残る時代・分野がある場合は早急に再確認しておきましょう。
とくに、近・現代史から出題される第4問は、提示文問題よりも、知識重視の問題が出題される傾向にあり、毎年多くの受験生が知識不足で痛い目を見ています。
近・現代史の学習が十分でない、知識が定着しきっていないという人(とくに現役生のみなさん!)は、教科書の明治期~昭和戦後の占領期あたりまでをざっと読み返しましょう。そのさい、用語や流れの説明につまるような部分があれば、時間を惜しまずに、教科書・参考書、過去問やZ会の添削問題の解説などを読んで、知識を整理しておきましょう。
2.提示文読み取り問題を復習する
過去問や模試、Z会の添削問題など、これまでに取り組んだ東大型の問題について、出来の悪かったものを中心に解き直して、提示文の読み方・解答への反映のさせ方を復習しておきましょう。
模範解答や解説と比べて、書きもらした要素があった場合は、「なぜ書くべきだったのか」という“考え方”を理解できているかどうか、確認しましょう。その要素の意味が理解できていれば、本番で似たようなテーマが出題された際に、応用して活かすことができます。
3.本番に向けてのシミュレーションをする
東大地歴は2科目で150分という時間設定です。大問4題が均等の分量で時代も固定されている日本史は、大論述を擁する世界史、問題数が多い地理に比べて、事前に時間配分を想定しやすいという特徴があります。
Z会の直前予想演習シリーズなどを使って東大日本史に即応した問題に取り組み、「設問・提示文の読み取り→構想を練る→草稿を書く→答案を仕上げる」という一連の流れをシミュレーションして、どのくらいの時間をかけて日本史の各問を解くか、戦略を立てておきましょう。
Z会の東大講座・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!