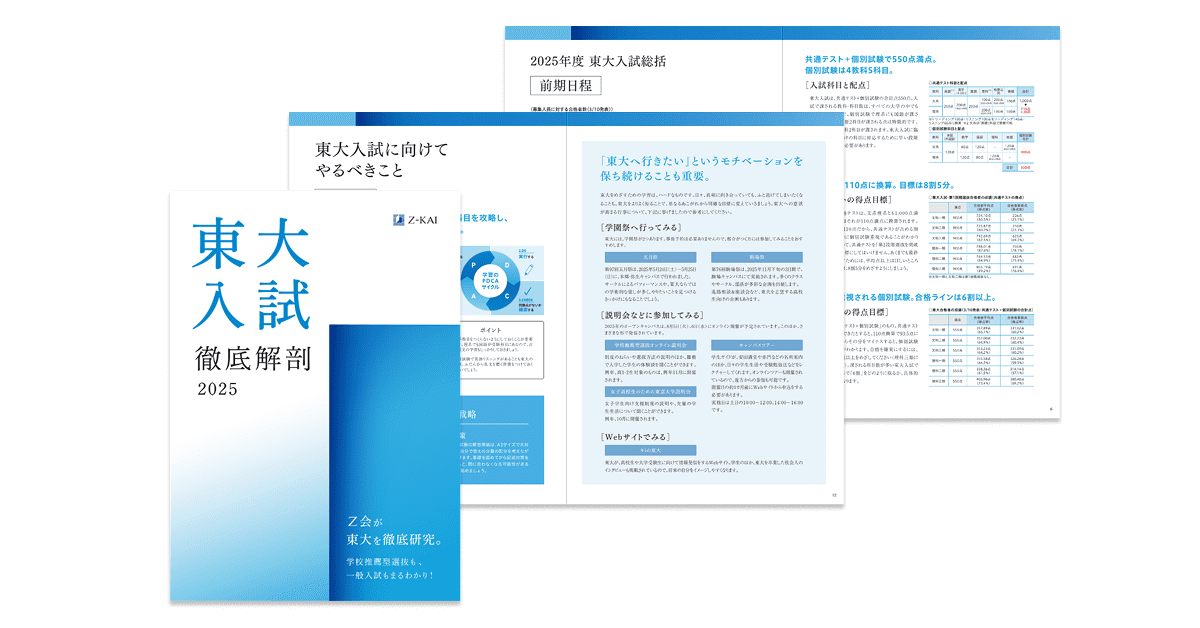Z会の東大講座担当者が、冬〜直前期にかけての「東大数学」の学習ポイントをご紹介。【今から共通テストまでにやるべきこと】【共通テスト後〜個別試験本番までにやるべきこと】を解説します。
今から共通テストまでにやるべきこと
共通テストの数学で問われる力
共通テストの数学では
問題解決のプロセスを構築するための、批判的考察力、統合・発展させる力、見通しを立てる力などを問う出題
がなされます。教科書レベルの基本的な手法や知識は大前提として、問われる知識は少ないながら、より深い理解が問われる出題が加わるということです。記述式の問題にしっかり答えられる力が要求されるともいえるでしょう。
実戦的な対策で、“出題の型”などを押さえよう!
問われる知識が少ないとしても、「どの知識が問われるのかわからない」ので、教科書に掲載されているすべての項目に関して、深い理解が必要になります。
とはいえ、これまでの出題を踏まえると、“出題の型”ともいえる特徴的なものが見えてきます。例えば、「簡単な例を通して問題解決のプロセスを学び、その過程を振り返って新たな問題解決を行う」というものが挙げられます。このような“出題の型”に事前に慣れておくだけでも、大きなアドバンテージになるでしょう。
まだ、過去問の蓄積が少ないため、不安な気持ちは大きいと思います。しかし、本番当日は「目の前にある問題を1問でも多く得点する!」という強い意思が好得点につながります。準備期間は、実戦的な対策ができる教材をフル活用し、“出題の型”や難易度感、時間配分を含めたシミュレーションを行っておくことが重要です。
共通テスト後〜個別試験本番までにやるべきこと
共通テストから個別試験まではおよそ1カ月。この時期には「新しいことに手を出しすぎない」ことが功を奏することが多いです。
- 添削済み答案をもう一度振り返って減点されやすいポイントを把握する。
- 1度解いた添削問題や過去問に別解がある場合はそれを研究してみる。
など、これまで行ってきた学習内容を振り返り、得られた力を確実に発揮できるようにしておくことがおすすめです。
また、東大を受験するみなさんには「釈迦に説法」かもしれませんが、東大の出題傾向に合わせて、各分野の学習の比重のかけ方を変えることも重要です。
- 東大文系:微積分、確率、整数、ベクトル、図形と方程式
- 東大理系:微積分、確率、整数、空間図形(体積を含む)
が頻出分野なので、これらの分野の学習に重点を置きましょう。なお、理系の微積分では図形が絡む問題、計算力を見る問題、論証力を見る問題など多様な出題が見られることにも注意が必要です。
また、東大数学は問題の難易度や分量に対して時間制限が厳しく、解答を短時間で簡潔にまとめ上げる力がきわめて重要となります。問題の解き方や考え方はもちろん、「答案にどう書くか」ということもつねに意識して問題演習に取り組みましょう。さらに、試験本番では「何を捨てるか」といった見きわめも重要となります。試験開始直後に問題全体を見渡し、各問題の大雑把な方針を考えながら、解くべき問題の優先順位をつけるとよいでしょう。そのために、(これまでの学習の振り返りを中心としつつ)「初見の問題」にも積極的に取り組み、“実戦感覚”を養っておくのが理想です。
そこで、出題傾向・難易度などを本番に合わせたオリジナル予想問題に取り組める直前予想演習シリーズがおすすめです!直前予想演習シリーズには、東大受験生の答案を長年見てきた精鋭の添削者による添削指導もつきますので、答案への記述力も磨くことができます。
Z会の東大講座・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!