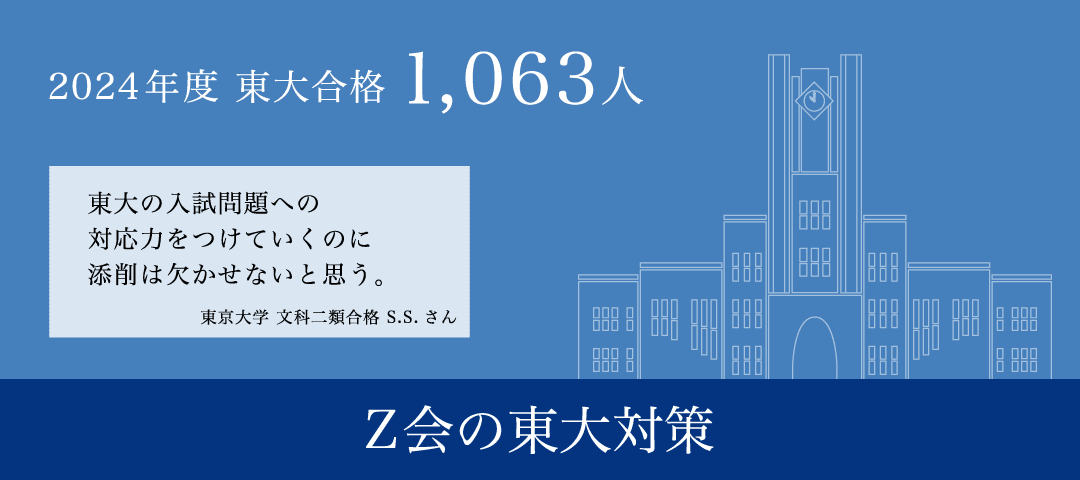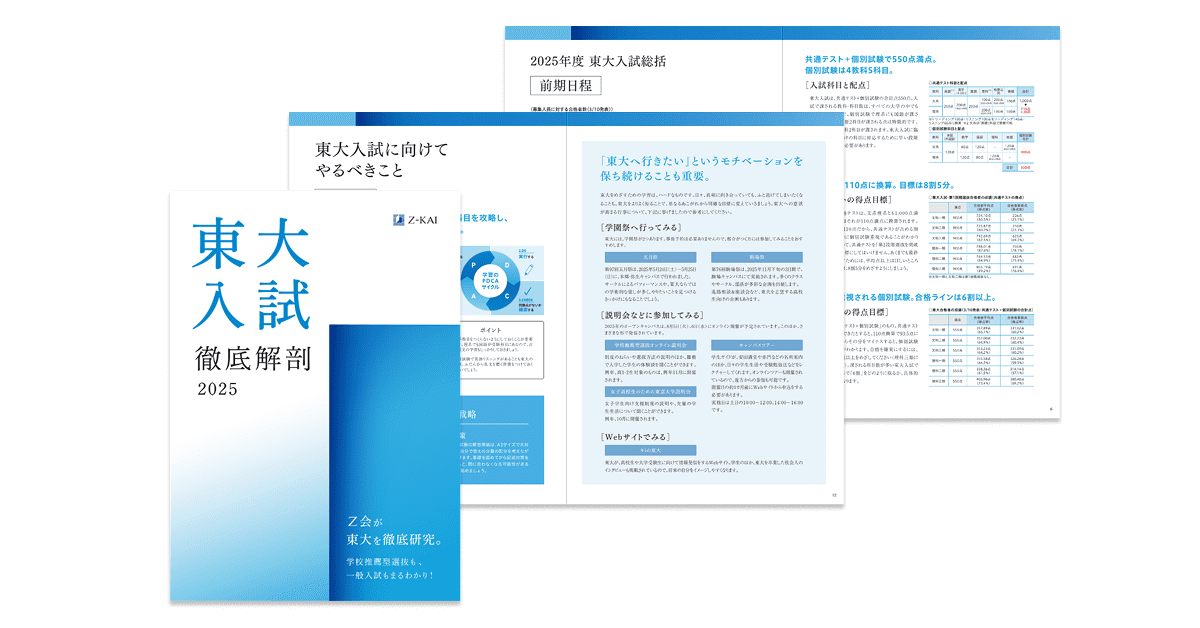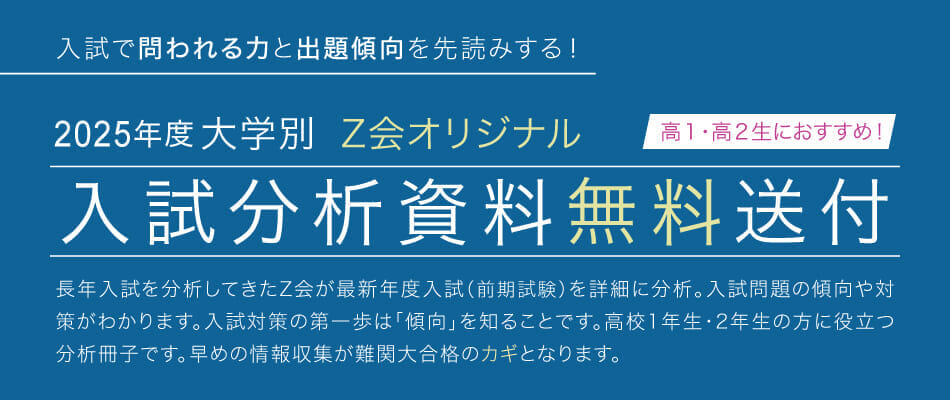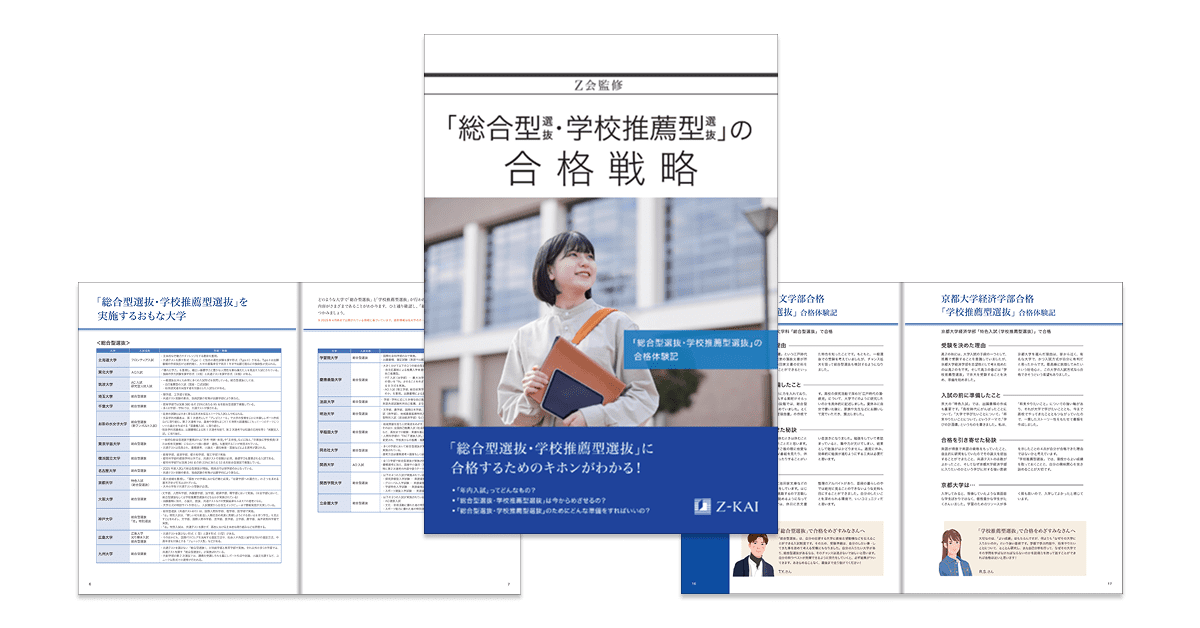Z会の大学受験担当者が、2025年度前期試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、今年の傾向と来年に向けた対策を解説します。
Z会地理担当者からのメッセージ
2025年度の東大地理は、問題の難度は高くなかったものの、2024年度よりも資料数や論述の問題数・字数が大幅に増えたことによる「時間の配分力」が重視された出題となりました。また、少ない字数で問題の要求通りに解答する「表現力」も、高得点を目指す重要な要素となっています。出題テーマでは、近年見られるようになった、「現代社会の諸課題」に関する問題が、2025年度でも多く出題されました。日頃から世の中の出来事にアンテナを張り、地理に関連しそうなテーマやキーワードをピックアップし、概要や問題点・具体的な対策をまとめておくことをお勧めします。
本科「東大講座 地理」では、東大地理の出題内容を分析し、事項説明や図表の読み取りをもとにした論述問題を、幅広い分野から多数出題しています。東大をめざすみなさん、Z会と一緒に頑張っていきましょう!
今年度の入試を概観しよう
分量と難度の変化 (時間:2科目150分)
- 難易度は2024年度から変化なし
- 分量は2024年度から増加
2025年度入試の特記事項
- 論述総字数は2024年度の990字から大幅に増加し、1,170字であった。論述問題数も2024年度から増加し19問であった。指定語句を用いた問題は4問に増加したが、単答問題は20から10へと大幅に減少した。
- 2024年度では日本に関する大問単位や中問単位での出題が見られなかったが、2025年度では第3問で出題された。地形図の読図に関する出題は見られなかった。
- ファストファッションや観光、新型コロナウイルスの感染拡大による人々の移動など、時事的な内容を扱った問題が多く見られた。
合否の分かれ目はここだ!
例年通り問題数は多いが、定番のテーマや基礎的な問題をミスなく押さえ、時間配分を考えながら解答しきることが重要であった。時事的な問題が多く見られたが、教科書での基礎用語の確認や、日頃からテレビ・ラジオや新聞の特集などでの情報収集など、幅広い視点からのアプローチにより、解答の糸口を見つけられたかどうかが合否の分かれ目となった。また、単答問題は確実に正解し、得点を積み重ねることも重要である。
さらに詳しく見てみよう
大問別のポイント
第1問
自然環境への人間活動の影響(論述60字×6、単答) [標準]
設問A 高緯度地域における温暖化の影響に関する問題。基本的な問題が多く、確実に解答したい。
(2)はグラフの他の項目に惑わされず、多角的に考えることがカギである。(3)は永久凍土の融解による温暖化の仕組みを説明する問題であるが、地中のメタンが影響することは基本的な事項である。(4)は2021年度の第1問でも同様の内容が取り上げられている。過去問の対策が重要となる問題であった。
設問B 人間活動による河川流域の環境の変化に関する問題。各地の自然・社会状況や、河口部の自然災害など、幅広い内容から考察する出題であった。
(1)は各河川が位置する気候環境から確実に解答したい。(2)はグラフの数が多いものの、読み取りは難しくなく解答しやすい。(3)は東南アジアの経済発展に気づけたかどうかがポイントであった。(4)は図より河口部が狭くなっていることから、自然災害発生時の海側と河川側双方から見た河口砂州の役割を考えたい。
第2問
近年活発化する経済・余暇活動(論述30字×1、60字×4、90×2、単答) [標準]
設問A 衣服の企画、生産、消費に関する問題。ファストファッションは、近年、教科書にも掲載されるようになった用語である。このような用語についても確認できているかどうかで点差が開く出題であった。
(1)は市場指向型工業の説明であり解答しやすい。(2)はベトナム、バングラデシュなどを取り上げ、中国より優位になってきた点を説明したい。(3)は指定語句「天候」の使い方が難しい。ファストファッションの意味を考え、「天候」は消費者側の立場で使いたい。(4)はEUだけでなく、他地域の事例も考えると答えやすい。
設問B 近年の日本の観光や旅行に関する問題。外国人旅行者の増加による影響は、テレビ・ラジオや新聞の特集でも取り上げられており、取り組みやすいテーマである。問題の要求に沿って確実に解答したい。
(1)は日本人と外国人の旅行先の傾向の違いも読み取り判断しよう。(2)は設問Bリード文の「業務活動を目的とする」もヒントとなる。(4)は解決方法と反対意見の様々な事例を考えつつ、バランスよく説明したい。
第3問
人口の分布と移動(論述30字×2、60字×2、90字×2、単答) [標準]
設問A 首都圏の人口集中地区の変化に関する問題。東大地理では頻出のテーマである。
(2)は地図上の同心円の距離と「時間距離」の違いを考え、この違いはどのようにして生じるかを考えるとよい。(3)は起点となった出来事を指摘し、その後の都市や人口分布の変化を説明したい。
設問B 新型コロナウイルスの感染拡大による人口移動に関する問題。理由を複数説明する必要があり、多角的な視点からの分析を必要とする出題であった。
(1)は変化率の読み取りを間違えないようにしたい。2021年に人口減少が緩和した理由については複数考えられる。(3)はテレワークなど新しい勤務形態の普及については考えやすいが、もう1つの理由を考えるのが難しい。(4)は「リアルタイムでの人口移動」もヒントとなる。
攻略のためのアドバイス
東大地理を攻略するには、次の3つの要求を満たす必要がある。
●要求1● 使いこなせる知識力
東大地理では、全分野・地域の基本事項を覚え、使いこなす“知識力”が求められる。なかでも、自然地理(地形・気候・植生など)に関する出題とそれに関連する農牧業・文化・環境問題の出題が多い。これらに対応するため、自然地理に関する知識をとくに確実なものにしておく必要がある。
●要求2● 多くの情報を読み取る資料読解力
東大地理では、統計資料・地図などから多くの情報を読み取る“資料読解力”を必要とする問題が多い。とくに資料から国名・品名などを判定する問題に正解することは、合格点確保には必須である。また、地形図の読図問題が出題されることもあるので、地形図の基本的な読図力も養っておきたい。
●要求3● 簡潔・確実に解答できる表現力
東大地理の出題形式の中心は、60字の論述問題である。指定字数の少ない論述問題に対応するには、問題で要求された条件に対して、簡潔・確実に解答する“表現力”が求められる。それには、「題意を正確に把握し、聞かれていることだけに答えること」「掲載資料・リード文の意味を読み取り、それらを踏まえていることが伝わる表現を解答に織り込むこと」を意識した論述演習が必要である。
また、地理は問題数が多いため、過去問なども使い、時間配分を意識した演習も重要である。
対策アドバイス
基礎力の完成
まずは要求①を満たすため、教科書学習を中心に、学習が手薄な分野・地域をつくらないように努めよう。Z会の通信教育の講座を利用するなどして、高校3年生の夏までには教科書の全範囲の学習を終わらせておきたい。とくに、東大地理で頻出の自然地理や日本地理(とくに人口・都市・産業)の苦手分野は必ずなくしておくこと。また、要求②を養うため、統計集や地図帳に日頃から目を通す習慣をつけ、統計の持つ意味を理解しておくことが重要である。
東大型の問題への取り組み
入試で総字数1,000字程度の論述問題を75分ほどで取り組むことを想定すると、遅くとも高校3年生の夏までに、論述力養成にも着手したい。なお、東大地理の攻略には、過去問などで傾向を知り、東大型の問題演習を繰り返すことが有効かつ効率的である。高校3年生の秋以降は、Z会の通信教育の本科「東大講座 地理」で、これまで身につけた要求①・要求②の力を試しながら「複数資料の比較」や単答問題がその後の論述問題と関連する「芋づる式」などの東大型の問題に取り組み、添削指導を受けることで、要求③を磨いていこう。
実戦演習
「素早く」「確実に」資料を判読することで失点を抑え、答案の完成度を高めて得点の上積みができるようにしておきたい。Z会の通信教育の本科「東大講座 地理」では、直前期に入試に対応した出題をしている。制限時間・時間配分や問題に取り組む順序などを意識して要求①~要求③を鍛えつつ、より本番に近い形で得点力のある答案を作成する訓練を積もう。
Z会でできる東大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!