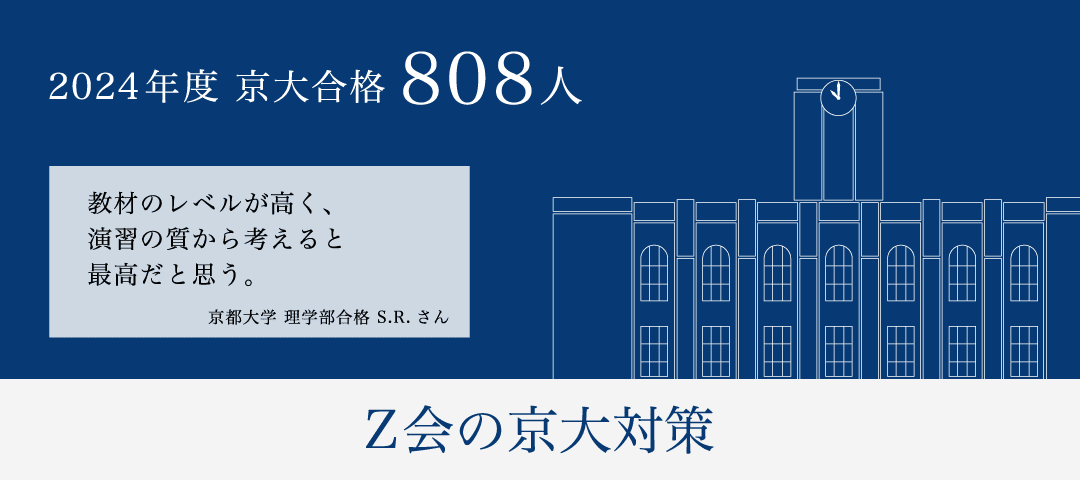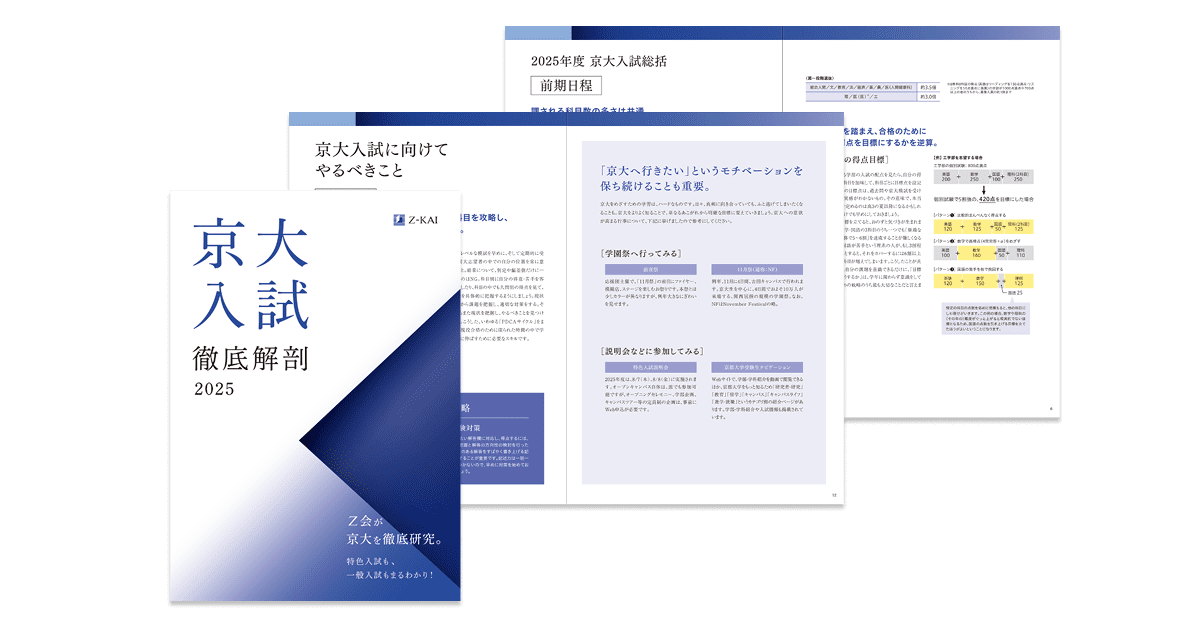「受験勉強は計画性が大切…」とよく言われるものの、スケジュールを立てるうえで悩みをもつ受験生も多いはず。そこで今回は、京大受験生から「スケジュールに関するお悩み」を募集し、京大に合格した先輩に回答してもらいました!
気になるトピックをお選びください。
「苦手克服に手こずっているが、それでもこだわって取り組むべき?」
京大に合格した先輩にお伺いします!
苦手の克服にどうしても時間がとられてしまいスケジュールどおりに進みません。それでも苦手克服には時間をかけるべきでしょうか?
時間のかからない苦手克服法を考えることが必要だと思います。自分にもいくつか苦手はありましたが、その時間を邪魔だと感じたことはありません。むしろその為に勉強しているのだと思います。何ができないから苦手なのかを考えて取り組めば、時間をかけすぎずに苦手克服ができると思います。
(京都大学工学部工業化学科)
(京都大学工学部工業化学科)
私も苦手科目があり、秋以降も多くの時間を割きました。スケジュール通りに進まない焦りもあるでしょう。しかし、60点を90点にするよりも、30点を60点にする方が効率よく点数をあげられるはずです。程度の差はあれど、苦手に向き合うことが一番の近道だと思います。ありふれたアドバイスですが、「間違えた問題を大切にする」ことや「先生や友達に助けてもらったり丁寧な解説を熟読したりする」ことで、格段に理解が早まるはずです。
(京都大学法学部)
(京都大学法学部)
「苦手」の度合いによりますが、苦手科目を得意科目にするような勉強は必要ありません。残り半年でそれをするのは現実的ではないと思います。私は数学が苦手でしたが、得意な日本史でカバーすると決めて日本史に力を入れたところ、本番では平均して6割5分=合格ラインに達することができました。志望学部での配点が高かったり、苦手分野が頻出だったりする場合には、毎日コツコツ取り組んで苦手を「軽く」していく必要がありますが、苦手ばかりにこだわって得意分野の勉強が疎かになり、得点源を失うのはもったいないと思います。
(京都大学文学部人文学科)
(京都大学文学部人文学科)
「応用問題集と過去問、どちらから取り組むのがおすすめ?」
京大に合格した先輩にお伺いします!
「応用問題集に取り組んでから過去問演習に入る」のと「過去問演習を始めてから、適宜、応用問題集に戻る」のと、どちらのほうがよいのでしょうか?
どちらでもよいと思いますが、私は力のついた状態で過去問に挑みたいと考え、応用問題のあとに過去問に取り組みました。時間がなければ並行してやるのもよいかもしれません。
(京都大学法学部)
(京都大学法学部)
実際に試験を作る人達が作った過去問に取り組むことは非常に有効だと思うので、過去問で演習量を稼ぐこと、赤本で実際に近いシュミレーションを行うことを、秋以降は定期的に行うべきだと思います。ただ、それだと特定分野に偏ってしまったり、急な傾向変化や志望大変更のさいに不利になったりするので、応用問題集に取り組むことも必要です。過去問演習を軸にしながら、応用問題集で補完していくという形がよいのではと思います。
(京都大学工学部工業化学科)
(京都大学工学部工業化学科)
過去問演習を始めてから、適宜、応用問題集に戻るのがおすすめです。秋の志望大学別の模試までに志望大学の傾向をしっかりおさえ、今後の受験勉強の指針を持つために、過去問演習に着手しておいたほうがよいと思います。
(京都大学文学部人文学科)
(京都大学文学部人文学科)
「問題集の選び方・取り組み方のコツは?」
京大に合格した先輩にお伺いします!
「この問題集の次はこれ」のようなおすすめの順番をよく耳にするのですが、予想以上に時間がかかり、全教科でそれをやるには時間が足りません。問題集の選び方・取り組み方で、なにか工夫はありますか?
「おすすめの順番」はあくまで一般論ですから、自分に合わせて臨機応変に考えましょう。私の経験では、複数の問題集に中途半端に手をつけるよりも、1冊をしっかり仕上げた方が効果的です。内容を見て、自分に合いそうだと思ったものに絞って取り組むのがよいと思います。
(京都大学文学部人文学科)
(京都大学文学部人文学科)
この場合、参考書の問題全てに取り組む必要はないでしょう。参考書の目次欄から、自分の弱いところを厳選してその部分を中心に取り組むのがよいと思います。どうしても不安なのであれば、全ての問題を解くのではなく、分かっている部分は読んで再確認する程度に留めるのがいいでしょう。
(京都大学教育学部教育科学科)
(京都大学教育学部教育科学科)
問題集はあくまでも手段の一つなので必須ではないですし、解くことが目的となっては元も子もありません。試験日から逆算して、自分に本当に必要なのか考えることが大切だと思います。その上で時間が足りないのであれば、一部を掻い摘んで解いたり、短期で終わらせられる別の手段を講じたりすべきでしょう。
(京都大学法学部)
(京都大学法学部)
最終的に入試で点数が取れるのがゴールです。時々過去問や模試を解いてみて、自分の到達具合を測り、それに合わせて取り組む問題の量は調節すればよいと思います。
(京都大学総合人間学部総合人間学部)
(京都大学総合人間学部総合人間学部)
Z会の京大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!