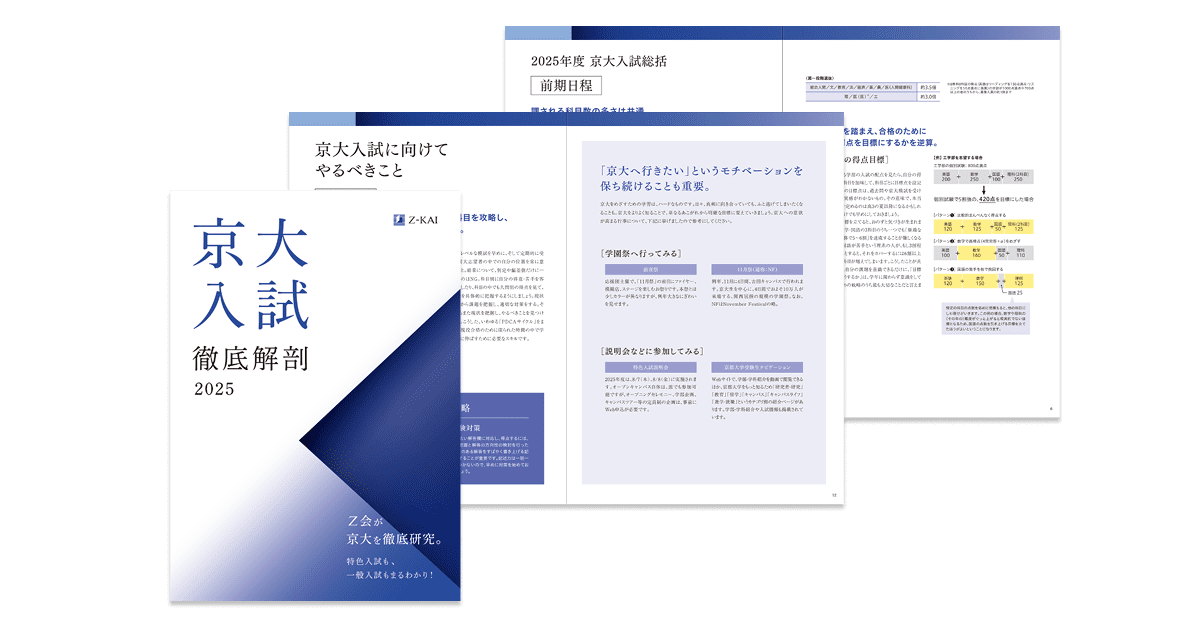今回のテーマは「記述対策、論述対策を自宅でやるにはどうすればよいか?」です。京大入試では避けて通れない上に、独学での対策が難しい「記述対策、論述対策」。Z会を受講して合格を勝ち取った京大生の先輩9名の「学習上の工夫」や「Z会の添削の感想」といった自身の経験をもとに答えます!
受験生のお悩み
記述対策、論述対策を自宅でやるにはどうすればよいか教えて下さい。
京大生が回答!
京大の記述対策・論述対策はプロに見てもらう必要がある。
記述や論述は、一人の自宅学習では限界があると思っています。学校の先生にお願いできるのであれば、添削してもらった方がよいです。
それが難しい場合は、Z会の通信教育 大学受験生向けコース「京大講座」のほか、直前期に予想問題を添削してくれる「直前予想演習シリーズ」があるので、活用するべきだと思います。
そのうえで、返されたものについてはしっかり復習することが大切になります。私は英作文・和文英訳については自分でノートに「問題・自分の解答・どこが直されたのか・模範解答」を書いて、同じミスを繰り返さないように注意していました。
過去問をよく見て、傾向と対策を知ること、可能であれば学校の先生などにメールで連絡をとって、添削をお願いしてみても良いと思います。
最初はまず書いてみることが大事なので時間など気にせずじっくり解くのがいいと思います。過去問演習をする頃になったら、時間をはかって本番を模した解答用紙で解く経験を積むことが大事だと思います。自分の解答はプロに見てもらって、自分の言葉で解き直すと身につきやすいです。
解答解説が詳しい問題集を使う。
解答解説が詳しい問題集を選び、どのポイントが採点基準になっているのか意識しながら答え合わせと復習をするようにしていました。
解説が詳しい問題集をえらぶこと。その上で、設問意図を汲み取って記述していくという練習を何度も繰り返すことをおすすめします。
また、社会の論述ではポイントや流れをルーズリーフにまとめ、復習することで、オリジナルの論述テキストができ上がります。
自分の解答と模範解答を照らし合わせて、模範解答に使われている言葉の意味や構文が何を示しているのか、なぜそうなっているのかをかみ砕いて、自分の解答との相違点を具体的に出して、それが間違いなのかを確かめる必要があると思います。
記述・論述に強いZ会、先輩たちはどう使った?
Z会の通信教育 大学受験生向けコース「特講:過去問添削 京大」を受講しました。実際の入試と同じ時間割で解くことができ、本番の流れの練習になりました。英語、国語などは添削もしていただけたのでとてもありがたかったです。
Z会の本の『段階式 世界史論述のトレーニング』や『文系数学 入試の核心』を使用していました。解説が丁寧なので、自宅で一人で勉強していてもつまずかないで勉強できると思います。
Z会からのアドバイス
先輩たちの体験談、いかがでしたでしょうか?先輩たちに共通して言っているのは「独学では記述対策・論述対策は厳しく、プロの目で解答を見てもらうことが欠かせない」「解説が詳しい教材を使うこと」でしたね。この点を意識して、今後の学習を進めていってください。
Z会の添削指導については、こちらのページで詳しく確認することができます。ぜひご覧ください。
Z会の京大対策・ご案内
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!