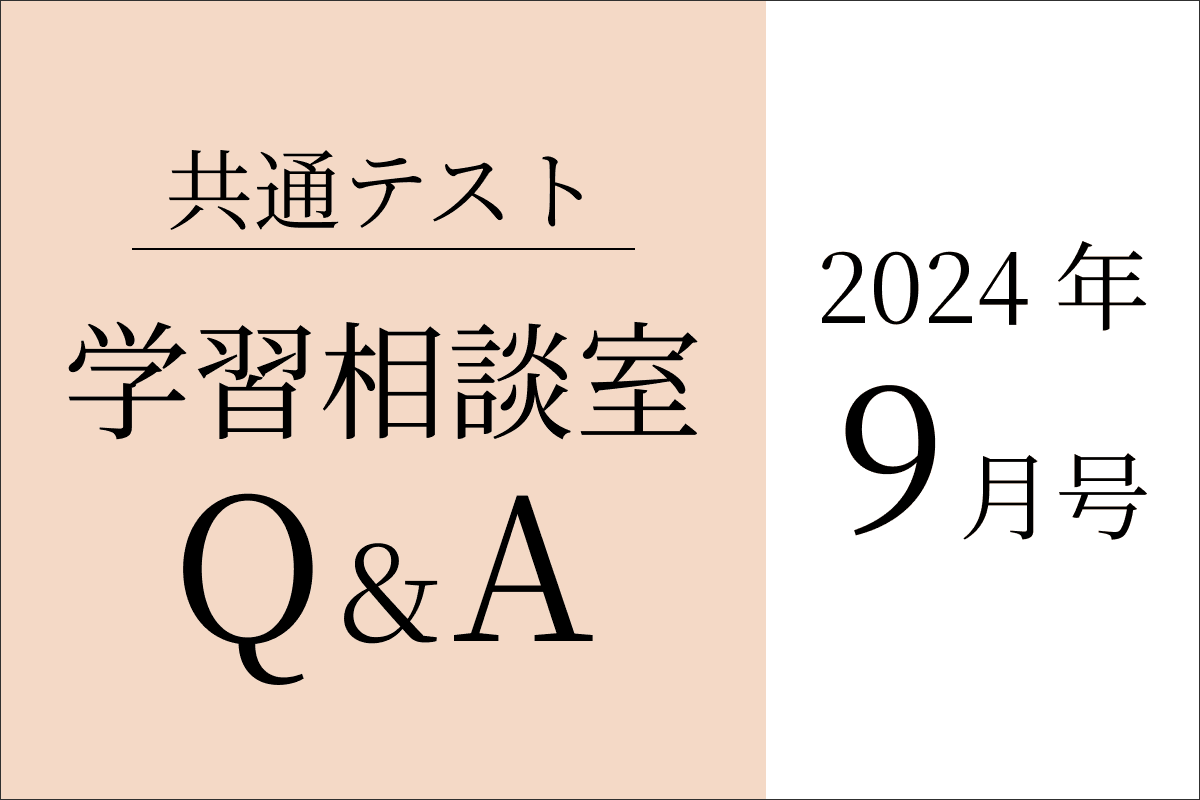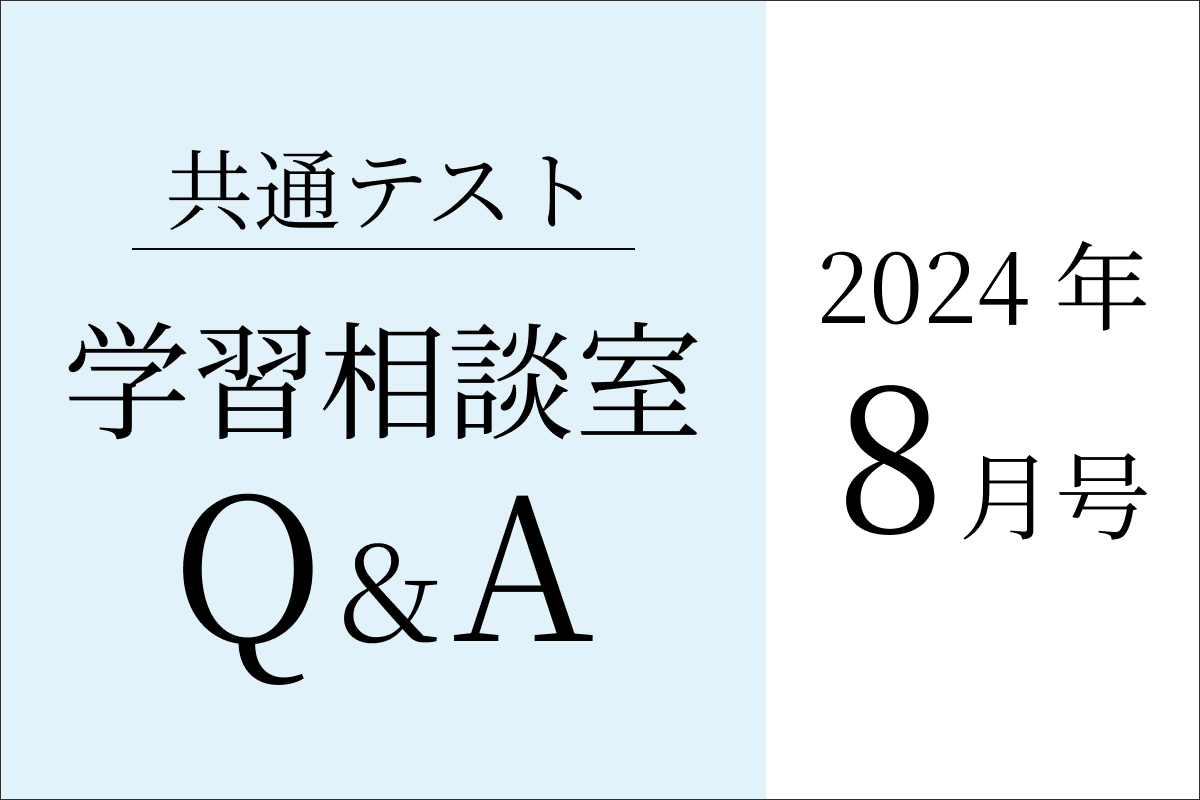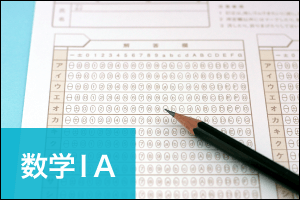共通テスト学習相談室(2023年4月号)
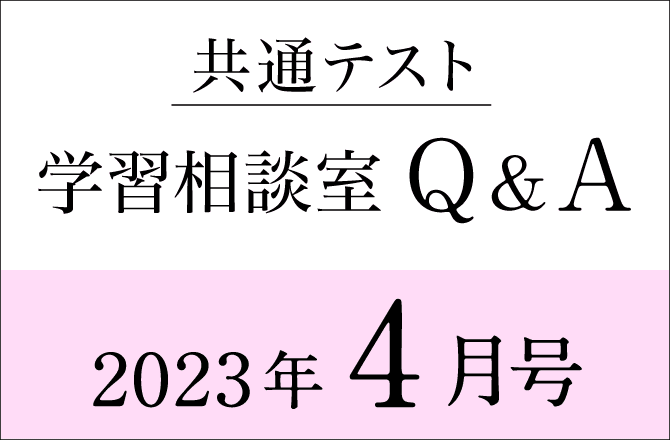
投稿日時:2023年4月28日
今回は前月号に引き続き、共通テスト前後の時期に寄せられた質問を紹介します。本番に即したリアルなお悩みが多数寄せられました。
模試はいつごろからどのくらい受けるべきですか?
受験生の悩み
年間計画を立てているのですが、模試を多く受けすぎると復習の時間が足りなくなるような気がします。
1年間どのようなスケジュールで受験するのが良いか教えてください。
【高3、京都大学 総合人間学部 志望】
Z会がお答えします!

模試については、共通テスト模試は年4回程度(①5月あたり、②夏、③秋、④直前期)を軸にして、試験時間内での得点率を最大化することを目的として、受験すると良いです。
記述型の模試は、夏と秋の京大模試(実戦・オープン)を計4回受験すれば十分です。
5月の駿台全国は、受験後の自分の実力を試すのには良い機会なので、受験してもよいかもしれませんね。
Z会の講座「共通テスト攻略講座」の難易度は?
受験生の悩み
Z会の「共通テスト攻略講座」は、実際の共通テストと同じくらいの難易度を想定していますか?
【高3、千葉大学 医学部 医学科 志望】
Z会がお答えします!

Z会の共通テスト攻略講座は、共通テストと同じ難易度の問題演習をするわけではなく、どうすれば本番で9割を取れるか、ということを主眼においてカリキュラムが作成されています。そのため、共通テストと比較してきっと歯ごたえを感じる問題もありますが、必ずしも難しい問題ばかり、というわけではありません。
演習内容自体も毎月共通テストと同じ形式の問題を解く、というのではなく、各月毎にテーマが設定されており、それに応じて演習を通じて実力を強化していくという内容になっています。毎月ペースよく取り組むことで効率よく共通テスト対策を進めていくことができます。ぜひ時間を取って取り組んでくださいね。
数学:学力が足りない、計算が遅い。対策を教えてください。
受験生の悩み
根本的な学力が足りない、計算のスピードが遅いことが弱みなので、対策として数研出版の教科書傍用問題集「スタンダード」に取り組もうと思っています。
計算力を上げるために基礎的な問題集に戻る選択肢はありでしょうか?
【高3、京都大学 農学部 志望】
Z会がお答えします!

数学の実力の判定を共通テスト模試のみに頼ると、正しく測れていない可能性がありますので、注意が必要です。共通テストはあの形式の問題を試験時間内に処理することが難しい試験であり、低得点がすなわち数学の学力が足りていないという結論にはつながりません。
上記のような事情がありますので、もう一度同じ問題に時間無制限で取り組み、今の実力で解けない問題がないかを確認してください。時間無制限であれば全ての問題に着手でき、ほぼ正解できるという状態にあるならば、計算スピードを意識しつつも、より難度の高い、京大入試に近い問題での演習を続ければ良いと思います。逆に解けない問題があるなら、スタンダードを用いてその分野の基本事項を復習し、入試問題を解くことができるように理解を深めておくことが重要です。
入試までの時間は限られますので、計算スピードを上げるというような単発の問題解決のための対策を行うのではなく、計算スピード「も」上げる、という形で、他の対策の中に課題を組み込む視点が必要ですよ。
世界史:基礎的な勉強法について、アドバイスがほしいです。
受験生の悩み
世界史Bを受験する予定です。
共通テスト対策として、山川の「大学入学共通テスト対応30テーマ世界史問題集」を購入したのですが、難しすぎてとても時間がかかりました。まだ基礎が固まっていないうちは、もっと基礎的なツールを購入して取り組んだほうが良いのでしょうか。
学校で購入したのは、教科書と資料集、用語集だけで、問題集は買っていません。
また、世界史の勉強法で何かアドバイスがあればお願いします。
【高3、東京大学 理科二類 志望】
Z会がお答えします!

知識が不足しているか、「使える」知識として定着していない可能性があるので、教科書を中心に時代の流れの把握→同時代の地域同士の関係性の確認→特定時代の特定地域の政治・経済・宗教・文化など、という形で知識の整理を行うと良いと思います。
資料集で視覚的な情報を、用語集で用語の情報を補完しながら教科書を読み進めると、断片的な知識が時代に沿った縦のつながり、あるいは同時代の横のつながりとして理解できます。これを行いながら、山川の世界史問題集に再度取り組んでみてください。
地理:論述について、おすすめの勉強法を教えてほしいです。
受験生の悩み
知識はある程度は埋まっていると思い、最近はテーマ別の論述の参考書をやっているのですが、身についている感じがしないです。
おすすめの勉強法などあったら教えていただきたいです。
【高3、東京大学 理科二類 志望】
Z会がお答えします!

地理の論述では知識や文言の表面的な理解(暗記)だけでなく、その背景や影響なども含めた理解が問われます。その点では、歴史科目の論述対策と共通します。
例えば気候では、気候帯の分布を覚えるだけでなく、それぞれの気候帯の成因やその特徴の説明が求められます。
基本は問題集を使った学習になりますが、「実力をつける地理100題」(Z会)や「納得できる地理論述」(河合塾)などの問題集を解いて、自らの言葉でどこまで論述できるかを把握しましょう。そのうえで模範解答や解説を読み、捕捉しきれなかった要点や誤った理解がないかを確認し、補足や修正を図ります。
加えて、「新詳資料 地理の研究」(帝国書院)などの資料集で出題分野の周辺知識を補強すると、類題対策としても効果的です。ノートを1冊用意して学習に取り組み、周辺知識も含めて自分の言葉で説明できるように仕上げていきましょう。論述対策にはZ会の東大コースのご受講もお勧めです。
Z会からのアドバイス
共通テストの難易度を気にしている方が多いようですが、共通テストの難しさは
①形式が独特である
②試験時間に対する分量が多い
の2点に集約されます。
ということは、基本的な問題を素早く解答できる力を身につける(②への対応)と、共通テスト型の問題演習を通じて、形式に慣れる(①への対応)の2種類の対策が必要であると言えます。
春先は、個別試験対策も含めて、自身の学力を増進することが重要な時期ですので、「正確な知識の定着」「確かな処理能力」、つまり②を見据えた、解答のスピードと正確さを養成するトレーニングを積んでください。
基礎を「完璧にする」ことは、普通に考えると不可能ですので、「できることを増やす」イメージで勉強を進めると良いです。既習範囲をざっと見渡して、弱い分野・項目を見つけ、その弱点克服に時間を費やしつつ、全分野的に問題演習を行うと、全体的なレベルアップを図ることが可能となり、その結果が共通テストにおける高得点につながります。
(Z会高校学習支援担当 山邊圭祐)
Z会でできる大学受験対策
◆[専科]共通テスト攻略演習(高3生向け)
共通テストの傾向をふまえた教材に取り組みます。毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。共通テスト型の問題に慣れ、得意科目9割突破を狙いましょう。
同じカテゴリの人気記事
共通テスト学習相談室
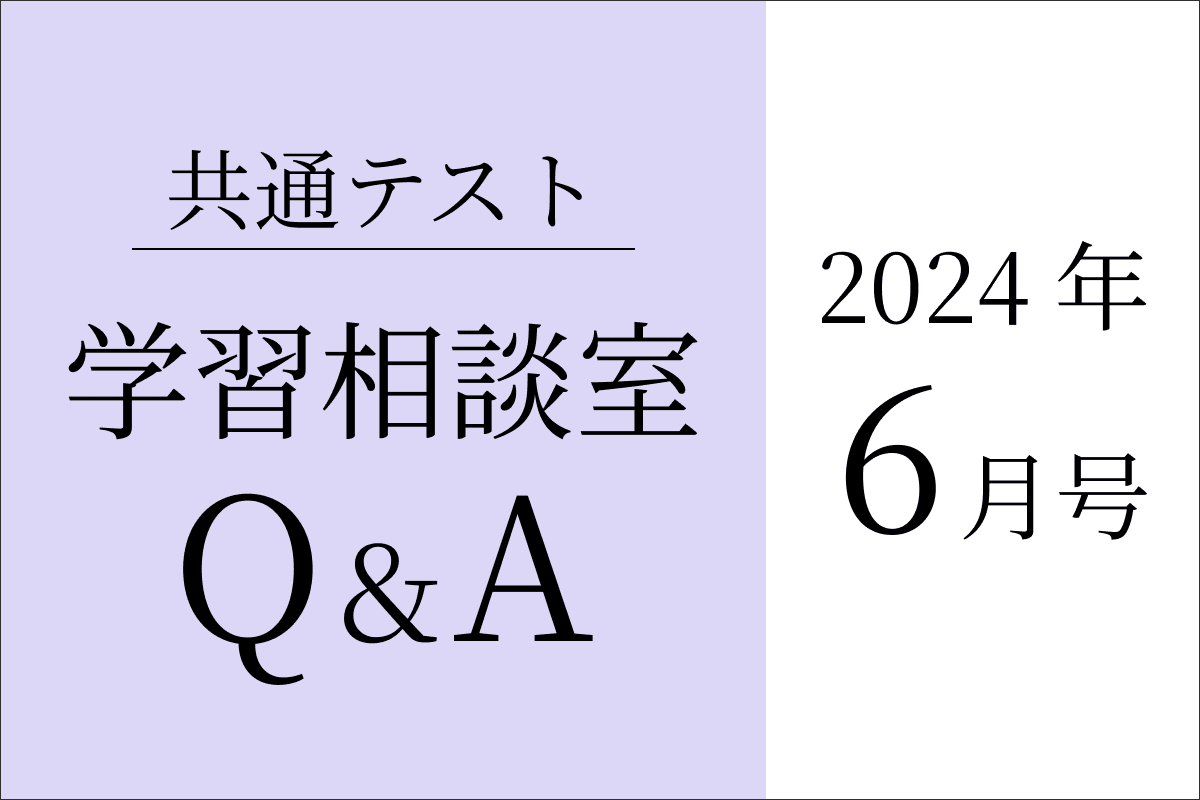
共通テスト学習相談室(2024年6月号)
2025年1月実施の共通テストから「情報」が追加されることが決まっており、皆さんもどのように学習を進めていったらよいのか、気になっていますよね。今回は「情報」についての相談(おすすめ問題集・参考書、学... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む