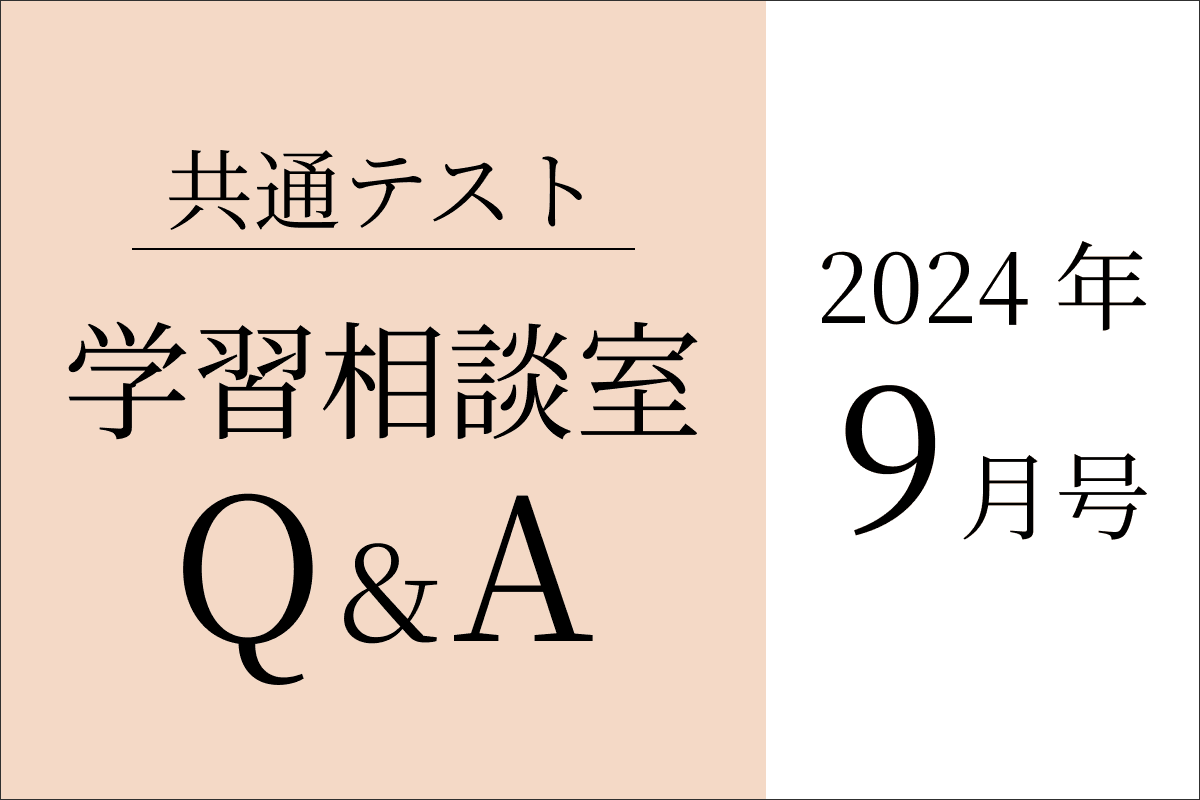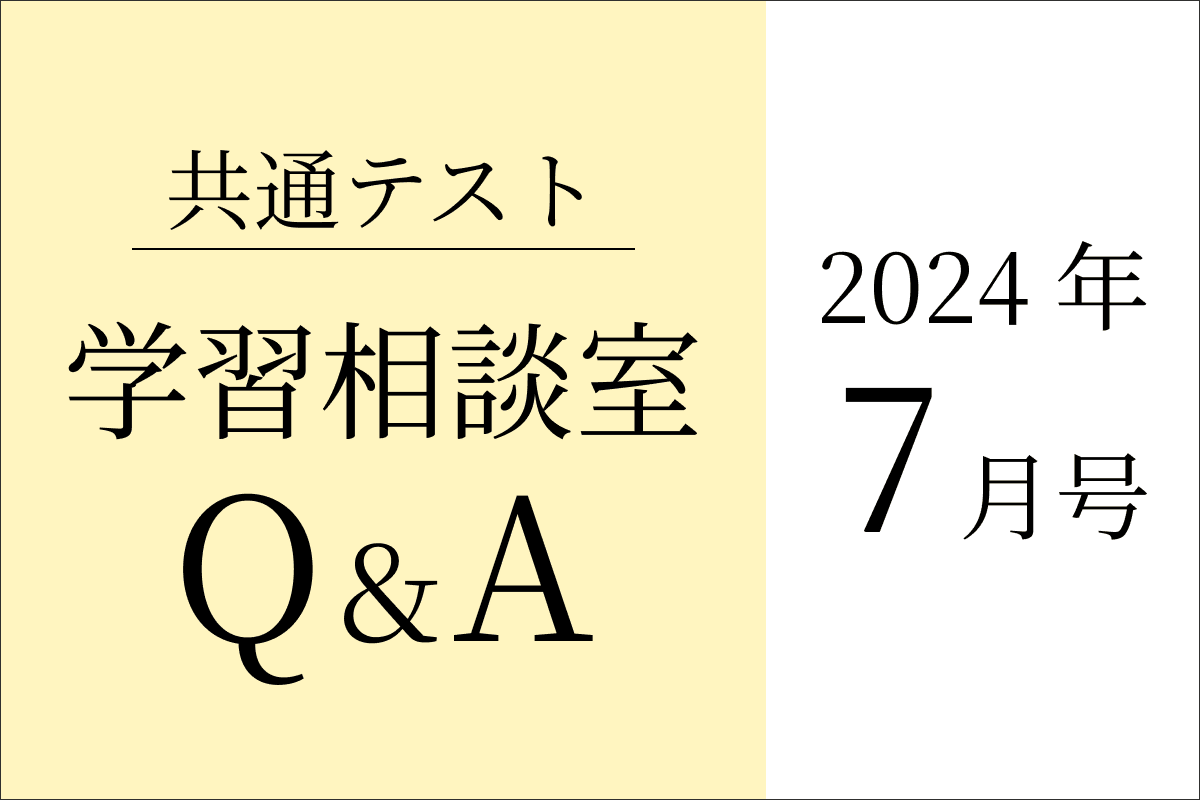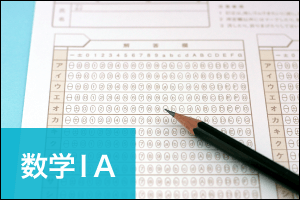共通テスト学習相談室(2024年8月号)
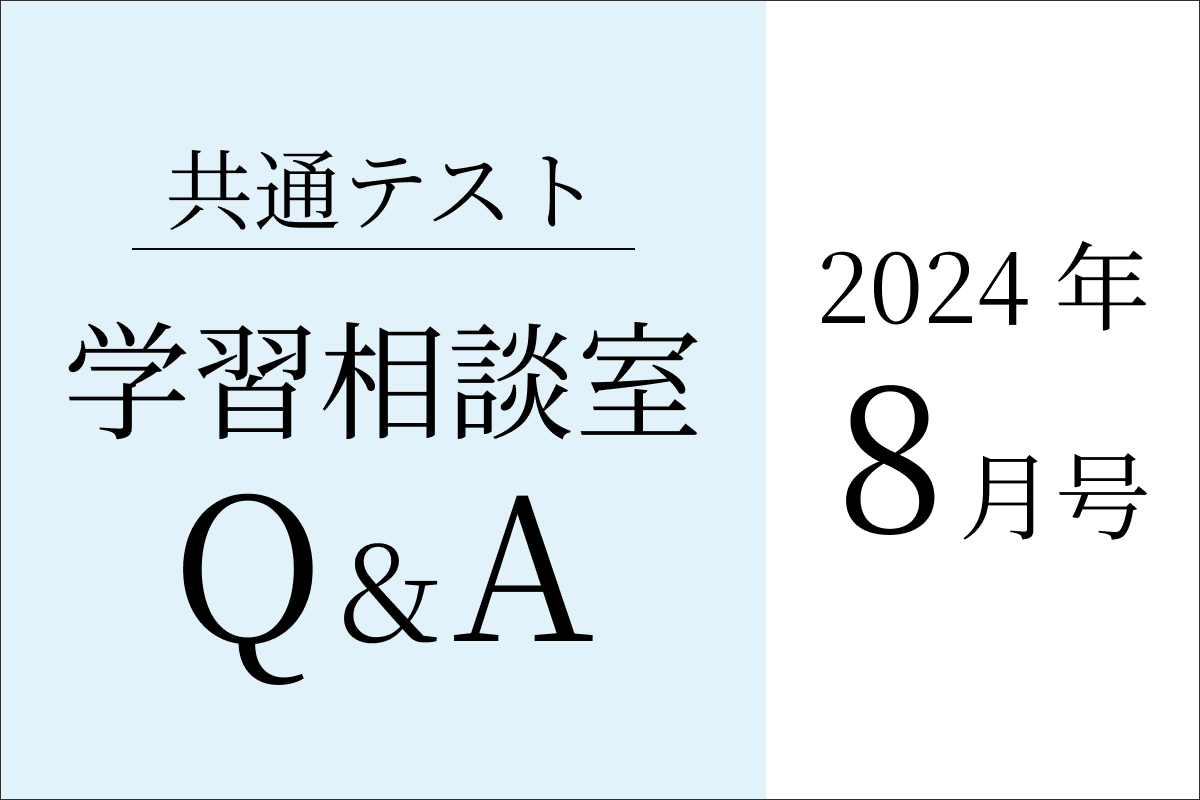
投稿日時:2024年8月8日
今回は「地歴」の学習に関する相談・悩みを、「知識の身につけ方、初見の問題への対応、二次試験も意識した学習スケジュール」についてピックアップしてご紹介します。教科目に項目が分かれての紹介ですが、いずれも地歴全般に当てはまることですので、適宜ご自身の学習科目に置き換えてご参考ください。
日本史:おすすめの暗記方法はありますか?
相談
日本史の学習をする際、通史を1周する頃には最初の方の時代の記憶がかなり抜け落ちていて、ずっと覚え直しになってしまい不安です。このまま忘れる度に覚えるのを繰り返せば定着するようになりますか? 効率の良い暗記法があればご教授いただきたく思います。
【高3、京都大学 志望】
回答

日本史は、暗記量がとても多くて大変ですよね。すでに言及されているように、繰り返すことによって定着していきますので、その点に関してはご安心ください。
とはいえ、私自身も受験生だったときは、漫然と繰り返してもなかなか覚えられず、いろいろな工夫をしました。今回は、私が実践した暗記法の例として紹介しますので、参考にしてみてください。
私は、通史の学習では教科書(や実況中継)と一問一答を主に使っていました。一問一答を繰り返す際に工夫したこと・意識して臨んだことは、2つです。一つ目は、一回一回、その回で全て覚えるつもりで一問一答を解いていくということです。人間の記憶力には限界がありますので、結局、全て覚えることはできないのですが、全て覚えるつもりでいるかどうかで、定着度合いが大きく異なることに気がつきました。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、一回で全て覚えるつもりで取り組む。しかし、忘れてしまうことは仕方がないので繰り返す、という勉強の繰り返しになります。
二つ目は、一問一答の進め方に関する工夫です。多くの人は、教科書等でインプットした後に一問一答を解くことになると思うのですが、一周目は、教科書の章ごとに解く、二周目は、教科書の2章分ずつ解く、さらに三周目は、時代ごとに解くといったように、少しずつ一問一答を解く範囲を広げていきます。このように進めると、少しずつ負荷が大きくなっていくため、勉強しやすいですし、日本史をミクロにも、マクロにも捉えることができるようになっていくため、非常におすすめです。
地理:初見の資料への対応力について
相談
共通テストの地誌、特に表で複数の国を比較する問題を解いて解説を読むと、習っていなかった知識や国の特徴が多く出てきて混乱します。このような問題への力をつけるにはどうすればよいでしょうか。
【高3、東京大学 理科一類 志望】
回答

共通テスト地理の大きな特徴は、問題に必ず資料が使用されていることです。そのため、日頃の学習で身につけた知識と初見の資料を結びつけながら答えを導き出す力が重要となります。9割の得点を取るためには、まず考察の土台となる基礎知識の理解は欠かせません。お使いの参考書や地図帳で学習内容を把握し、太字で示されている重要な語句やロジックをしっかりと理解していくように心がけましょう。夏休みが終わるまでには全範囲の学習を一通り終わらせておくのが望ましいです。
基礎知識を身に付けたら、共通テスト型の問題に積極的に取り組んでいきましょう。共通テストでは、ある程度既存の知識をもとに正解を選べる問題と、ほぼ資料から読み取れることのみから答えを導き出す問題があります。特に後者の問題については、共通テスト独自の形式にどれだけ慣れ親しんできたかによって問題を処理できるスピードが変わってきます。そのため、共通テスト模試やZ会の共通テスト攻略演習への取り組みを通して、初見の資料から必要な情報を素早く読み取る力を鍛えていくことが重要となります。
また、共通テストによく出るデータを大まかに覚えていくようにすると短時間でより自信をもって正解を選べるようになるので、共通テスト型の教材でそういった知識を身に付けていくのがおすすめです。
世界史:共通テストと二次試験の対策スケジュールについて
相談
入試で、共通テストと2次試験の記述問題があるのですが、いつから何をやればいいでしょうか。今は学校の先生に記述問題の添削をしてもらっています。
【高3、筑波大学 人文・文化学群 志望】
回答

入試に向けた世界史の学習については、ひとまず通史の学習と論述対策の2軸で考えることが大切です。秋以降には、加えて共通テスト対策が必要になってきます。現時点で論述問題の添削をしてもらえているのは、かなり早いペースで学習を進めることができていると言えるでしょう。学習スケジュールとしては、秋ごろ(10月〜11月)に通史の学習が終わり、過去問演習や共通テスト対策を本格化させるのが一般的とされています。そのため、まずは通史の学習が終わる時期を確認するようにしましょう。11月中に終わる場合には、無理に先取りを行う必要はありません。すでに通史の学習を終えている場合には、演習中心の学習になりやすいですが、知識や理解の維持のためにも、教科書の読み返しなど復習を怠らないようにしましょう。
第一志望の筑波大の世界史は、400字程度の論述問題が4題出題される形式が定着していますから、受験戦略上、早い時期から論述問題対策に重きを置く方針は正しいです。出題内容もオーソドックスなものが目立つため、入試までにあらゆる問題に触れておくとよいでしょう。
理想としては、9月以降、できれば夏休み中に過去問演習を始めることができるとよいので、夏休みが終わるまでに論述の基礎を身につけましょう。論述対策の問題集に1冊取り組み、基本的な問題は教科書や参考書を見なくても自力で解けるレベルを目指してください。余裕があれば2冊目に取り組んでも問題ありませんが、その時点での他科目の完成具合を見て、どの程度までやり込むか判断するとよいでしょう。
9月以降は、過去問演習を本格化させましょう。引き続き学校の先生に添削をお願いできるようであれば、添削までセットで取り組むようにしましょう。さらに、共通テストの演習も少しずつ比重を上げていき、Z会や各予備校が出している実戦問題集にも取り組み始めましょう。なかなか目標点に届かない場合には、さらに共通テスト寄りの学習にシフトチェンジしても大丈夫です。その中で、定期的に2次の過去問を挟むイメージで問題ありません。共通テストが終われば2次試験の対策に集中できますから、共通テスト1カ月前に目標点に届いていない場合、その時点でほぼ共通テスト対策に振り切ってしまってもよいでしょう。そこまで考えて、入試までの学習スケジュールを立ててみてくださいね。
Z会からのアドバイス
7月までのアドバイスと同じとなります。今の時期は基礎固めを行うことが大切です。
とはいえ基礎を「完璧にする」ことは普通に考えると不可能です。そのため、「できることを増やす」イメージで勉強を進めると良いです。既習範囲をざっと見渡して、弱い分野・項目を見つけ、その弱点克服に時間を費やしつつ、全分野的に問題演習を行うと、全体的なレベルアップを図ることができ、その結果が共通テストにおける高得点につながりますよ。
基礎が固まってきたら、基本的には二次試験を意識した対策を進めましょう。知識習得と同様に時間がかかる論述対策ですね。なお共通テスト形式に慣れるための対策は、(それまでに実力が完成しつつある前提で)直前期に集中して行っても良いのですが、それまでに定期的に過去問や模試での演習をはさんでもよいでしょう。他の科目とのバランスを意識しながら学習スケジュールを調整していってください。
Z会でできる入試対策・ご案内
本番を想定した質の高い演習で得意科目9割突破へ!
![[専科]共通テスト攻略演習(高3生向け)](https://www.zkai.co.jp/kyotsu-test/wp-content/uploads/sites/34/2024/01/24kyotsu_pc.png)
本講座では、9割突破に向けて、毎月着実にレベルアップできるカリキュラムをご用意。
毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!
同じカテゴリの人気記事
共通テスト学習相談室
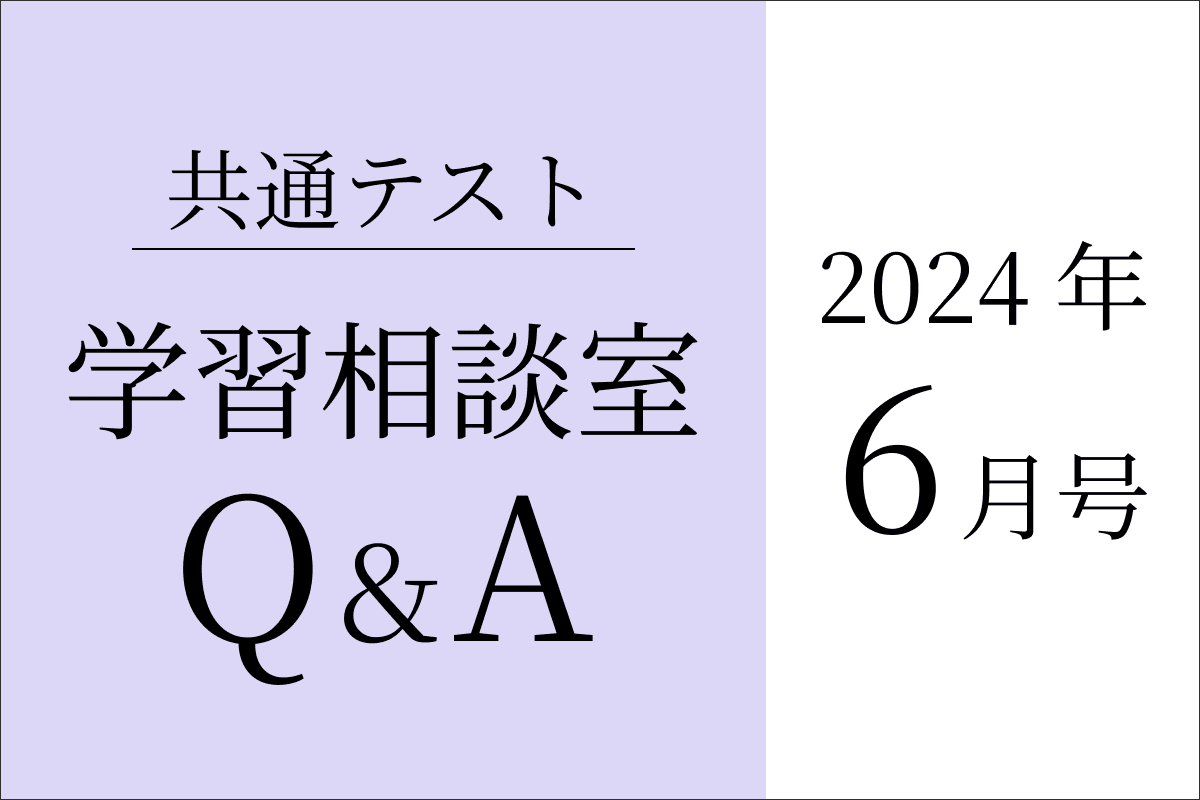
共通テスト学習相談室(2024年6月号)
2025年1月実施の共通テストから「情報」が追加されることが決まっており、皆さんもどのように学習を進めていったらよいのか、気になっていますよね。今回は「情報」についての相談(おすすめ問題集・参考書、学... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む