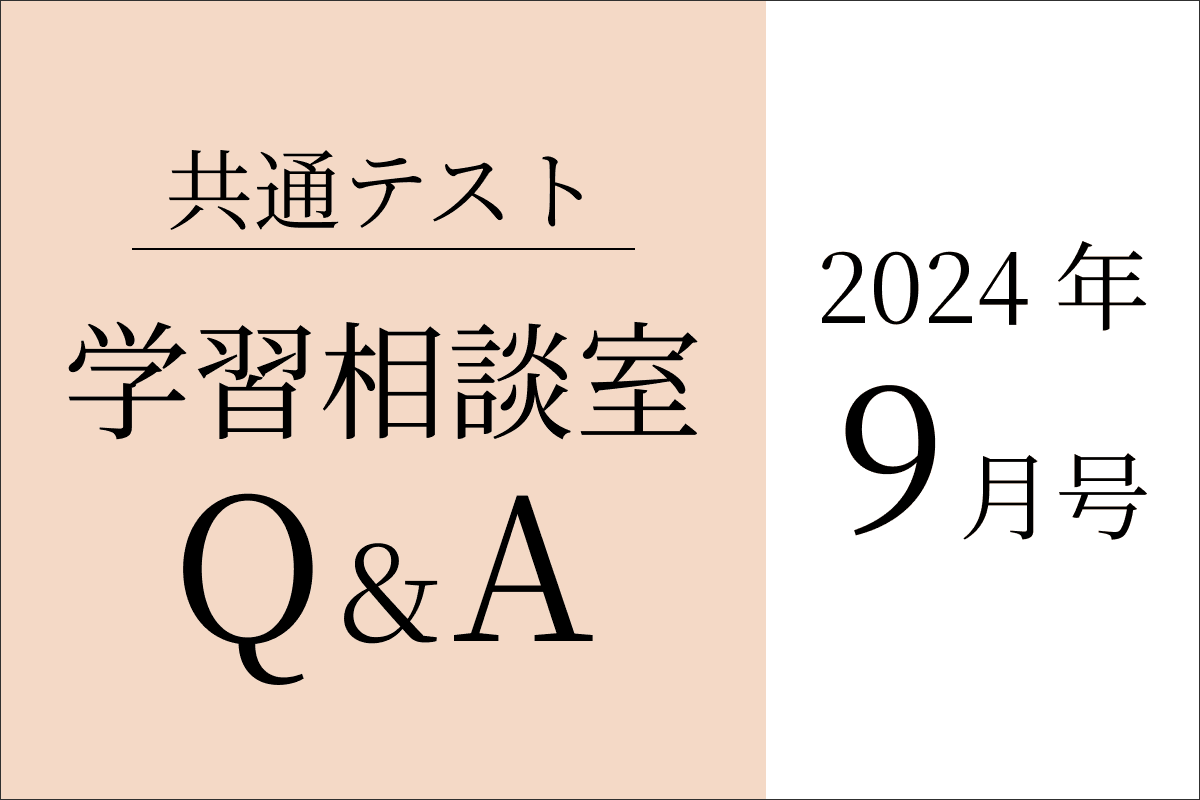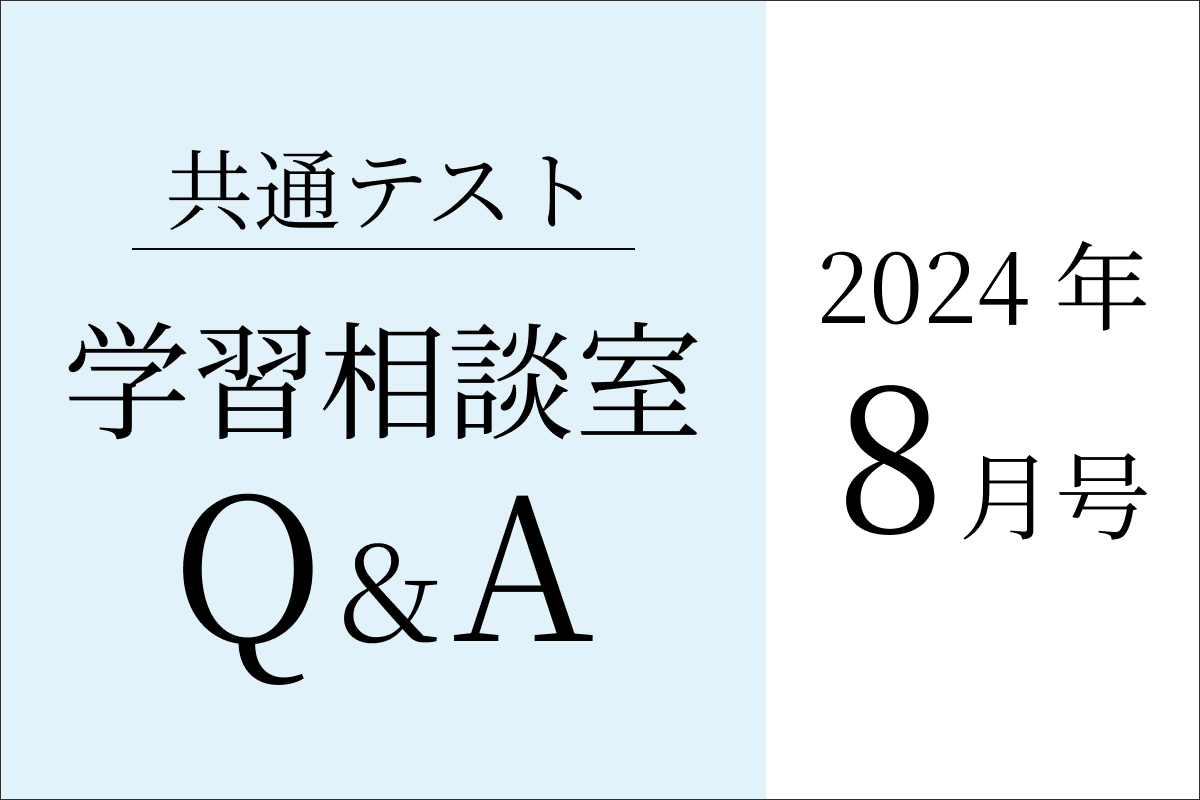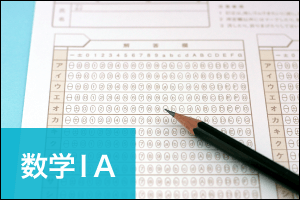共通テスト学習相談室(2024年7月号)
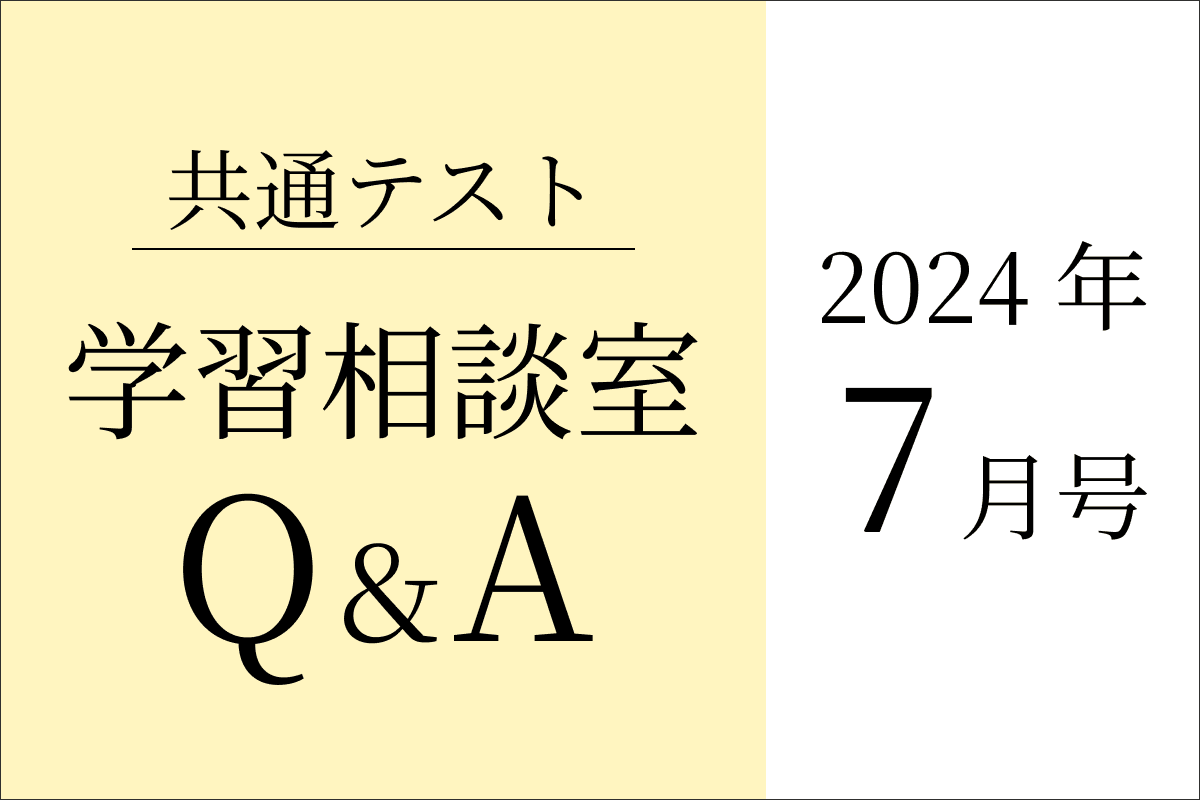
投稿日時:2024年7月8日
今回は「理科」についてピックアップしました。理系受験者は、夏休み期間を有意義に過ごすためにもぜひご確認ください。
- 物理・化学:どんな対策をすればよい?
- 化学:今の時期の学習バランスは?
- 化学:発展問題が解けるようになるには?
- 物理:得点力を伸ばすために意識すべきことは?
- 今月のZ会からのコメント
- <Z会でできる入試対策・ご案内>
物理・化学:どんな対策をすればよい?
受験生の悩み
共通テストの物理と化学はどんな対策をすればいいですか。本番では八割を目指したいです。
【高3、東京工業大学 志望】
Z会がお答えします!

今の時期であれば基礎固めを行うことが大切です。つまり、共通テストに特化した対策というよりは、既習範囲の基本事項をしっかり身に着けることを最優先し、学校で配られた問題集を完璧にしていきましょう。
物理では、教科書に載っている公式をどのように使えば問題が解けるのかを学ぶことが特に大切です。基本的な問題集が問題なく解けるようになったら、入試標準レベルの問題集を使って問題演習をしていき、応用問題の解き方を学んでいきましょう。
化学も、学校指定の問題集がある場合は、まずはそちらを完璧にすることを目指すとよいです。そして、入試標準レベルの問題集を使って問題演習をしていき、化学の問題の解き方を身に着けていきましょう。
物理化学に限った話ではないですが、この時期にしっかりと基礎固めをすることで、共通テストだけでなく二次試験の対策にもなります。秋以降共通テストの過去問などの演習を通して得点力を大きく上げていくことができるので、まずは共通テストを意識しすぎずに各科目の実力を伸ばしていくことを意識していくとよいですよ。
化学:今の時期の学習バランスは?
受験生の悩み
国公立理系志望です。今の時期はなんの教科をやるべきでしょうか?
【高3、横浜国立大学 理工学部 志望】
Z会がお答えします!

今の時期は、二次試験で使用する教科の学習を中心にバランスよく行うのがおすすめです。横国大志望ということで、二次試験では英語・数学・理科(物理・化学)が課されますから、これらの学習をバランスよく行いましょう。
学習にあてられる時間を英語・数学・理科で3等分して、これまでの学習の進捗や得意・不得意に応じて学習時間を調整すると良いでしょう。多くの現役生は理科の演習が足りていない傾向にあるため、英語の時間を少し削ってその分を理科にあてる、などとするとよい場合があります。ご自身の学習状況を振り返り、これからの学習方針を立てるようにしてください。
共通テストでしか使わない教科の学習は、今の時期はそれほど力を入れて取り組まなくても構いません。二次試験でも課される教科は、二次試験対策が共通テスト対策を兼ねます。二次試験で課されない教科・科目については、隙間時間や息抜きに知識の復習や簡単な問題演習(大問1つ分など)を進めると良いです。共通テストの割合は、夏から秋以降に徐々に増やしていきましょう。
化学:発展問題が解けるようになるには?
受験生の悩み
共通テストで化学を8〜9割取りたいと思っています。いまセミナー化学の理論化学をやっていて、発展問題が全然わからないのですがどうすればいいでしょうか?
【高3、徳島大学 志望】
Z会がお答えします!

理論問題の発展問題は、解き方をマスターしていないと解けない問題が多くあります。つまり、初見でスラスラ解けるかどうかよりも、問題を解くことを通じてその解き方をマスターしていくことが想定されています。ですから、わからない問題が多いからと言って焦ることはありませんよ。最初は解説を見ながらでよいので、解き方のパターンを習得していきましょう。解説を見て解き方を覚えるだけでなく、どうしてこういう式になるのかということを教科書などで原理を確認しながら理解していくとよいですよ。このようにパターンを習得していくと、化学は解き方のパターンが大体決まっているので解ける問題も増えてきますよ。
物理:得点力を伸ばすために意識すべきことは?
受験生の悩み
受験では共通テスト・2次試験どちらも物理を受験します。そのために問題演習を繰り返して解法を理解するだけでなく講義系の参考書を使用して性質の理解などにも努めています。しかし、テストや模試になると問題が解けなくなったり、解けても計算ミスや力の向きが逆であったりしていつも点数が取れません。どのようにして勉強を進めることがより効率的でしょうか。また、試験中はどのようなことを意識するべきですか。
【高3、金沢大学・医薬保健学域 志望】
Z会がお答えします!

テストや模試での得点を伸ばしたい場合は、結果の分析とそれに応じた対策を講じるのが一番効果的です。例えば、計算ミスであれば、採点された答案を振り返り、自分がどのような部分・計算でミスをしているのかを考えます。ノートにそれを書き溜めていくと、ミスの傾向が見えてくるはずですので、該当部分を集中的に見直すようにすると良いです。使用できる文字に気をつけたり、特定の四則演算は必ず検算するようにしたりと、見直しのマイルールを定めましょう。
普段解けているような問題が試験本番で解けなくなる、という場合は、その部分の理解が浅い可能性があります。もう一度教科書や問題集を見直し・解き直しし、模試の問題も繰り返し解くと良いです。模試やテストを受けるごとにその時点での課題を確認・克服し、また次の模試やテストに臨む、というサイクルを繰り返すと、点数が徐々に上がっていきますよ。
試験中に意識することとしては、時間配分や問題の取捨選択が挙げられます。一つの難しい問題にこだわるよりも、なるべく簡単に解ける問題を多く解いた方が合計点数を最大化できます。大問ごとに10分、20分などと制限時間を決めてそれをきちんと守ったり、問題を解き始める前に全ページを見渡し、簡単に解けそうなものから解き始めたりと、臨機応変に対応できるようになることが大切です。普段の演習では、取り組む問題一つ一つを丁寧に身につけていくことが大切ですが、過去問に時間を計って取り組む際は、このような試験本番でのイメージトレーニングも兼ねると良いです。
Z会からのアドバイス
今の時期は共テ型の出題や二次試験の応用問題対策から始めるよりも、基礎固めを行うことが大切です。そもそもの土台が固まっていない状態で取り組んでも、基礎があやふやな部分を洗い出すという使い方以外の結果としては、基礎学力の不足で得点が伸び悩むことになると思われます。英数国などの科目も同様ですが、夏休み中までには、苦手な単元があれば克服に時間を投じたり、理解がおぼつかない点があれば基本事項からしっかり身に着けたりすることを最優先しましょう。教科書や学校で配られた問題集を完璧にしておけば、秋以降の共通テスト型の実戦的な演習に多くの時間を避けられるようになるはずです。
Z会でできる入試対策・ご案内
本番を想定した質の高い演習で得意科目9割突破へ!
![[専科]共通テスト攻略演習(高3生向け)](https://www.zkai.co.jp/kyotsu-test/wp-content/uploads/sites/34/2024/01/24kyotsu_pc.png)
本講座では、9割突破に向けて、毎月着実にレベルアップできるカリキュラムをご用意。
毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!
同じカテゴリの人気記事
共通テスト学習相談室
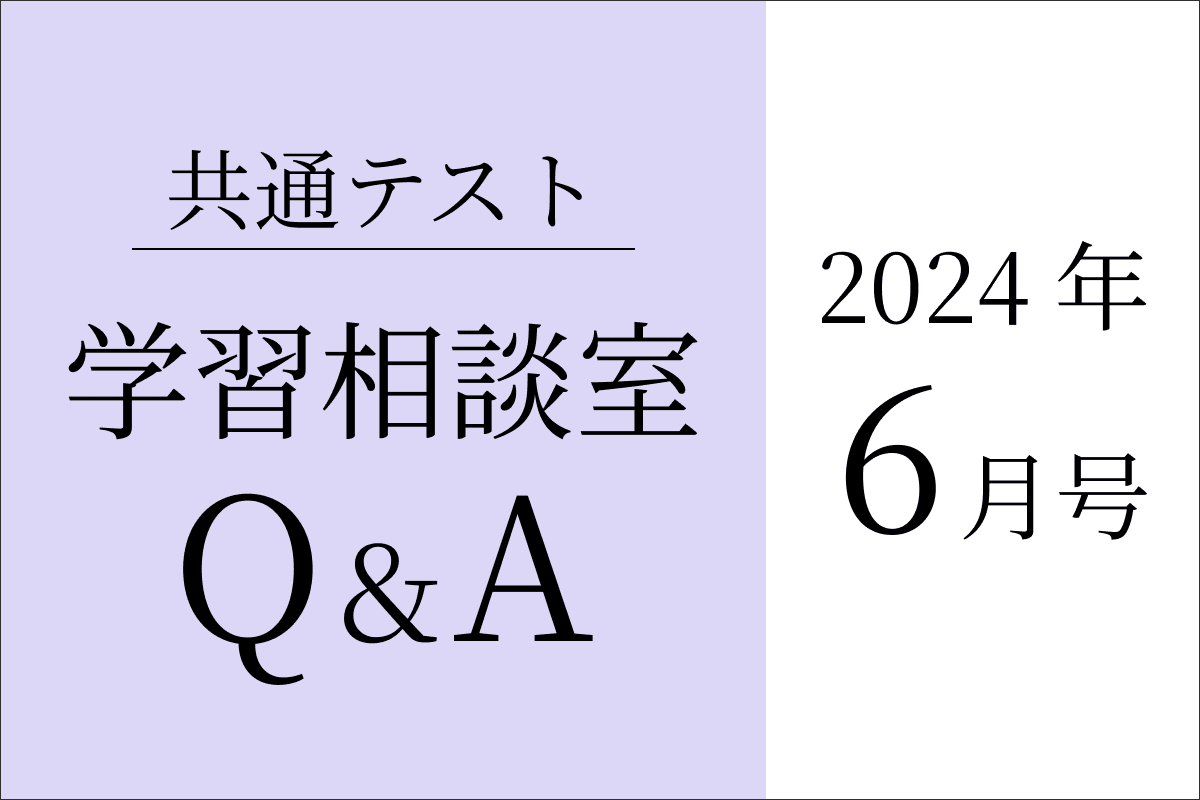
共通テスト学習相談室(2024年6月号)
2025年1月実施の共通テストから「情報」が追加されることが決まっており、皆さんもどのように学習を進めていったらよいのか、気になっていますよね。今回は「情報」についての相談(おすすめ問題集・参考書、学... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む