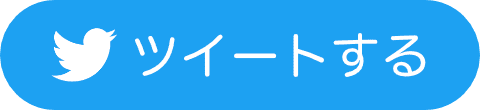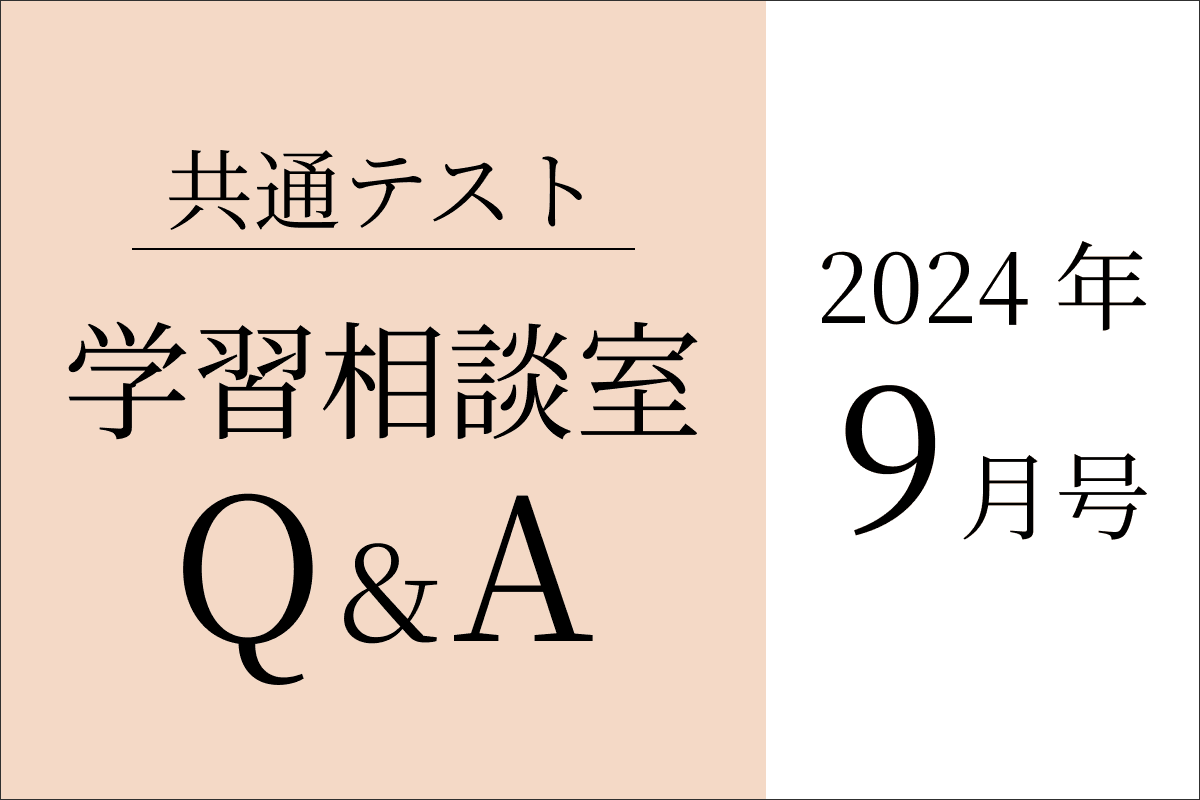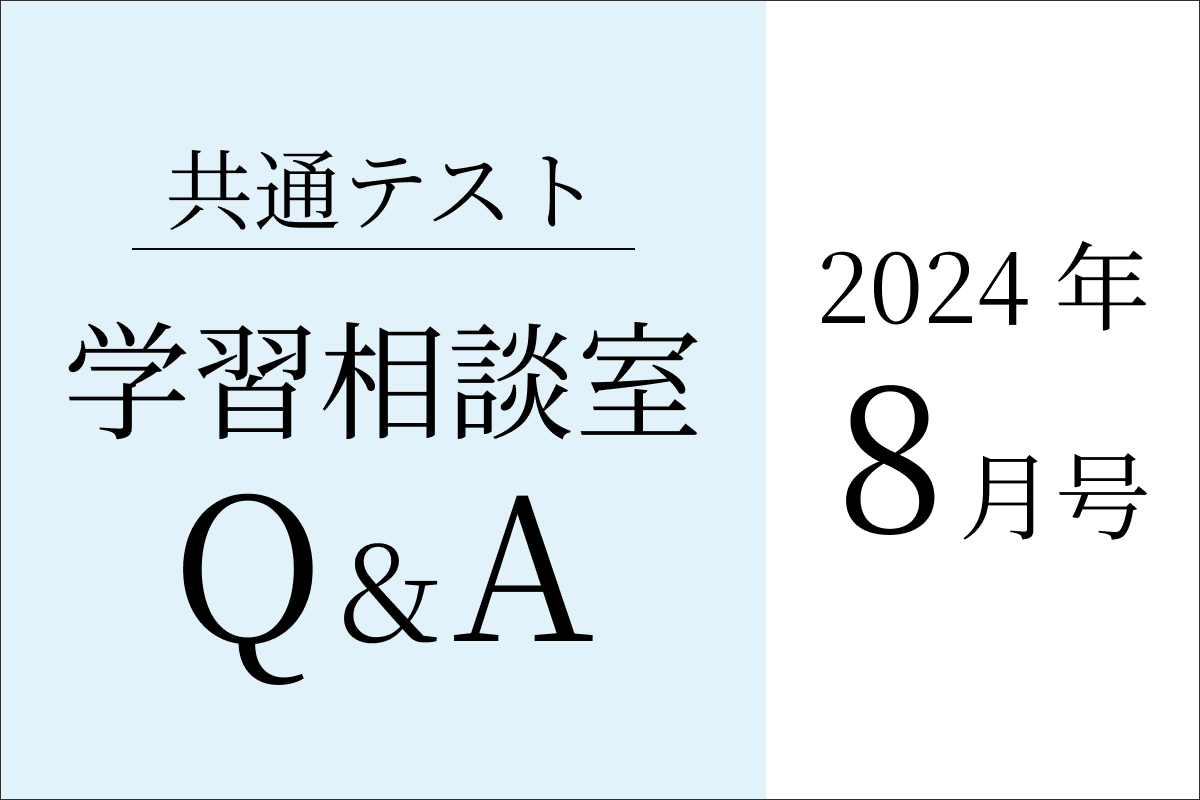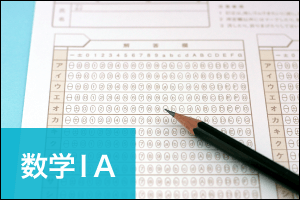共通テスト学習相談室(2023年7月号)
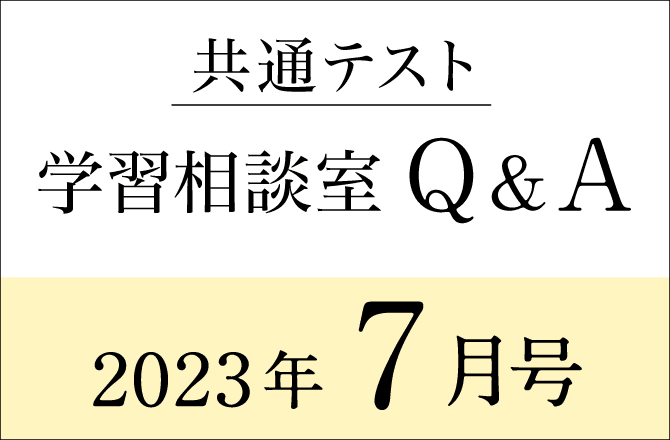
投稿日時:2023年7月24日
「教えてZ会!」(Z会員の質問相談窓口)に寄せられた質問の中から、共通テストに関するものをピックアップ。今回は前月に引き続き模試に関する質問を紹介します。入試のプロであるZ会の高校学習支援担当のアドバイスを、ぜひ参考にしてください!
模試のたびに結果の波が大きい。安定させるには?
受験生の悩み
共通テスト模試の結果に関して、事前にしっかり対策をすれば8割程はとれるところ、対策が足りないと6割程になってしまいます。
このままでは不安です。
【高3、京都大学 理学部 志望】
Z会がお答えします!

対策の進み具合によって得点に波があるとのことですが、今はまだ各分野の知識理解が完全には身についていない時期でしょう。また共通テスト形式の演習自体も完璧ではないでしょうから、結果に波が生じてしまうのはよくあることです。演習を通じて、安定して得点できるよう仕上げていきましょう。
対策として、まずは点数がブレてしまう理由を自分で分析しましょう。直前に対策したか否かだけではなく、分野ごとの定着度の差なども影響している可能性が高いです。今まで受けてきた模試や、解いているのなら過去問を見直してみてください。分析したら、波を小さくするための具体的な対策(苦手分野の克服や各分野の定着度の向上)を立てて実行し、次の模試に挑みましょう。そして模試の結果を踏まえて、また計画を立て直すというサイクルを繰り返しましょう。これは二次試験対策にも共通しますから、今後勉強を進める際にも意識してください。
英語:模試で得意科目が惨敗…理由を明らかにして、出来る対策を進めたい。
受験生の悩み
駿台の共通テスト模試を受け、ほぼ惨敗でした。
英語に力を入れていると謳っている学校に通っており、Z会の添削問題でも点数を取れていたので、共通テストの形式にまだ慣れていないとはいえ3割ほどしか得点できなかった事には正直落ち込みました。 今年度の共通テストは難化するとの噂を聞きますが、難化したとしても英語は8~9割ほど取りたいです。
【高3、京都大学 文学部 志望】
Z会がお答えします!

まず、高3の5月の時点で本番の目標点に到達しておかなければならないということは全くないので、今回の結果を気にしすぎないようにしましょう。むしろ現状と本番までの差を知る良い機会だと思い、今後の学習に活用していくのが良いです。
英語の対策としては、現状の点数を踏まえ「得点の伸びしろ」を分析することが重要です。自分が間違えた理由や原因について解答解説を確認しながら丁寧に分析していきましょう。原因の例としては、文法知識や覚えている単語量の不足などが挙げられます。この場合は文法書や単語帳の復習をおこなうことが必要です。他には長文形式の問題演習量が不足していることも考えられます。ご相談の中にも形式に慣れるという話がありますが、共通テストはセンター試験と異なり、出題形式が特殊という点が挙げられます。他にも文章量に対し時間が短いという制限もあります。こういった形式は演習量を増やして慣れることが重要です。文法面の復習と演習を並行しておこない、得点力を上げていきましょう。共通テスト英語は、配点の高い問題を少し失点するだけで点数が大きく下がる科目です。配点なども気にしつつ、現実的な対策をおこなっていく意識が重要です。
通われている高校が英語に力を入れているとのことですね。そういった場合、高校では入試の枠にとらわれない実践的な英語を重視していることが多く、学校の英語プログラムと入試対策は分けて考えて、双方丁寧に学習をした方がいいこともあります(どちらが良いか、ということではありません)。
共通テストの難易度については、来年難化するというよりは、今年(2023年実施)くらいの難易度が基準となってくると考えるのが良いです。共通テスト自体、始まって4年目の試験ですので、難易度の基準を調整している時期といえます。易化、難化(のうわさ)に気を取られず、現状取り組める過去問を基準に対策をおこなっていきましょう。
文系教科の対策・進め方について
受験生の悩み
共通テストの文系教科の対策をどのようなペースで進めたら良いのかわかりません。
模試の結果からは不安定さや伸び悩みが見られるので、月1程度で各教科の共通テスト対策をした方が良いのかと迷っていますが、理系教科の勉強や2次対策で手いっぱいで正直余裕がないです。 いつから・どれくらい・どのように対策していくのが望ましいでしょうか。
【高3、京都大学 農学部 志望】
Z会がお答えします!

結論から言うと、二次試験で使う科目は二次試験対策を優先させ、二次試験で使わない科目(地理や漢文)は、今から基本事項の復習を計画的に進めていくという方針がよいです。
地理や漢文は、直前になって知識を詰め込もうとすると、十分な演習に取り組めない可能性もあり、また、二次試験対策の時間を圧迫してしまうことにもなりかねないので、今から始めることをおすすめします。そのための時間枠を確保するのが難しければ、すきま時間にコツコツと取り組んでいきましょう。理系科目の演習で頭が疲れたときに地理や漢文に取り組むと、気分転換にもなります。逆に、二次試験で使う科目については二次試験対策をしていく中で力をつけていくことができ、共通テスト直前の演習で対応できる可能性が高いので、現時点では心配しすぎる必要はないでしょう。
二次試験対策で手いっぱいで共通テスト対策にあまり時間を割きたくないという気持ちは分かりますが、優先順位をつけて、今始められることから始めていきましょう。
無意識にしてしまう初歩的なミスを減らすには?
受験生の悩み
知識の抜け漏れというよりは、無意識にこなすなかでの単純な初歩的ミスをしてしまいます(数学で三角形の面積を出すにも関わらず、1/2をし忘れる、地理の時差の計算でサマータイムの時間を考慮し忘れる…など)。
普段から本番を意識して時間を計って解くことなどが重要だと思っていますが、それ以外にも有効な対策として考えられることがあれば教えてください。
【高3、京都大学 医学部 志望】
Z会がお答えします!

無意識にこなしてしまう過程でのミスを減らすのは、なかなか難しいですよね。いくつか対策法を紹介するので、ぜひ試してみてください。
まず、自分でどのようなミスをしてしまう傾向にあるのかを把握することは大切です。相談文にも書いてくれていますが、「このようなミスをしてしまう」ということを自覚するだけで、次からそこに意識を向けることができますよね。それから、なるべく余裕のあるスペースで計算を進めるのも重要です。計算過程が見やすいと計算過程を俯瞰することでミスに気が付きやすくなります。共通テストでは余白が決して多くはなく、余裕のあるスペースを確保することが難しいかもしれませんが、解答スペースを工夫しながら答案を作成することも、大事な戦略の1つです。
また、共通テストという形式に慣れることも大事です。現段階で完璧に慣れていましょうというのは無理な注文だと思いますが、まだ経験不足で形式に気をとられている部分があるのではないでしょうか。形式に気を取られると、いつもなら当たり前にこなしている計算や簡単な処理に抜け漏れが生じやすくなるでしょう。この点は、今後、共通テスト形式の問題に取り組んでいく中で改善されていくはずです。
Z会からのアドバイス
夏に共通テスト模試を受験する人は多いと思われますので、受験前に考えておく戦略についてお伝えします。
すでに1度は共通テスト模試を受験した人が大半だと思いますが、共通テスト型の問題の難しさは分析できているでしょうか?科目別にざっくり判断すると、
- 英語・数学・国語:試験時間に比しての問題文量が多く、時間内にすべての問題に取り組むこと自体が難しい。
- その他の科目:現役生は対策が間に合ってないことから、そもそも解けない問題がある。
という感じになるかと思われます。この傾向を踏まえて、夏の模試では、
- 英語・数学・国語:時間配分を意識して取り組む
- その他の科目:事前にできるだけ対策し解ける問題を増やす
という感じで、事前準備、および試験中の戦術を考えた上で受験を行ってください。そうすることが、結果の正しい分析につながります。
※2022年7月コメントの再掲となります。昨年の相談回答内容 ![]() もぜひご参考ください。
もぜひご参考ください。
(Z会高校学習支援担当 山邊圭祐)
Z会でできる大学受験対策
◆[専科]共通テスト攻略演習(高3生向け)
共通テストの傾向をふまえた教材に取り組みます。毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。共通テスト型の問題に慣れ、得意科目9割突破を狙いましょう。
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をTwitterでシェアしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!
同じカテゴリの人気記事
共通テスト学習相談室
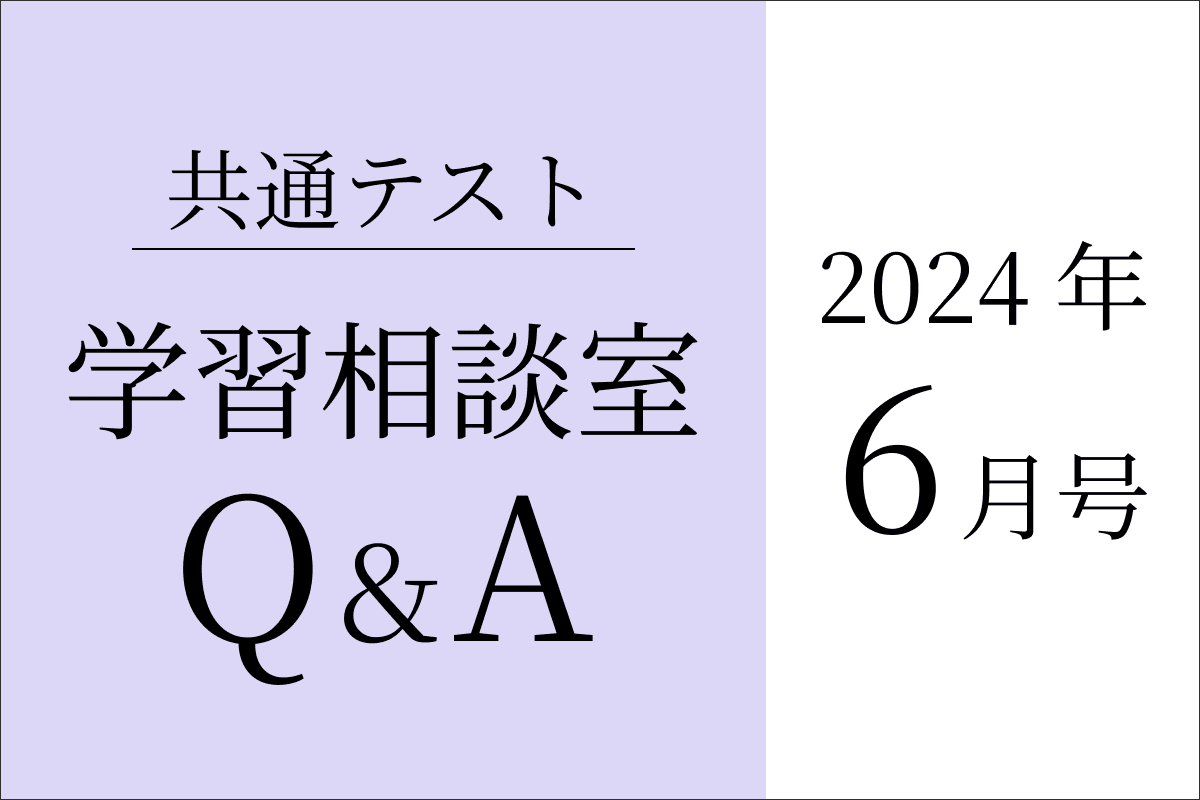
共通テスト学習相談室(2024年6月号)
2025年1月実施の共通テストから「情報」が追加されることが決まっており、皆さんもどのように学習を進めていったらよいのか、気になっていますよね。今回は「情報」についての相談(おすすめ問題集・参考書、学... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む