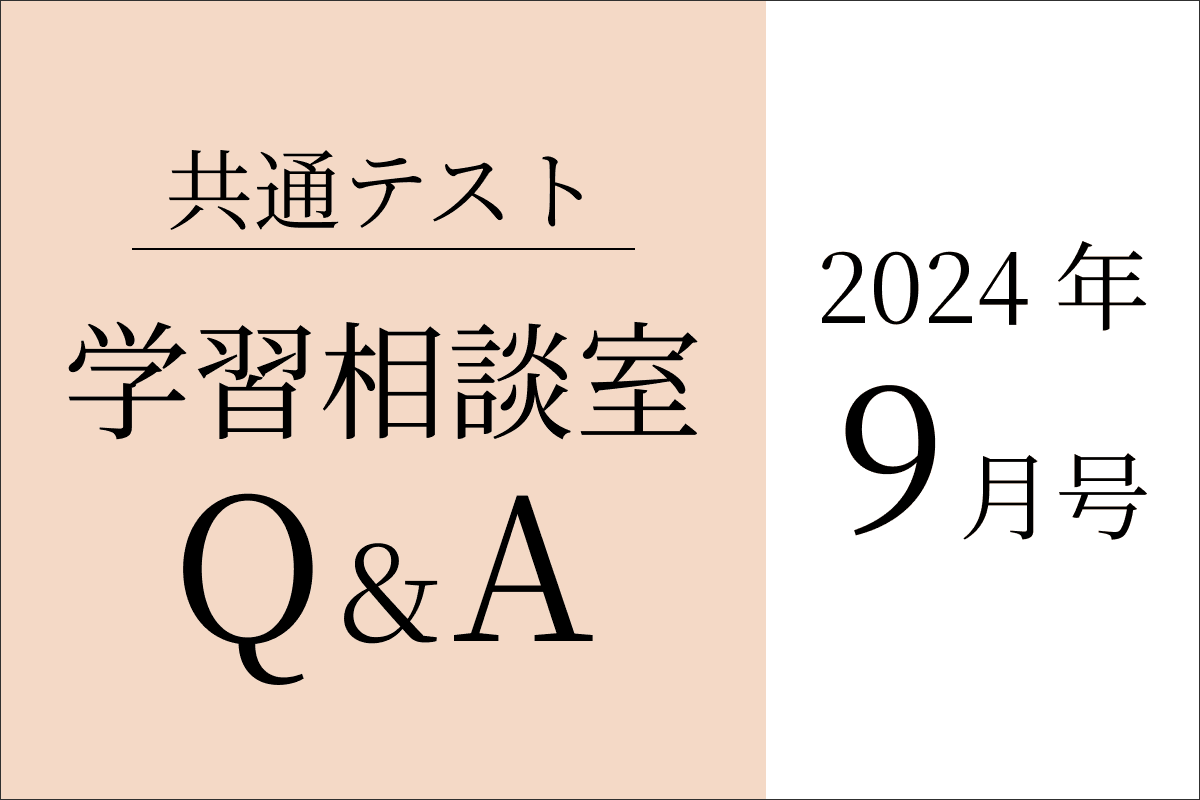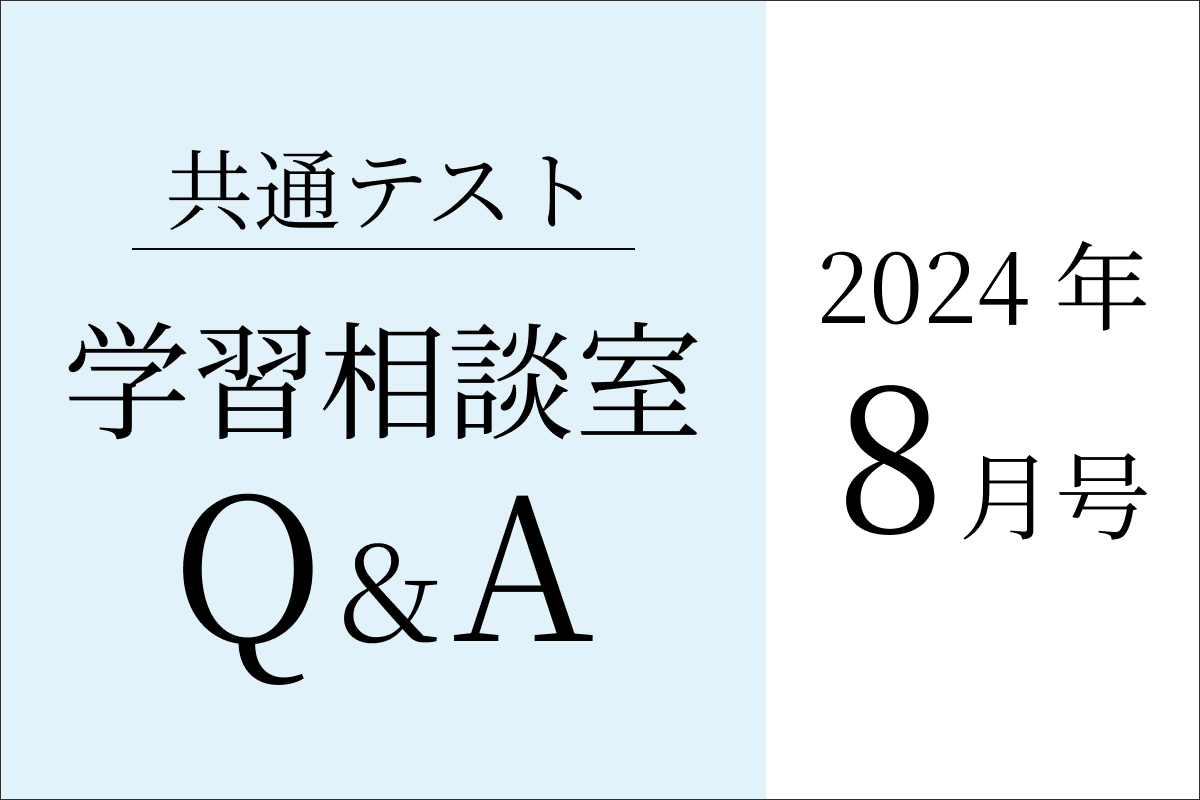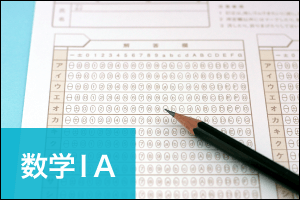共通テスト学習相談室(2024年5月号)
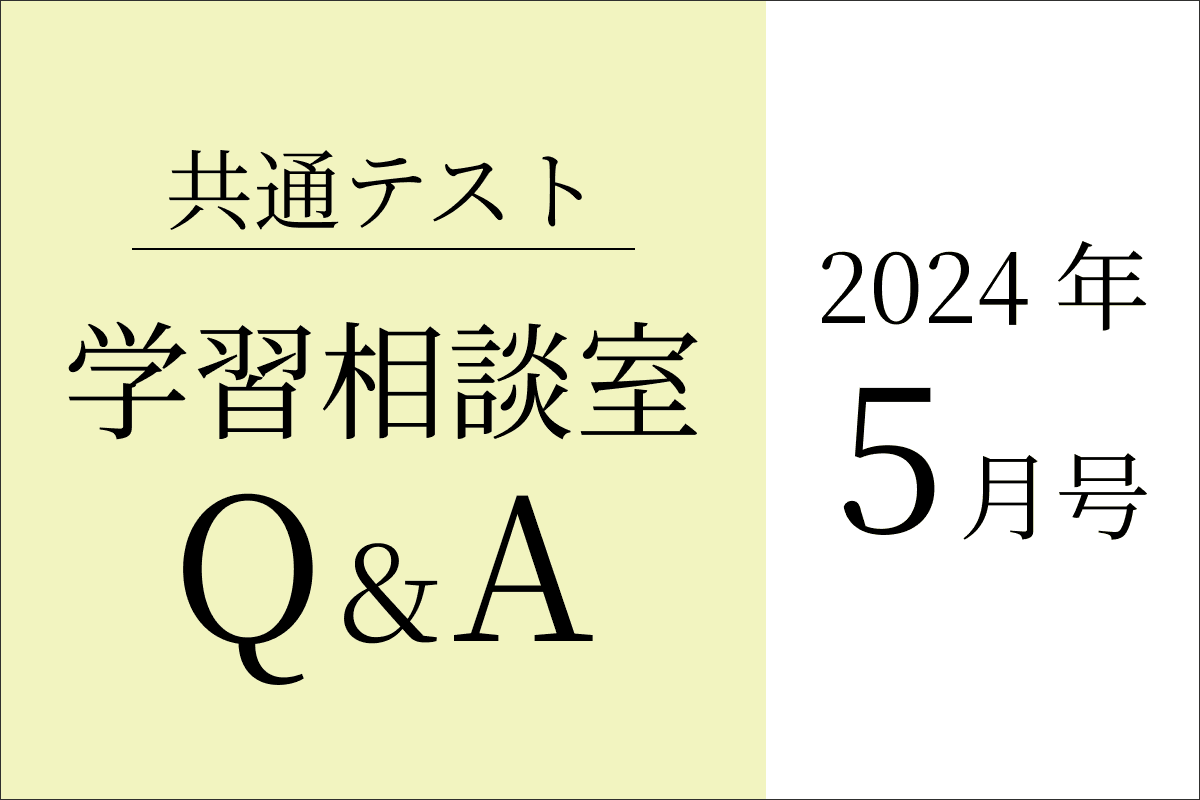
投稿日時:2024年5月6日
この時期に多かった共通テストの学習に関する相談・悩みを、過去に公開した相談と回答からピックアップしました。きっと皆さんが気になっていることと思います、ぜひ参考にしてください!
- 英語:時間内に解き終わるためには、どのような対策が効果的ですか?
- 英語:共通テスト形式のリスニングは、どのように対策したらいいですか?
- 数学:学力が足りない、計算が遅い。対策を教えてください。
- 国語:現代文の対策について
- 今月のZ会からのコメント
- <Z会でできる入試対策・ご案内>
英語:時間内に解き終わるためには、どのような対策が効果的ですか?
受験生の悩み
「英語リーディング」の解答時間が足りず、全ての設問を解けないことに困っています。
速読力などが不足している点が原因だと感じていますが、大問を読む順番についても様々な情報が耳に入り、何がベストなのかわかりません。模試などでいくつかの方法を試してみましたが、結局時間内に解き終わることには繋がらなかったので、どれが効果的だったのかいまいち分かりませんでした。
【高3、東北大学 法学部 志望】
Z会がお答えします!

大問を読む順番については、解きやすいように進めていただければ良いです。全設問を時間内に解くために必要なのは、速読力だけではなく読解力を伸ばすことです(読解力があがると、その分スムーズに設問に取り組めるというわけです)。
読解力向上のための学習方針が決まっていらっしゃる場合、それを貫いていただければ大丈夫ですが、悩んでいたりはっきり固まっていない場合の参考に、以下では読解力を伸ばすための道筋を提示しておきます。
読解力が伸びない原因としては、「①英文の構造が把握できていない」「②英文読解の経験値が浅い」「③語彙力が万全でない」の3つが考えられます。
①:英文の構造が把握できていないとは、英文法の知識を、文章の意味を理解するために必要な知識に変換できていない、ということです。ただ文法問題が解けるだけの知識では、読解には使えません。読解ができるようになるためには、まず英語を英語のまま理解できるようになる必要があります。主語がどこからどこまでか、どこまでが関係節で何を修飾しているのか、こういったことを見抜けるように、構文解釈のトレーニングを行ってください。
②:単に英文読解演習の経験が浅いことも考えられます。こちらについては、ぜひZ会の共通テスト予想問題などに取り組み、その復習を時間をかけてしっかりと行なってみてください。解説をじっくり読んで、読み方・解き方を習得することで、ただ闇雲にたくさんの問題を解くよりも学習効果が高くなります。
③:語彙力が万全でないという原因も考えられます。標準的な語彙については、少しでも記憶が曖昧だと英文全体の読解に支障をきたします。ですので、『速読英単語 必修編』などの標準的な単語集を何度も繰り返して標準的な語彙を完璧にしていきましょう。
繰り返しになりますが、共通テストのリーディングにおいて解く順番はさほど重要ではありません。問題全体の傾向としては、前半の方が難易度は低いことが多いため、前から順番に解いていく形でかまいません。もちろん、演習を積む中で自分のやりやすい順番で解いていけば良いのですが、今回のように時間内に解き終わらないことが悩みである場合は、まずは読解力をどう向上させるかを検討することがポイントです。
英語:共通テスト形式のリスニングは、どのように対策したらいいですか?
受験生の悩み
私は自分の中では結構英語が得意なつもりなのですが、共通テスト形式のリスニングではいつもミスが目立ちます。どのように対策したらよいでしょうか?
【高3、京都大学 農学部 志望】
Z会がお答えします!

まずは基本的なリスニング対策を行いましょう。具体的には、問題を解いた後、間違えた部分について間違えた原因(知らない単語が出てきたため、発音がわからない単語が出てきたため、など)と、原因に合わせた対策(単語帳を確認する、単語を何度か発音してみる、など)を考えましょう。その後、音声を聞きながらスクリプトと和訳を確認し、音声と同じスピードでスクリプトを読めるようになるまで何度も音読をしましょう。余裕があればシャドーイングまで行えるとよいでしょう。また、下読みの時間が短い、選択肢が紛らわしいなどの共通テスト特有の問題形式に慣れるため、定期的に共通テスト形式のリスニング問題を解くのもおすすめです。
数学:学力が足りない、計算が遅い。対策を教えてください。
受験生の悩み
根本的な学力が足りない、計算のスピードが遅いことが弱みなので、対策として教科書傍用問題集に取り組もうと思っています。
計算力を上げるために基礎的な問題集に戻る選択肢はありでしょうか?
【高3、京都大学 農学部 志望】
Z会がお答えします!

数学の実力の判定を共通テスト模試のみに頼ると、正しく測れていない可能性がありますので、注意が必要です。共通テストはあの形式の問題を試験時間内に処理することが難しい試験であり、低得点がすなわち数学の学力が足りていないという結論にはつながりません。
上記のような事情がありますので、もう一度同じ問題に時間無制限で取り組み、今の実力で解けない問題がないかを確認してください。時間無制限であれば全ての問題に着手でき、ほぼ正解できるという状態にあるならば、計算スピードを意識しつつも、より難度の高い、京大入試に近い問題での演習を続ければ良いと思います。逆に解けない問題があるなら、教科書傍用問題集を用いてその分野の基本事項を復習し、入試問題を解くことができるように理解を深めておくことが重要です。
入試までの時間は限られますので、計算スピードを上げるというような単発の問題解決のための対策を行うのではなく、計算スピード「も」上げる、という形で、他の対策の中に課題を組み込む視点が必要ですよ。
国語:現代文の対策について
受験生の悩み
現代文は数学とは違い公式などがないので、どのように学習を進めていけばいいのかがわかりません。
例えば読む速度を速くするとか、ディスコースマーカーは印をつけるなど、具体的にどのようなことを意識して勉強をしていけばいいのか知りたいです。
【高3、慶應義塾大学 理工学部 志望】
Z会がお答えします!

おっしゃる通り現代文の読み方には明確な公式などはありません。とはいえ、挙げてくださったようにディスコースマーカーを意識して読むことなど、現代文を解くうえでの「コツ」や定石はある程度ありますから、それらを身につけながら演習を重ねていきましょう。
現代文を読むうえで何より重要なのは、「本文に忠実に読むこと」です。文中にあることのみを根拠に答えることが鉄則ですから、先入観やご自身の経験などは極力加えずに、本文から読み取れる限りで答えることを意識してください。なかには独自の観点から書かれた文章もありますから、「自分だったらこう考える」「常識的に言えばこう」など、本文以外を根拠に解くことは禁物です。共通テストでは、常識的な(本文の論旨と異なる)選択肢へ誘導する「ひっかけ」選択肢も多くありますから、選択肢を吟味する際も本文とこの点が異なるから誤答、など必ず本文から根拠を探し出してくださいね。
なお、これらの現代文の解き方についてまとめた参考書として、「現代文の解法 読める!解ける!ルール36」(Z会)はおすすめです。基礎から丁寧に論理立った「解法」を身につけられる参考書ですから、もしよろしければ書店などで探してみてください。また、意外と知らない単語や表現に引っかかって思うように読めないことも多いです。英語や古文もふくめ、理解が曖昧な表現にあたったら、必ず辞書を引いて意味を確認するようにしましょう。
Z会からのアドバイス
共通テストの対策をどう進めるかについて、悩む人が増えているようです。
共通テストも個別試験も、高校の教科書内容を基に出題される試験ですから、両者の対策の大半は共通となるはずですよね。
両者の試験の形式、つまりアウトプットの部分が、客観式(マーク式)なのか、記述式メインなのかの違いでしかなく、解答に至るまでに必要な知識・技能、思考力等は、両者で区別されるものではありません。
そのため、今の時期は、入試に必要な科目の基礎を固めることを念頭に対策を進めつつ、自身の対策の方向性が正しいかどうかを、共通テストや個別試験の過去問への取り組み、あるいは模試の受験によって、適宜確認していく形で問題はありません。
共通テストのみで必要となる科目については、週1日、しかも短時間でよいので曜日を決めて取り組み、対策を継続しましょう。
Z会の『共通テスト攻略演習』を受講されている方は、該当科目のものに取り組み、答え合わせまでを1日で完了させ、そこで見つかった弱点を、翌週に復習する形で進めると良いと思います。
なお、共通テストのみで必要となる科目は、最低でも2科目は存在するはずですので、「1周目に演習、2週目に復習」と考えると、2科目で1カ月を費やすことになります。
1日に2科目取り組む、あるいは週に2日対策の時間を設けるなど、柔軟な対応が必要になりますので、ご自身の入試科目を考慮しつつ、無理のない学習計画を立て、コンスタントに対策を進めていってくださいね。
Z会でできる入試対策・ご案内
本番を想定した質の高い演習で得意科目9割突破へ!
![[専科]共通テスト攻略演習(高3生向け)](https://www.zkai.co.jp/kyotsu-test/wp-content/uploads/sites/34/2024/12/2025kyoututest_kv.png)
本講座では、9割突破に向けて、毎月着実にレベルアップできるカリキュラムをご用意。
毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
本記事を読んでいただきありがとうございます。記事をX(旧Twitter)でポストしてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします!
同じカテゴリの人気記事
共通テスト学習相談室
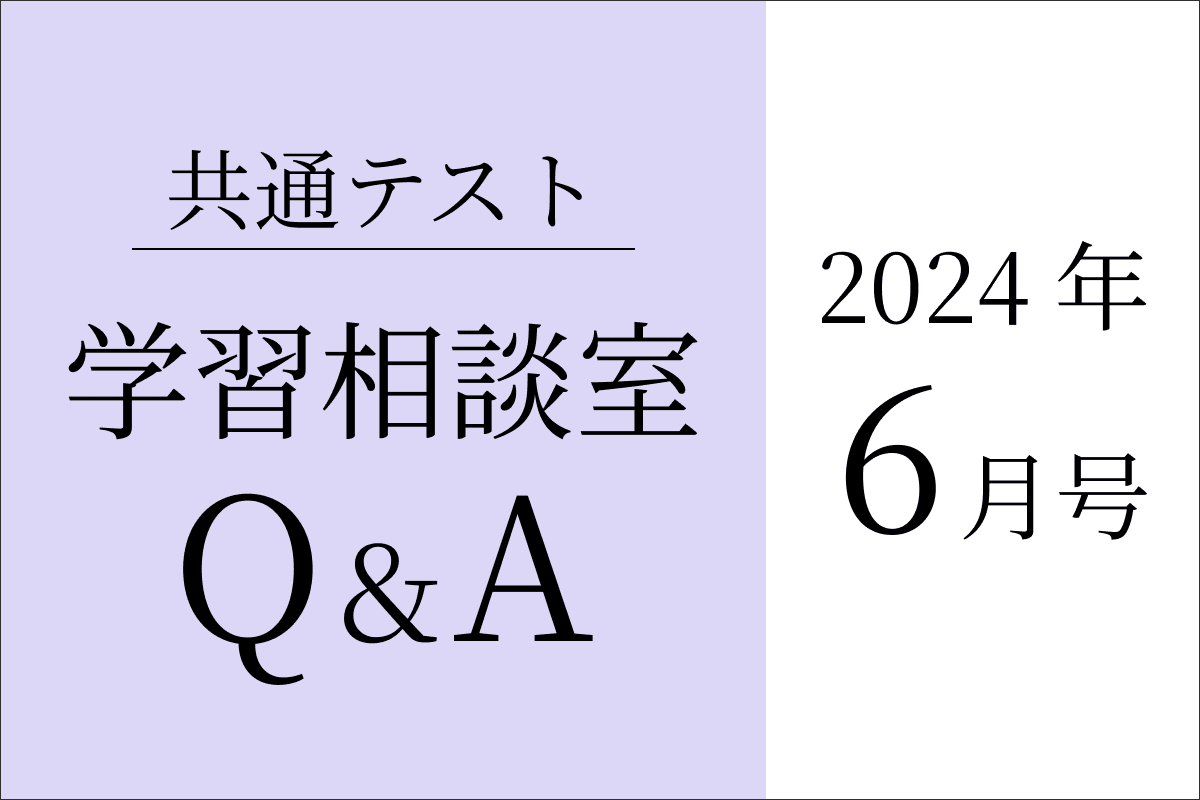
共通テスト学習相談室(2024年6月号)
2025年1月実施の共通テストから「情報」が追加されることが決まっており、皆さんもどのように学習を進めていったらよいのか、気になっていますよね。今回は「情報」についての相談(おすすめ問題集・参考書、学... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む