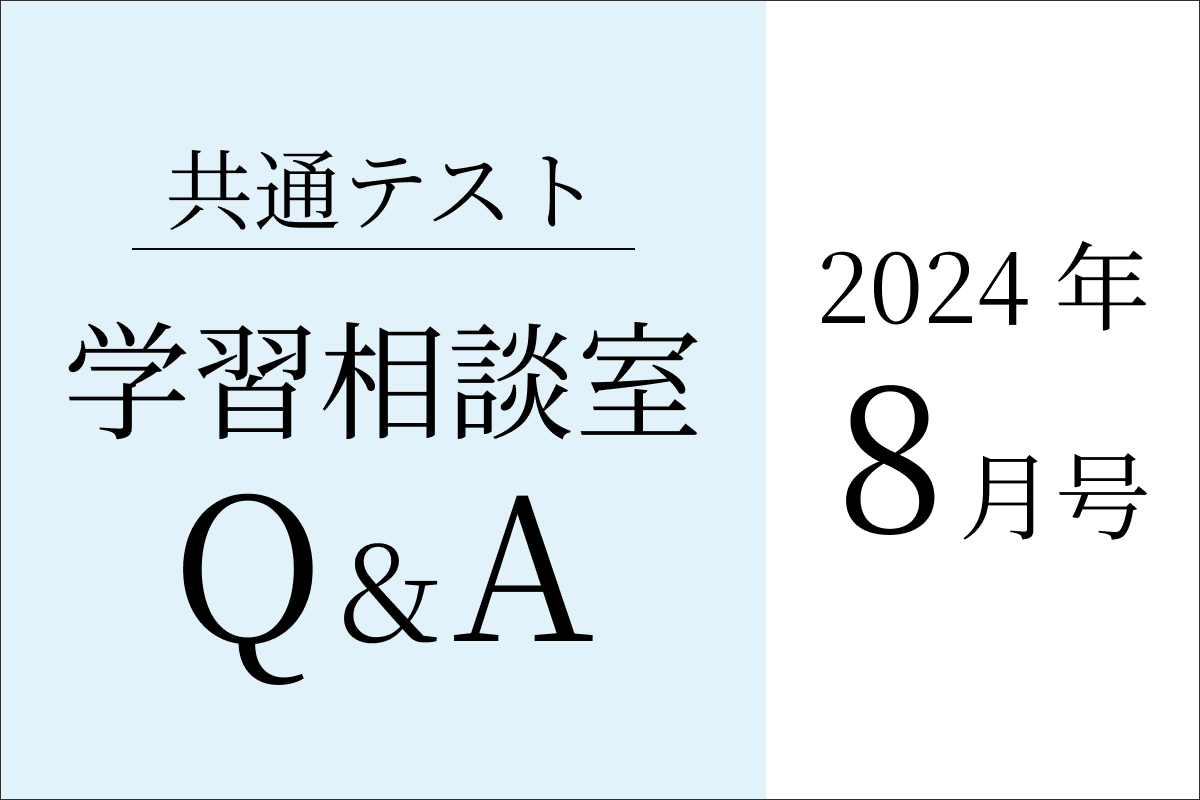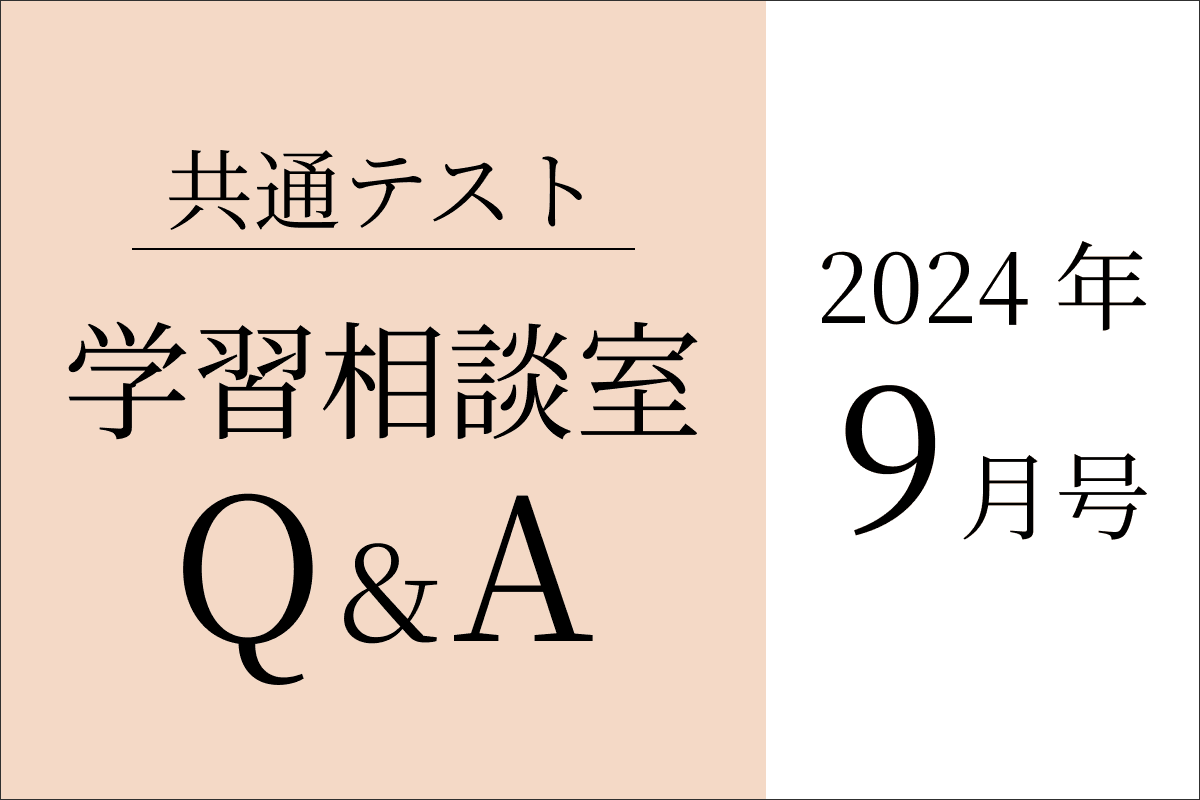共通テスト学習相談室(2022年7月号)
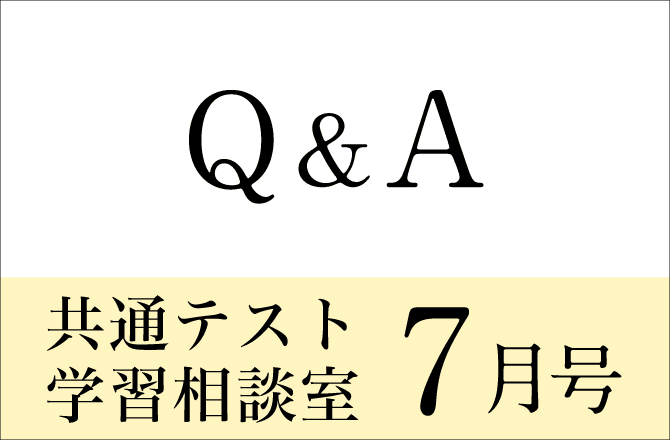
投稿日時:2022年7月21日
今回は6月に寄せられた質問を中心に紹介します。共通テスト模試についての質問が多く、「模試での得点アップの方法」「そもそも模試を受けるべきか?」などにお悩みの方が多いようです。Z会の高校学習支援担当がアドバイスをおくります。
模試になると時間が足りなくなってしまう…。
受験生の悩み
共通テスト模試をいくつか受けています。速読英熟語で所見の文章を1分100字程度の速さで読めるようになったのですが、模試では大問1つ分がほとんど手付かずの状態です。特に前半部分に時間がかかっているように感じています。どうすればいいですか?【高3、京都大学 文系 志望】
Z会がお答えします!

速読の学習を頑張っているようですね。 共通テストの前半部分の時間を短縮するために、速読の対策はさらに進めるとよいでしょう。
例えば、毎日英語のニュース記事などを読むようにするのがおすすめです。なるべく素早く英文を読み進めつつ、誰かに説明できるくらい正確に内容を把握するようにしましょう。
共通テストの前半の問題は語彙や文法が比較的簡単なものが多いので、易しい表現を用いた短めの記事を選ぶと無理なく取り組めてよいと思います。
東大模試対策を優先したいが、共通テスト模試は受けるべき?
受験生の悩み
7月下旬に共通テスト模試が学校で実施されるのですが、夏までには東大模試をめざして過去問を解いたり苦手克服に取り組んだりしたいと思っており、共通テスト模試が負担になるように感じます。この時期に共通テスト模試を受験することは必要・重要でしょうか?なお、前回の共通テスト模試受験は5月末です。【高3、東京大学 理科一類 志望】
Z会がお答えします!

東大模試が夏休みに開催されるので、その準備のためには共通テスト模試に割く時間がもったいなく感じてしまう気持ちはよくわかりますが、学校で開催してもらえるものであれば積極的に受けておいて問題ありません。
現時点ではなかなか共通テスト型の問題に触れる機会が少ないですから、数カ月おきに基礎が身についているかを確認するための貴重な機会として、共通テスト模試は活用したほうがよいでしょう。
また、現時点で東大模試のために過去問演習を行うことはおすすめしません。あくまでも東大模試は全国の志望者の中での実力の立ち位置の把握や形式に慣れるためのものですし、過去問演習は全体の学習がおおむね終了する9~10月ごろから始めたほうがより効果的です。
過去問を1年分軽く確認する程度であればやって損はありませんが、現時点では過去問演習に時間を割くよりも苦手克服を中心に対策を行っておくことをおすすめします。
模試の会場受験とオンライン受験の違いは?
受験生の悩み
7月の共通テスト模試について質問です。受験予定の共通テスト模試には会場受験とオンライン受験があるのですが、会場受験が4,900円でオンライン受験が1,000円とのことです。受験者数は多少異なるもののオンライン受験でもよいかな…と思っています。会場受験とオンライン受験の違いはどんなものでしょうか?【高3、京都大学 理学部 志望】
Z会がお答えします!

オンラインと会場の最も大きな違いは、やはり雰囲気や緊張感です。本番は会場で受験するわけですから、実際に会場で受験して雰囲気や緊張感を含めて体験しておくことをおすすめします。受験料は確かに高くなってしまいますが、より本番に近い状況で自分の実力を測ることができるでしょう。
その他の違いとしては、解答方法(オンライン受験では、マークシートを鉛筆で塗るのではなくパソコンやタブレット上で選択して解答)や、問題用紙の見やすさなどがあります。
本番は自分の手で鉛筆を使ってマークシートを塗るわけですから、マークシートを塗る手間なども実際の会場で練習した方がよいでしょう。また、問題用紙もマークシートとともにパソコンやタブレット上に表示されるため、書き込みがしづらく、見にくい可能性があります。
以上を踏まえ、ぜひ会場での受験を検討してくださいね。
共通テスト模試で結果が出ない…。勉強方法を変えるべき?
受験生の悩み
共通テスト模試で全然結果が出ないのですが勉強方法を変えるべきなのでしょうか。それともこのまま続けるべきでしょうか。間違えてしまう箇所は、既習範囲で忘れていること、古文漢文で読解が全くできないこと、英文が正しく読めていないことなどだと考えています。【高3、京都大学 工学部 志望】
Z会がお答えします!

まずは、得点が伸びない原因をより深堀りして明らかにすることが大切です。
既習範囲で忘れている事項については、あくまでも部分的に忘れているだけなら、「問題演習→復習」を繰り返すことで補強できます。しかし、あまりに忘れている知識が多いようなら学習方法を変え、基礎固めから取り組むことをおすすめします。
古文・漢文と英語については、共通テストレベルの文章が正確に読めないのであれば、単語や文法、構文といった基礎が不十分である可能性が高いです。読解力は読解問題をひたすら解いていけば高まるのではなく、単語や文法・構文といった基本的な知識を丁寧に押さえ、それらをもとに語と語のつながりや文の構造を把握して正確な意味を捉えることが必要です。
秋以降に本格的に入試演習を行うためにも、まずはこれらの基本的な事項を夏までに定着させておきましょう。
物理:基礎力はついているはずなのに、難度の高い模試では点数が取れない…。
受験生の悩み
物理に関する質問です。共通テスト模試で9割を取れているため基礎力はついたものだと判断し、よりレベルの高い問題集に取り組み始めていたのですが、駿台模試やプロシード模試などの難しい模試では全然点数が取れません。もう少し標準的な問題から解けるか確認した方がよいのでしょうか?【高3、京都大学 工学部 志望】
Z会がお答えします!

いわゆる典型問題は解ける状態のようですので、その典型問題に対応できるやり方を、融合問題に適用できるようになれば、レベルの高い入試問題でも解けるようになります。
模試で得点できなかった原因を深掘りして分析することが重要です。問題文を読解できれば解説どおりに解ける状態にあるなら、入試レベルの問題演習を繰り返して、対応力を強化すればよいでしょう。問題文を要素に細分化しても解法を思いつけないようであれば、基本的な知識や理解が不足している可能性が高いので、基本に戻って理解度を高めていくのがよいでしょう。
今月の受験対策アドバイス
夏に共通テスト模試を受験する人は多いと思われますので、受験前に考えておく戦略についてお伝えします。
すでに1度は共通テスト模試を受験した人が大半だと思いますが、共通テスト型の問題の難しさは分析できているでしょうか?科目別にざっくり判断すると、
- 英語・数学・国語:試験時間に比しての問題文量が多く、時間内にすべての問題に取り組むこと自体が難しい。
- その他の科目:現役生は対策が間に合ってないことから、そもそも解けない問題がある。
という感じになるかと思われます。この傾向を踏まえて、夏の模試では、
- 英語・数学・国語:時間配分を意識して取り組む
- その他の科目:事前にできるだけ対策し解ける問題を増やす
という感じで、事前準備、および試験中の戦術を考えた上で受験を行ってください。そうすることが、結果の正しい分析につながります。
(Z会高校学習支援担当 山邊圭祐)
Z会でできる大学受験対策
◆[専科]共通テスト攻略演習
共通テストの傾向をふまえた教材に取り組みます。毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
◆[Z会の映像]共通テスト対策映像授業
「授業」を中心に学習を進めたい方におすすめ。Z会精鋭講師陣による質の高い解説講義(映像授業)で、共通テストの攻略ポイントを学びます。
◆[Z会の通信教育]高2生向け講座
高2の夏は成績アップの分岐点。ここで難関大合格を見据えた学習を始めておくことが、共通テストでの高得点にもつながります。
同じカテゴリの人気記事
共通テスト学習相談室
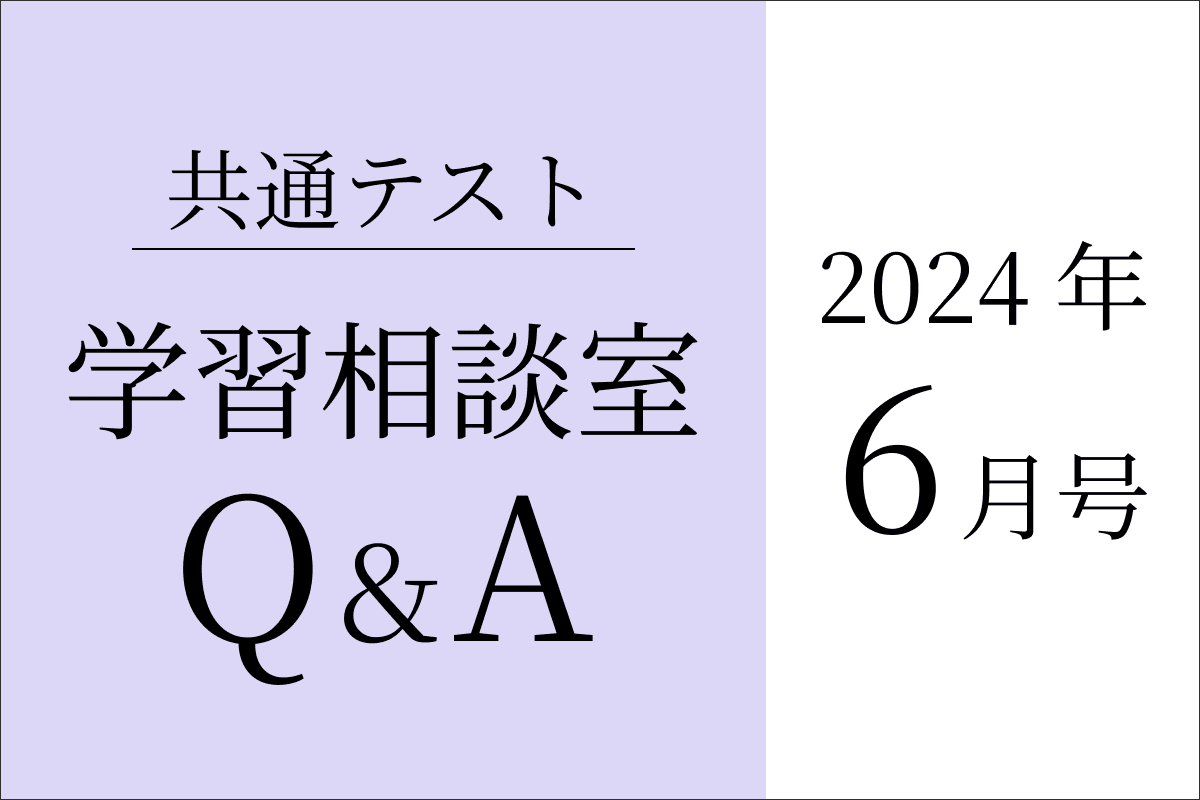
共通テスト学習相談室(2024年6月号)
2025年1月実施の共通テストから「情報」が追加されることが決まっており、皆さんもどのように学習を進めていったらよいのか、気になっていますよね。今回は「情報」についての相談(おすすめ問題集・参考書、学... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む