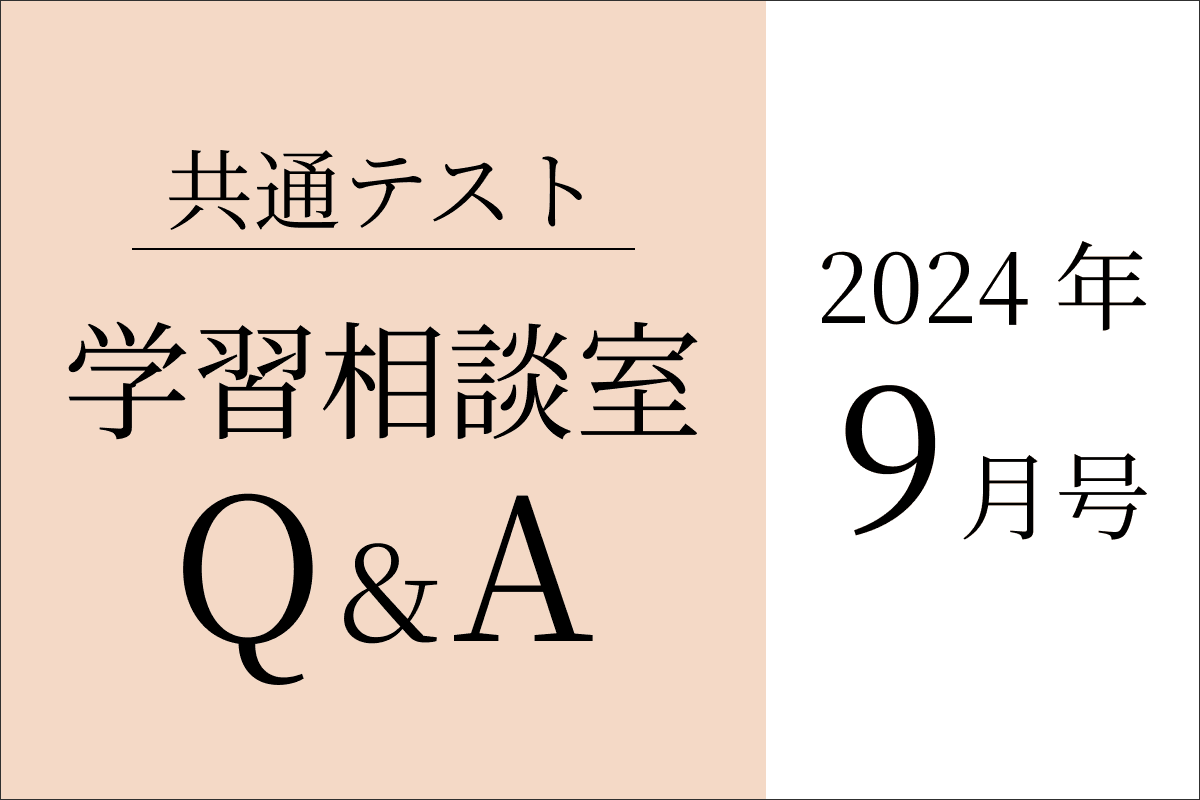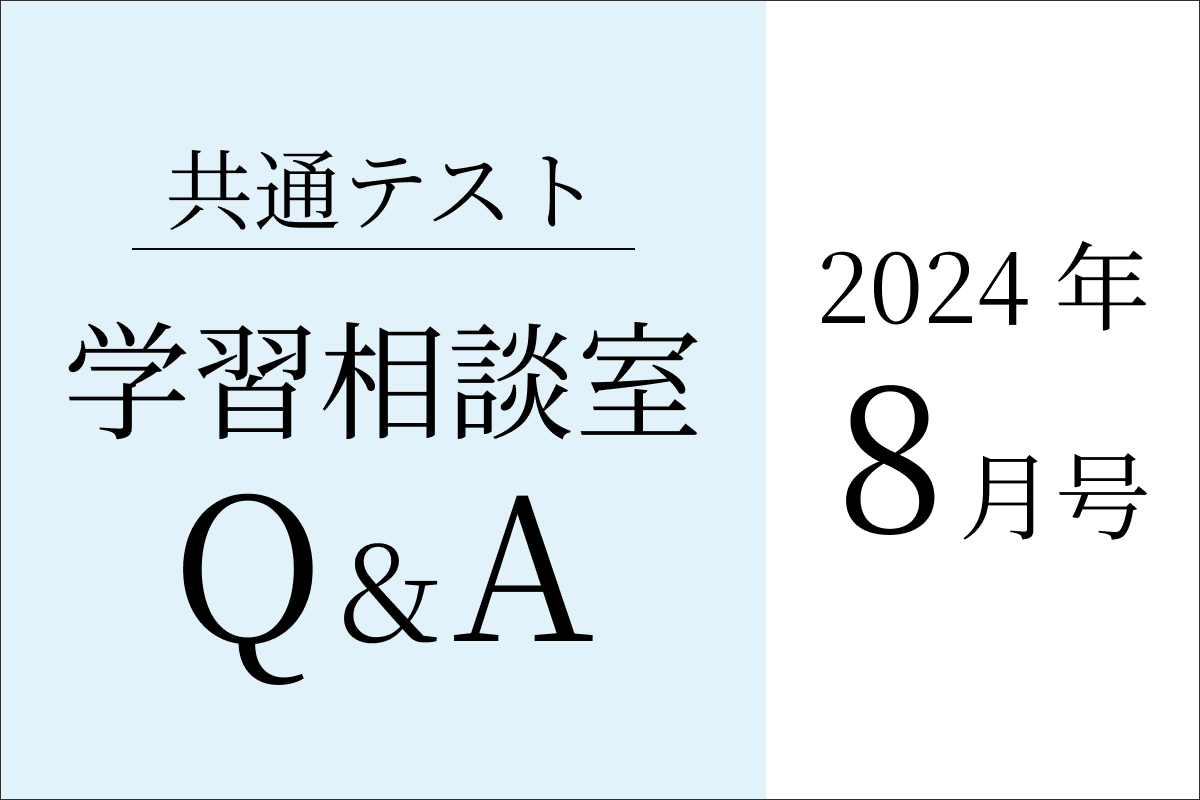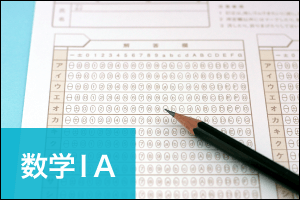共通テスト学習相談室(2022年10月号)
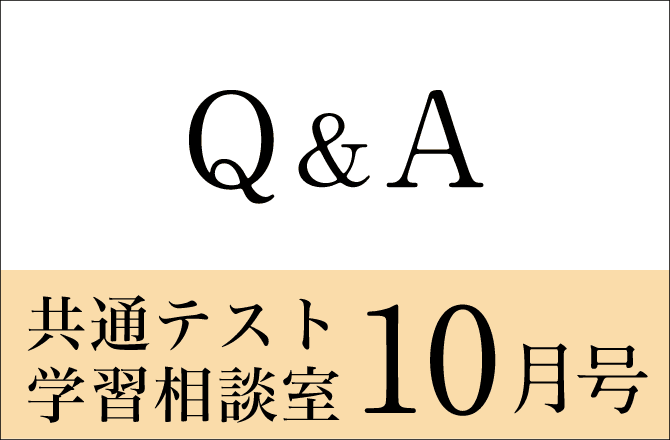
投稿日時:2022年10月21日
今回は9月〜10月に寄せられた質問を中心に紹介します。模試の結果をふまえた相談から、過去問対策のタイミング、時間配分のお悩みまで、抱える課題も様々です。Z会の高校学習支援担当がアドバイスをおくります。
共通テスト模試の得点が伸びない…。
受験生の悩み
この夏も努力はしたのですが、持っている知識を結びつけるのが大変で、地理の成績が5割程度でした。なんとか他の教科で8割弱は死守していますが、どうにかして上げたいです。
参考書を買うべきならばどのようなものを選ぶべきでしょうか。
【高3、東京大学 理科一類 志望】
Z会がお答えします!

5割程度の得点ということは、まだまだ定着していない知識があるはずです。盤石な知識があれば7割程度は得点できるはずです。時間はそれほど残されてはいないので、共通テスト型の問題に取り組みつつ、失点した箇所について、①知識の不足、②問題文の読み取りの思考力の不足、のいずれに該当するかを確認しましょう。①の場合は教科書や参考書に戻って確認、②であれば考え方を吸収、という形で進めてください。
用いる問題集は、Z会の『共通テスト実戦模試』のような共通テスト1回分の問題がまとまったものがおすすめです。時間を計って取り組んでください。
時間内に解き切ることが出来ない場合は、時間外に解いた問題を明らかにした上で解答し、正答できるかどうかを確認してください。せっかくのトレーニングなのに、解かない問題があるともったいないですからね。
現代文:マーク形式の問題にも取り組むべき?
受験生の悩み
現代文の点数が、模試を受けるごとに下がりっぱなしです。解答解説も意識して読んでいるつもりなのですが一向に改善する気配がありません。週1ペースで記述式の問題を解いたり、Z会の添削問題を解いたりしていますが、マーク形式の問題は解いていません。
やはり、個別試験ばかりを意識するのではなく、できないところを減らすためにもマーク形式の問題を解くべきでしょうか?
【高3、京都大学 経済学部(文系) 志望】
Z会がお答えします!

現代文は、今の時期であればまだ記述問題を中心に取り組む方針でよいと思います。
共通テスト(選択式問題)でも、頭の中で組み立てておき、それに最も近い選択肢を選ぶという点で、記述問題と同じ思考力が求められるからです。きちんと復習する姿勢は素晴らしいので、そのまま続けてみることをおすすめします。
英語:時間が足りない…。共通テスト英語の時間配分のコツは?
受験生の悩み
共通テストの英語で毎回時間がなくなってしまいます。時間を意識して解くとミスを多くしてしまいます。どうしたらよいのかわかりません。
【高3、総合人間学部(文系) 志望】
Z会がお答えします!

英文を何度も読み返してしまって時間が足りなくなってしまったという経験があると思います。この「読み返し」をなるべく減らすことを目標に勉強を進めるとよいと思います。
①短期的な工夫:段落ごとにメモを取る。
すでに実践しているかもしれませんが、第5問や第6問などやや長めの長文を読むときには、パラグラフごとに(ごく簡単な)メモを残しておくとよいです。パラグラフのテーマを表す言葉を日本語でひとこと走り書きしておくだけでも十分です。こうすると、設問を解くときにどの段落を見ればよいか迷う回数を減らせます。
②中期的な工夫:メリハリをつけて読む。
共通テストの英語の語数は6,000語程度になりますので、どの文も均等に読んでいると時間はなくなるようにできています。そのため、設問を先に確認して、それに関連した箇所に注力して読み、他の部分はさっと読む、といったメリハリをつけることが大切です。過去に受けた共通テスト模試の解き直しをするときなどに練習してみましょう。
③長期的な対策:構文解釈の実力を上げる。
何度も繰り返し読み返す箇所は、文法構造が込み入っていて意味がつかみにくい箇所であることがほとんどです。複雑な構文を正確に読み取れるように、構文解釈の練習に引き続き力を入れてください。
共通テストの過去問はいつから始めればよい?
受験生の悩み
共通テストの過去問は、いつ頃から始めるのがよいでしょうか。私は12月中旬頃だと考えているのですが…。
【高3、東京大学 理科一類 志望】
Z会がお答えします!

10~11月の共通テスト模試で8割程度得点できる場合は、本格的な共通テスト対策は12月中旬ごろからの開始で構いません。
一方、8割を切る場合は、状況に応じて11月頃から徐々に対策を始めていきましょう。なお、共通テストの過去問は2年分しかないため、Z会の『共通テスト実戦模試』などの実戦形式の問題集に取り組むとよいでしょう。
国語:表現を問う問題の対策法を教えてください。
受験生の悩み
共通テストの国語の表現を問う問題はどのように対策すればよいですか?
【高3、東京大学 文科一類 志望】
Z会がお答えします!

表現の特徴を問う問題の選択肢は、たいていの場合、
①文章で用いられている表現(たとえば、「比喩を用いて」「擬態語を用いて」など)と、
②表現がもたらす効果(たとえば、「厳密に描いている」「軽やかな印象を与えている」など)の2つから成り立っています。
そのため、選択肢を①と②に区切って、部分ごとに正誤を考えると、正解にたどり着きやすくなります(特に、①の「文章で用いられている表現」に目を向けると、判断しやすいと思います)。
ただし、表現の特徴を問う問題は国語の先生の間でも難問とされているので、ここを完璧にすることよりも、他の問題で確実に正解できるようにすることのほうが優先順位は高いと考えてください。題材が共通テストの過去問や予想問題に限られるため、1回1回の問題演習を大切にするとよいでしょう。
Z会からのアドバイス:10月以降の共通テスト対策について
夏休みが終わって、共通テスト模試の得点が伸びないことを気にする人が増えてきました。みなさんからの相談は以下の3つに大別されますので、それぞれに対するアドバイスを記載します。
いつから共通テストの対策を始めればよいか?
模試で自身の目標点に達していない科目は、今すぐにでも対策に着手したほうがよいでしょう。全科目を網羅的に対策する必要はないので、科目ごとに考えることが重要です。
模試などでコンスタントに8割台の得点をとることができている場合は、12月に入ってから本番に向けて調整すれば問題ありません。
特定科目の得点が伸びないがどうすればよいか?
週1日でもよいので、時間を確保して共通テスト型の問題に取り組みましょう。先月のアドバイスと重なりますが、得点が伸びない原因が「そもそも知識・理解が不足しているから」なのか「共通テストの出題形式などに慣れていないから」なのかを切り分け、それに応じた対策を進めていくことが重要です。
特定科目の特定の出題傾向に対する相談
苦手な科目・苦手な出題形式がある場合には、「その出題を攻略する必要があるか」を考えましょう。
上記の「国語の表現を問う問題」の例ですと、この種類の設問は現代文の各大問に1つあるかないか程度であるため、得点にして20点を超えることはありません。そのため、仮に今国語が140点に到達しないレベルで苦しんでいるのであれば、この出題のみの対策では不十分なので、国語全体の得点や他科目での得点を上積みすることをめざしたほうがよいでしょう。
本番までの期間も短くなってきたので、合格に必要な得点から逆算して、出題の配点や出題頻度なども考慮しつつ対策の要否を決めることが必要です。
共通テスト本番まで残り2カ月程度です。「自分のやろうとしていることが、どのような結果につながるか」をよく考えて、対策を進めるようにしましょう。
(Z会高校学習支援担当 山邊圭祐)
Z会でできる大学受験対策
◆[専科]共通テスト攻略演習(高3生・高卒生向け)
共通テストの傾向をふまえた教材に取り組みます。毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
◆[Z会の映像]共通テスト対策映像授業(高3生・高卒生向け)
「授業」を中心に学習を進めたい方におすすめ。Z会精鋭講師陣による質の高い解説講義(映像授業)で、共通テストの攻略ポイントを学びます。
◆[Z会の通信教育]高2生向け講座
高2から難関大合格を見据えた学習を始めておくことが、共通テストでの高得点にもつながります。
同じカテゴリの人気記事
共通テスト学習相談室
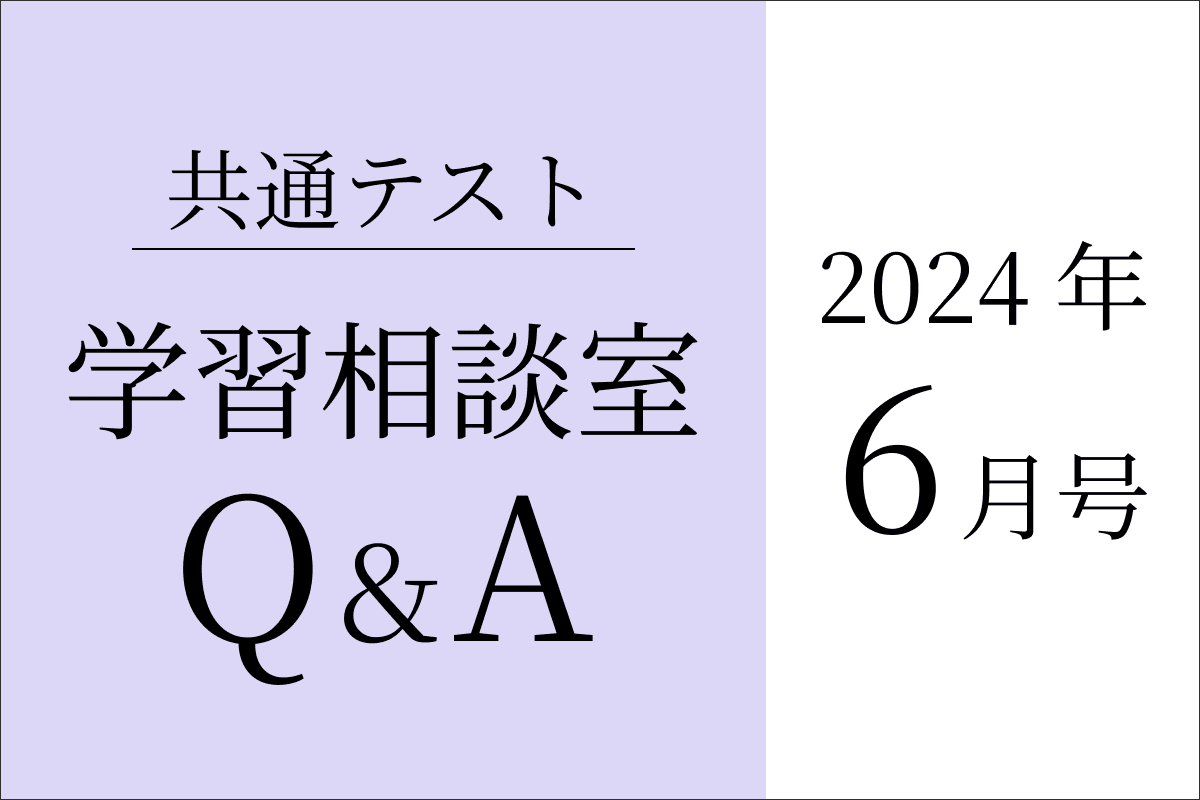
共通テスト学習相談室(2024年6月号)
2025年1月実施の共通テストから「情報」が追加されることが決まっており、皆さんもどのように学習を進めていったらよいのか、気になっていますよね。今回は「情報」についての相談(おすすめ問題集・参考書、学... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む