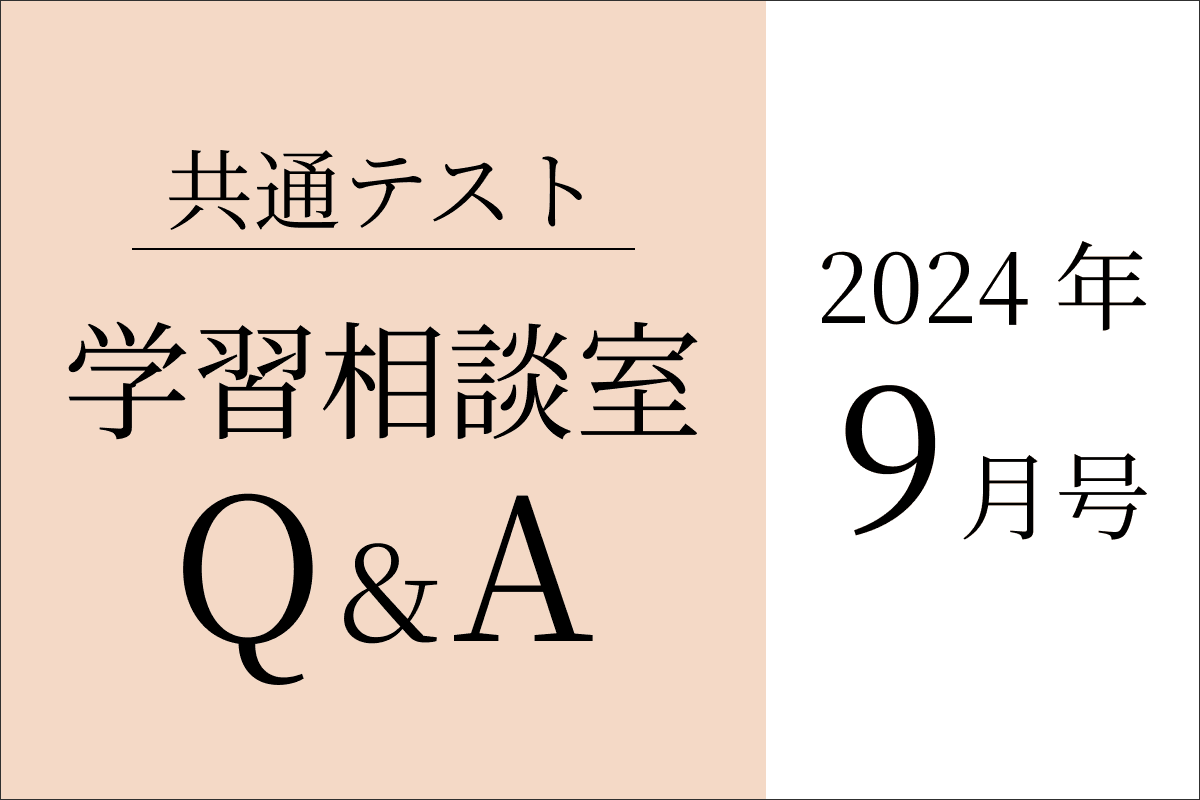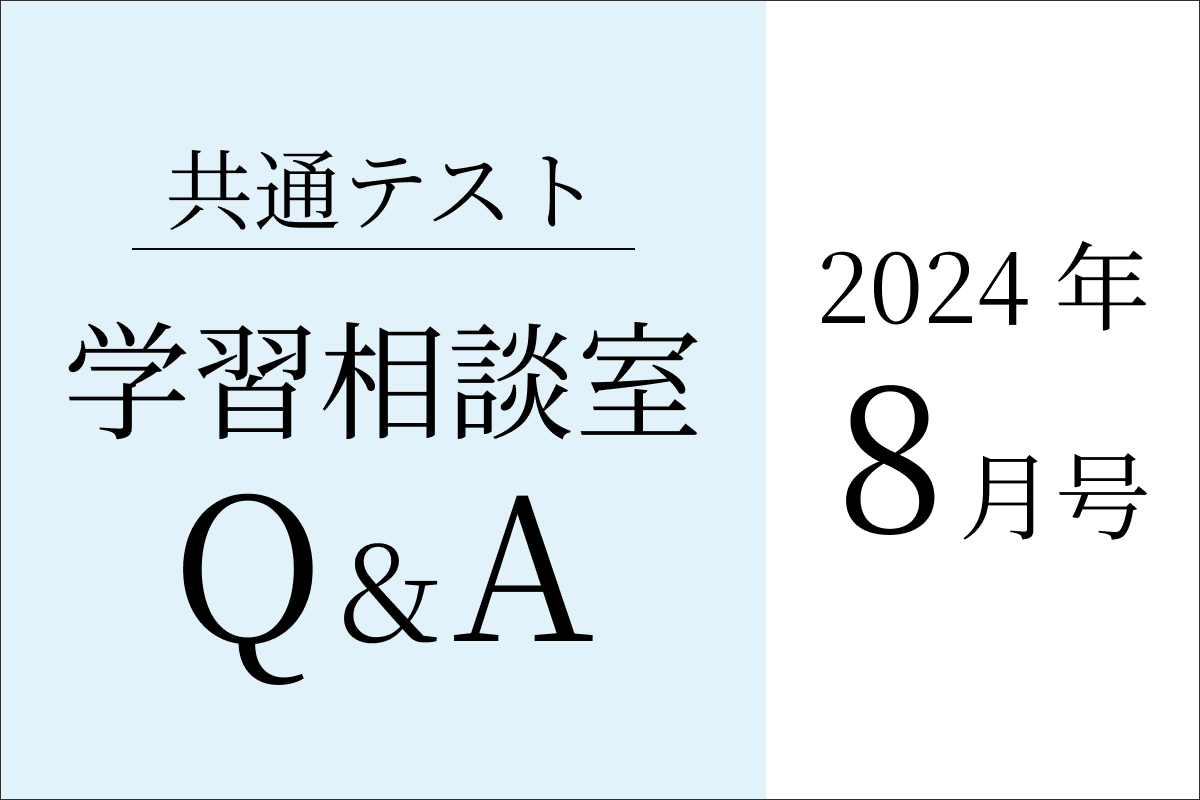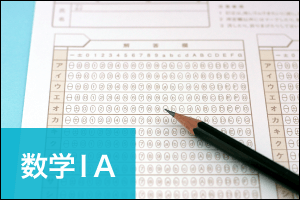共通テスト学習相談室(2022年11月号)
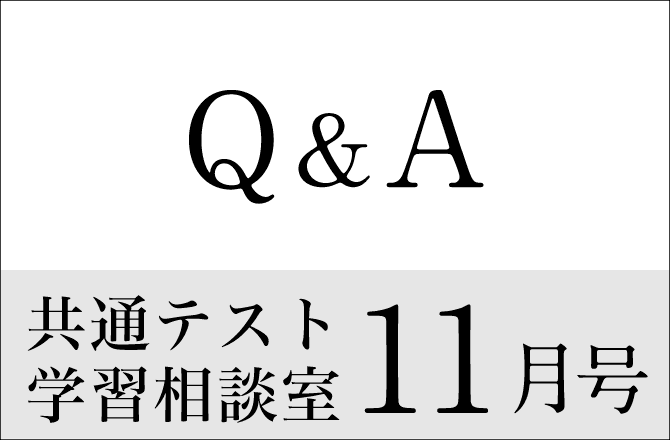
投稿日時:2022年11月22日
今回は10月〜11月に寄せられた質問を中心に紹介します。本番が近づくにつれて実戦的なお悩みが増えてきました。Z会の高校学習支援担当のアドバイスをぜひ参考にしてください。
英語:リスニングに慣れるための具体的な方法は?
受験生の悩み
共通テストのリスニングは安定して9割ほど取れるのですが、東大形式のリスニングは波があり、今回の冠模試では5割ほどでした。 現在、TEDトークを聞いて耳を慣らす練習しかしていないのですが、何か他に方法はありますか?
【高3、東京大学 文科三類 志望】
Z会がお答えします!

問題集や過去問を活用して、リスニング問題を解く練習をしましょう。
リスニング問題を解くためには、英語を聞き取る能力そのものだけでなく、重要な部分とそうでない部分を適宜判断して集中力に強弱をつける力や、聞き取った情報と設問とを素早く結びつける力など、「問題を解くための力」も必要になります。
英語を聞き取る力はTEDで伸ばせていると思いますので、あとは問題を解く練習をすると良いでしょう。
英語:速読と精読を両立するためには?
受験生の悩み
共通テストや東大英語に求められる速読を意識し始めたら、読解が雑になってきてしまい、悩んでいます。文の大意は掴めるのですが、細かい内容を無意識に読み飛ばしたまま解いてしまうので減点が目立ちます。速読と精読の両立のためにはどんな読解演習が効果的ですか?
【高3、東京大学 文科一類 志望】
Z会がお答えします!

いきなり本番レベルの速読をするのではなく、徐々に読解スピードを上げていく意識で学習すると良いでしょう。
例えば、精読すると20分かかる文章だとすると、まずは18分で読解することを目指し、次は15分、次は13分、…などのように、徐々に制限時間を短くして取り組んでみましょう。そのようにすることで、読解の精度を大きく落とすことなく、自然にスピードアップすることができます。
塾・予備校の冬期講習や直前講習には通うべき?
受験生の悩み
塾には通わず、Z会の通信教育と参考書だけで学習しています。最近、冬期講習や直前講習の情報が公開され始めましたが、それらに通って周りの刺激も受けながら東大に特化した授業を受けるのも有意義なのではないかと感じます。
しかし一方で、これまで塾に行かなかった分、学習ペースの乱れ・授業が自分に合わない、などのデメリットも懸念しています。本心では、今まで通り塾には通わずZ会を利用して学習を進めていく方が良いと考えていますが、迷いや不安を感じてしまいます。
各種講習に通うべきか、今後の学習についてのアドバイスをいただけると嬉しいです。
【高3、東京大学 理科一類 志望】
Z会がお答えします!

塾に限った話ではありませんが、大抵のツールにはメリットデメリットがあります。
塾のデメリットで言えば「講義のスケジュールが合わない可能性がある」「移動時間などのロスが大きい」「問題演習を積むことが今の課題であれば目的に合わない」などです。なんとなく「皆が通うなら私も…」という気分で始めると、このデメリットをもろに受けることになります。
一方で「苦手分野の講義を聞きたい」「問題演習で解説を読んでも理解しきれない部分を解消したい」「ライバルを見て刺激を得たい」などの目的があれば、塾に通うことで一定の効果を得られることが多いです。
私たちは、ご自身のためにとった行動であればそれを応援します。「塾に何を求めるのか」「それは塾に通った方が解決しやすそうか」という視点で再考してみてください。
数学・理科:目標点に届かない…。対策法は?
受験生の悩み
共通テストの対策をしているのですが、思うように点が取れず、どうしたらいいのかがわかりません。特に数学と理科基礎が悪く、目標点数に5点〜10点届いていない状態が続いていて、焦っています。 でも二次の割合が多いから…と思うと共テ対策ばかりに手をつけられず、自分でもバランスのとり方がわかりません。 どのような対策をするべきなのか教えてください。
【高3、京都大学 法学部 志望】
Z会がお答えします!

数学については、共通テストは純粋な数学の力というよりは、問題文の読解力と読解のスピードによって得点が決まる部分がありますので、一定以上の得点を狙って対策を行うことは難しいです。そのため、80点程度の得点ができているのであれば、あとは定期的に共通テスト型の問題を用いて対策を行う形で、あまり時間をかけずに進めるのがよいでしょう。
理科基礎については、基本事項の理解や定着に問題があることが、目標点に届かない原因のように思いますが、こちらも40点程度の得点ができているなら、過剰に意識せず、全科目の得点を8割にまとめる観点で、念入りな対策が必要か否かを判断してください。
なお、理科基礎は個別試験では課されないので、2科目とも40点以上に揃えたいと思うなら、「共通テスト型の問題に取り組んで課題を見つけ、その課題を教科書と問題集によって解決する」という対策を、少なくとも週1回は行った方がよいでしょう。
Z会からのアドバイス:10月以降の共通テスト対策について
共通テストまで残り3カ月ほどとなり、特定科目に関する粒度の細かい相談が増えてきました。それらの相談の多くが「やらなくてもよいこと」を探しているような印象を受け、強い危機感を抱いています。(化学の「無機」は対策すべきか、漢文にどれくらい時間をかけるべきか、等)
国公立大学を志望する場合、出願するためには、最低でも出願可能な得点を共通テストでとる必要があります。個別試験の対策も佳境となり、共通テスト対策に割く時間が限られていることは理解しますが、共通テストでの得点率は軽視すべきではなく、必要な対策には注力することをおすすめします。
共通テストは、出題難度自体はそれほど高いわけではなく、教科書の範囲内から出題されます。時間をかけて対策をすれば得点率は上がる場合が多いです。12月には共通テスト対策の比重を上げるなどして、最後まで諦めずに取り組みましょう。
(Z会高校学習支援担当 山邊圭祐)
Z会でできる大学受験対策
◆[専科]共通テスト攻略演習(高3生・高卒生向け)
共通テストの傾向をふまえた教材に取り組みます。毎月の演習で、基礎固めから最終仕上げまで段階的に対策を進められます。
◆[Z会の映像]共通テスト対策映像授業(高3生・高卒生向け)
「授業」を中心に学習を進めたい方におすすめ。Z会精鋭講師陣による質の高い解説講義(映像授業)で、共通テストの攻略ポイントを学びます。
◆[Z会の通信教育]高2生向け講座
高2から難関大合格を見据えた学習を始めておくことが、共通テストでの高得点にもつながります。
同じカテゴリの人気記事
共通テスト学習相談室
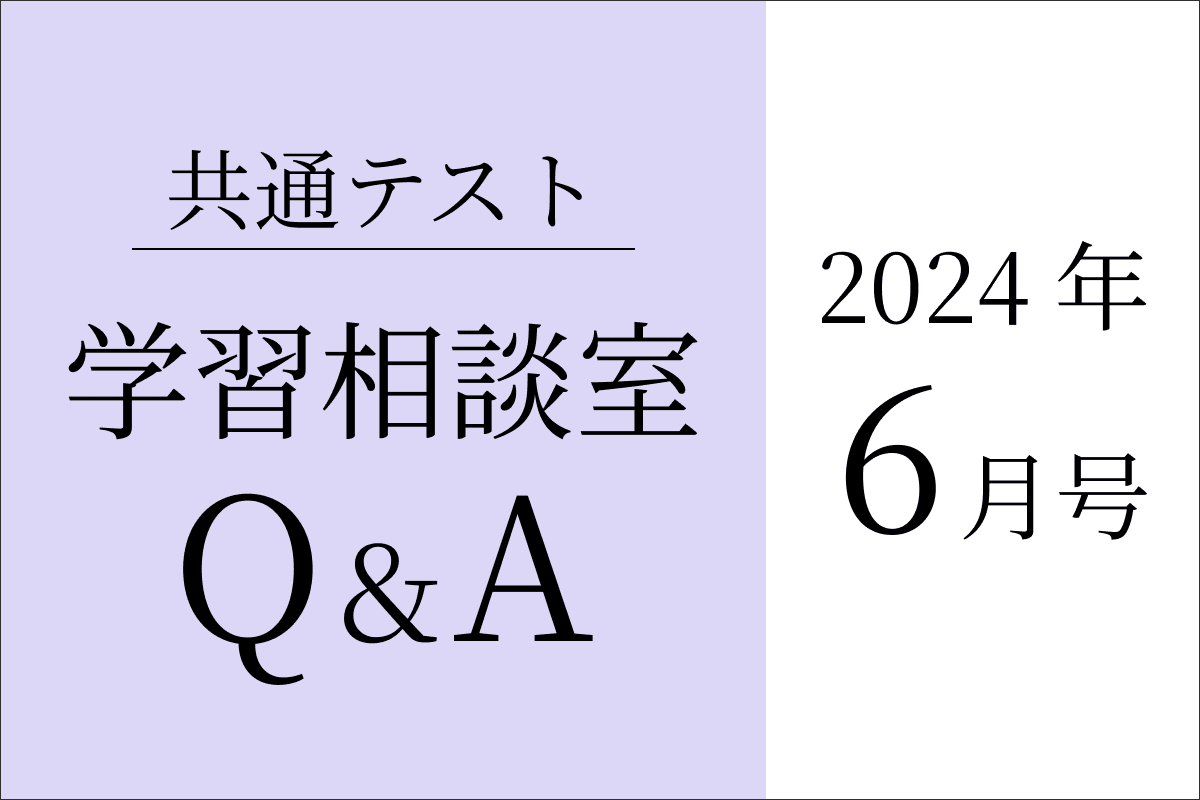
共通テスト学習相談室(2024年6月号)
2025年1月実施の共通テストから「情報」が追加されることが決まっており、皆さんもどのように学習を進めていったらよいのか、気になっていますよね。今回は「情報」についての相談(おすすめ問題集・参考書、学... (続きを読む)
詳細を読む
「Z会共通テスト対策サイト」の人気記事
指導担当者による共通テスト対策アドバイス

【2025年からの共通テスト】地理歴史・公民は2科目1セットで出題
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は2025年1月から大きくかわります。地理歴史・公民での変更内容と必要な対策について、Z会担当者が解説します。(「Z会の通信教育」大学受験地歴・公民担当・荒川裕子... (続きを読む)
詳細を読む