《小さな引き出し》から積み重ねる小論文対策
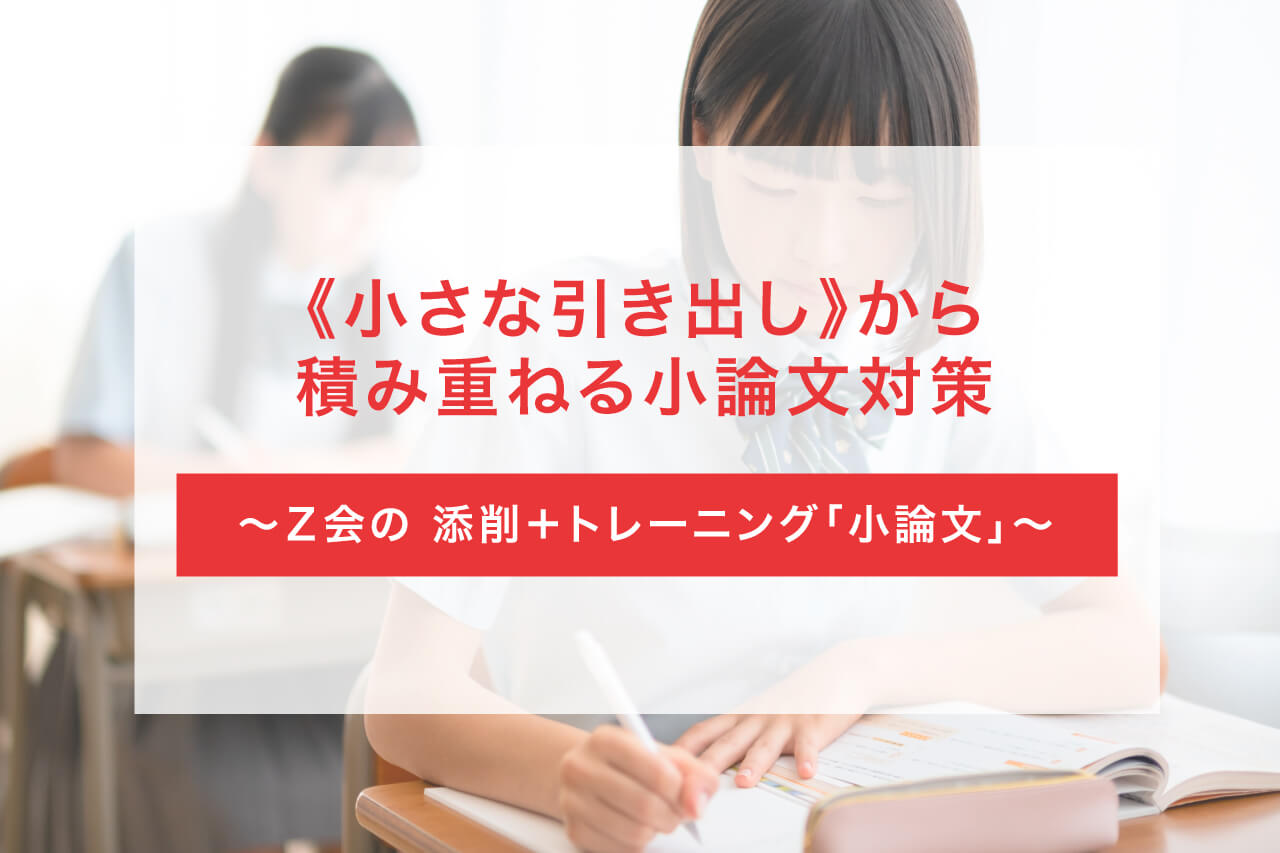

Z会ソリューションズ 先生向け教育ジャーナル
Z会ソリューションズでは、中学・高等学校の先生向けに教育情報を配信しています。大学入試情報、文部科学省の審議会情報をはじめ、先生方からお伺いした教育についてもご紹介します。
新しい学力観と小論文
「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を重視する新しい学習指導要領と連動した大学入試改革は、現在も進行中です。とりわけ、国公立も含めて、総合型選抜・学校推薦型選抜方式はその定員割合を大きく伸ばしてきています。
ここで求められる力は、特定の教科の枠組みで決められた知識と技能の量と運用能力ではなく、知識と技能に加えて、自らの体験や探究の成果を総動員して表現するという汎用的な力です。これらを問うためにどのような出題がなされるべきか、どう評価するか、その方法は千差万別ですが、多くのケースで課されるのは、面接・志望理由書に加え、小論文やプレゼンテーション・レポートといった、あるテーマに対する考察とそのアウトプットです。
面接や志望理由書とは別に、あえて小論文が課される意味を考えれば、高校までの活動や大学で学ぶ意志をアピールすることとは別の形で、大学で学ぶための学力や資質、入学後に学問や研究に主体的に取り組む目的意識など、受験生の潜在能力が問われているとみるべきでしょう。
〈考える〉〈整理する〉〈書く〉の積み重ね
そこで必要なのは、出された課題に対して、形式的に整った解答を作成することではなく、問題を自分自身の立ち位置から捉えて考え、意見を打ち出す技能とチャレンジ精神だといえます。そのように考えれば、小論文対策は直前期にノウハウを取り入れるだけで太刀打ちできるものではありません。早い段階から〈考える〉〈整理する〉〈書く〉ことの訓練を丁寧に積み上げていくことが不可欠なのです。次のように、順を追って3つのステップを踏んでいただくとよいでしょう。
〈考える〉
最初から、何か大きな問題に取り組む必要はありません。自分自身の身の回りで起こっていることや経験したこと、また日常の学習で知りえたことのなかで、関心をもったことや疑問に思ったことをそのままにせず、その「ひっかかり」を少し突き詰めてみることです。「何が起こっているのか」「別の視点でみると事態はどう見えるのか」「自分の関心や疑問は何に起因するのか」「これから考えるべきことは何か」といった観点から考えて、自分の《小さな引き出し》としてもっておき、少しずつ増やしていってほしいと思います。引き出しAと引き出しBが、あるときに繋がって、考えが一気に深まることもあるでしょうし、社会的に取り沙汰されているテーマを考えるヒントになることもあるでしょう。
〈整理する〉
考えたことを「意見」にするためには、そのまま書きつらねるのではなく、筋道立てて組み立てなければなりません。「論点」、「主張」、「根拠」、「事例」などを過不足なく組み入れて全体を構成します。とくに、明快で力強いものにするためには、不要な内容や冗長な表現をとる思い切りが必要です。
その上で、論理的・客観的に検証して「意見」として成立するかどうかを慎重に見極めることが肝要です。自分の考え、参照した文献や見解について、「本当にそう言えるのか」という目で厳しく批判し、論理が崩れるならば別の方法で再構築する。そのプロセスは苦しいものですが、乗り越えてこそ、論理的思考力は鍛えられます。
〈書く〉
〈考える〉〈整理する〉を経て形成した自己意見を〈書く〉段階で最も重要なのは、「他者」を想定することです。「他者」としてまず想定すべきは出題者です。出題者の意図を正確にくみ取ってその意図に応える意見提出を行うことが、小論文の最も重要な目的です。さらに、自分以外の第三者としての「他者」も想定する必要があります。提出した意見は、誰がいつ読んでも理解できる明快さと説得力をもつものでなければなりません。そのために、主張とそれを支える論理が誤解なく伝わる構成と、日本語の表現・表記の力、加えて、制限時間内で書き上げるスピードが不可欠です。それらは、整った美しい文章の「見本」に多く触れ、自分でも書く練習を重ねることで、確実に磨かれるでしょう。
従来のいわゆる「入試小論文対策」は、この〈書く〉ステップのみに焦点を当ててきましたが、新しい学力観を反映させた入試への対応を考えるならば、こうした直前期の特訓だけでは間に合わないと考えるべきです。日常生活や日常学習のなかで常にアンテナを張り、《小さな引き出し》をもって考え続ける、考えたことを厳しく検証して論理的に組み立てるというプロセスの積み上げこそが重要なのです。
これは、小論文に限らず志望理由書や面接にもいえることで、高校までの活動について話したり書いたりするときに重要なのは、部活動やボランティア活動で「何をしたか」ではなく、活動を通して感じ、考えたことについて「何がいえるか」です。ここでもやはり、〈考える〉〈整理する〉の積み上げが大きな力をもつことでしょう。
教科学習と両輪で積み上げる論述力
さらにいえば、小論文の入試対策は決して、教科学習とかけ離れたところにあるものではありません。日常の学習こそ、《小さな引き出し》の宝庫です。授業で得た知識や感じたことをフックにして少し突き詰めて考えることは、教科学習への関心を深め、意欲を高めることと表裏一体といってよいでしょう。また、知識や情報を総合し、俯瞰的にマッピングして本質を抽出する能力の必要性は、大学入学共通テストでも前面に押し出されています。
〈考える〉〈整理する〉を実践することで、教科学習をより深め、広げるための試みとして、小論文を〈書く〉力も積極的に鍛えていただきたいと思います。その先に総合型・学校推薦型選抜での受験が選択肢のひとつとして見えてくるのではないでしょうか。
Z会では、こうした学習のステップを体系化したラインナップと添削指導を提供しています。与えられたテーマに対して、一般論に終始することなく主体的な問題意識を提示できているか、客観的・論理的な検証をしっかり行うことができているかを見て、改善すべき点があれば、どうすればよかったのかを、個々の答案に沿って具体的に指導していきます。小論文を書くというチャレンジを通して《小さな引き出し》を集め、「論理的に考える」ことを積み上げる場なのです。
最新の記事
- 新しくなった「Z会テストエディター」 本文データダウンロードもテスト作成もこれ1つで完結!
- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|上智福岡中学高等学校
- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|穎明館中学高等学校
- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|豊川高等学校
- Z会の 添削+トレーニング 導入事例|八千代松陰中学校
- 英語4技能実践例ガイド【第3回】
- 『解いて身につく! 必携古文単語345』~大学入試で求められる古文の力と、本書の特長~
- 共通テスト国語、新課程入試の特徴と今後の対策 ~『ベーシックマスター国語』シリーズ~
- 新課程での共通テスト英語は「10分演習」から。Z会『共通テストドリル英語 10 minutes』
- 英語4技能実践例ガイド【第2回】
Contact
小学校~高校の先生・職員の方
【東京営業所】
月〜金 午前9:00〜午後5:30
(年末年始・土日祝日を除く)
(年末年始・土日祝日を除く)
Fax:03-5280-0071
【大阪営業所】
月〜金 午前9:00〜午後5:30
(年末年始・土日祝日を除く)
(年末年始・土日祝日を除く)
Fax:06-6195-8560
【書籍に関するお問い合わせ】
月〜金 午前9:00〜午後5:30
(年末年始・土日祝日を除く)
(年末年始・土日祝日を除く)
Fax:055-989-1436
【Webからのお問い合わせ】
大学の先生・職員の方/法人の方
月〜金 午前10:00〜午後5:30
(年末年始・土日祝日を除く)
(年末年始・土日祝日を除く)
Fax:03-5280-0071
【大学の先生・職員の方】
【人事・研修担当者様】
【取材のご依頼】
