【学校専用】LIPHAREシリーズ「課題発見・解決能力テスト」 導入事例|愛媛県立松山南高等学校
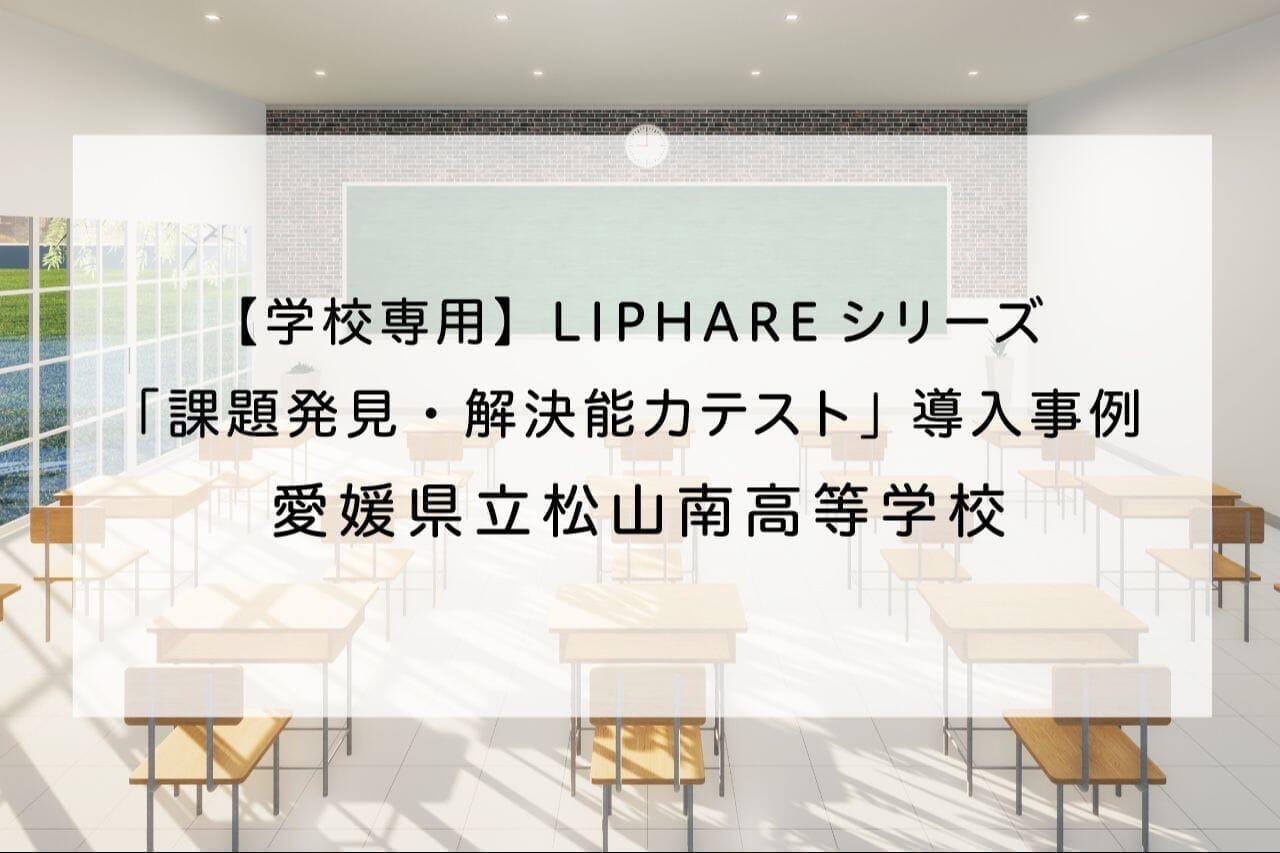

Z会ソリューションズ 先生向け教育ジャーナル
Z会ソリューションズでは、中学・高等学校の先生向けに教育情報を配信しています。大学入試情報、文部科学省の審議会情報をはじめ、先生方からお伺いした教育についてもご紹介します。
愛媛県
愛媛県立松山南高等学校
導入概要
・高校1年生 課題発見・解決能力テスト 応用レベル 学年全員
・高校2年生 課題発見・解決能力テスト 応用レベル 学年全員
どういった経緯で「課題発見・解決能力テスト」のご導入をされたのでしょうか?
近年、大学入試では、総合型選抜や学校推薦型選抜の募集人員が増加傾向にあります。このような変化の中、過去に私が担任し、課題研究を指導した普通科生徒が東京大学の学校推薦型選抜(旧推薦入試)に合格しました。その際、我々教員側の肌感覚として合格可能性があるのではないかと感じていましたが、模試の結果のような根拠になるものが乏しいと考えていました。そこで今後の進路指導では何らかの指標やデータに基づいたアドバイスを行いたいと考えるようになりました。
本校は現在、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の指定を受けており、普通科の生徒はデータを利活用した課題研究を行っているため、指標などはデータを利活用する能力を測定できるようなものが良いと考えていました。そのような中、「課題発見・解決能力テスト」をご紹介いただき、統計データが入った問題や資料を読み取るような出題がされていることが分かったため導入を決定しました。
「課題発見・解決能力テスト」はどのようにご活用されていますか?
本校は、SSHの研究開発目的として「新しい価値を創生する国際競争力を持った科学技術人材育成-Society5.0の実現に向けたSTEAM教育-」を掲げています。簡単に言い換えると「データを活用して様々な課題を解決していこう」というコンセプトで普通科は課題研究に取り組んでいます。
高校1年生、高校2年生の年度末(2月~3月)に課題研究をとおして身についた力を測定するために「課題発見・解決能力テスト」を実施しています。6~7月に結果が返却されるので三者懇談で活用します。高校3年生の三者懇談では結果をエビデンスとして活用しながら、どの入学選抜形式で受験準備を進めていくのかといった内容で進路相談を行っています。
高校1年生・2年生ともに「応用」レベルを受験しています。
課題研究の具体的な取り組み内容を教えていただけますか?
前述した通り、本校は「データを活用して様々な課題を解決していこう」というコンセプトで普通科は学校設定科目「データサイエンス」で課題研究に取り組んでいます。
高校1年生は、RESAS(地域経済分析システム)などを活用しながら愛媛県の現状について知り、改善策を考えていく取り組みを行っています。10月頃に現状について調査したことをまとめ、発表する中間報告会を行い、年度末に改善策や提案をまとめた成果報告会を行っています。
調査・分析・発表のためには、表計算ソフトの操作やデータの分析・活用方法を知る必要があります。そのような専門的な内容については、数学の授業や情報の授業を活用しています。また、学校設定科目「データサイエンス」の授業で、愛媛大学や滋賀大学と連携したデータサイエンスに関する講演や、ビッグデータを扱う企業と連携した講座なども行っています。
高校2年生になると、生徒一人ひとりが興味をもったテーマでグループを作り研究を行います。ここでもデータを利活用することが必須となっています。過去にはデータを活用してスポーツ(部活動)を強くするための研究をした生徒や、地元スーパーの協力を得て販売促進に関する研究をした生徒もいました。
高校2年生でも中間報告会、成果報告会を行い、高校3年生で論文の作成を行いますが、必ず1人1コンテストに応募することを目標としています。生徒は研究内容をまとめ、自ら参加するコンテンストを選び、応募します。高校生向けのコンテストは、内閣府地方創生推進室が主催している「地方創生☆政策アイディアコンテスト」や愛媛大学社会共創学部が主催する「社会共創コンテスト」など、多数開催されています。学校側でもこのようなコンテストを紹介しながら生徒が興味を持てるようにサポートをしています。
課題研究に取り組まれ、課題発見・解決能力テストを受験された結果はいかがでしたでしょうか?
過去に総合・学校推薦型選抜の入学選抜形式で受験した生徒の中には、面接がある試験で面接対応が得意だと思える生徒であっても合格にいたらず、逆にあまり話すことが得意ではないと感じる生徒が合格したというケースがありました。
「課題発見・解決能力テスト」の受験結果を見て、普段から話すことはあまり得意ではないものの、物事をよく分析し、意見を論理的に構築する能力が優れている生徒などを見つけることができました。また、学力試験の結果は目標とする大学に届かなくても、課題発見・解決能力テストの結果が高い生徒もいました。
このような生徒は潜在能力があるのではないかと見ていますが、学習習慣が身につかなかったり、課題研究を発表する場がなかったりすれば、その能力は発揮されないまま高校を卒業していくことになります。普段の授業では学習習慣に関する声掛けをしたり、課題研究では人前で発表する環境を作り、少しでも苦手意識をなくしたりするような機会を提供するなど、生徒一人ひとりの資質・能力を見極めて指導ができればと考えています。
大変素晴らしいお取り組みをされていらっしゃると感じましたが、やはりSSHだからできるお取り組みなのでしょうか。
以前、本校普通科の課題研究は、「調べて、発表する」というような「調べ学習」の域を出ないような内容が多く見られました。しかし、「改善策を提案する」という取り組みを入れることで「探究」へと変化していきました。
調べる段階でも、以前とは異なり根拠をもって現状を示すようになりました。根拠を示すためにはデータの活用は必須ですし、提案内容にも根拠を示す必要があります。徐々にデータの活用や分析ができるようになってきているように感じますが、統計やデータの扱い方などの専門的な内容は、数学や情報の授業での指導が必要となります。この部分については数学や情報の先生方の協力を得ながら、それ以外の部分での生徒へのサポートは担任・副担任の先生が行うような協力関係を築いています。この協力関係の構築はどのような学校でも実現可能だと考えています。
またツールやサイトの使い方についても、最初は生徒の背中を押してあげる必要はありますが、徐々に我々よりも上手に活用し、自走を始める生徒が出てきます。後は生徒の学びが捗るようなサポートしていけば良いと考えています。これもSSHだからできるという訳ではなく、どの学校でも同じような取り組みはできると考えています。とはいえ、生徒たちの資質・能力の特徴は全て表層化するものばかりではありません。そこで、「課題発見・解決能力テスト」のような測定ツールを使い、生徒の見えていない資質・能力を見極めて適切な指導やサポートにつなげていければと考えています。
最新の記事
- 【中学英語】『NEW TREASURE Online Speaking』が切り拓く、生徒の「話したい」を引き出す授業革命 ~教科書準拠の先にある、真のコミュニケーション能力育成とは~
- 【学校専用】スモールステップで着実に力がつく小論文対策
- 『2026年用 共通テスト対応模試 パワーマックス国語』 〜新課程初年度の共通テスト分析を踏まえた本書の特長〜
- 【2026共通テスト数学】新課程2年目対策! ~2025年度分析と対策ポイント~
- 【2026年度大学入学共通テスト対策】新課程2年目対策! 2025年度共通テスト英語の徹底分析と『パワーマックス英語』改訂のポイント
- 【学校向け】東京大学入試の国語で得点できる力を養うために必要な対策~2025年度入試問題Pick up!〜
- 共通テスト英語リーディング・リスニング対策のはじめの1冊 ~1回10分で、共通テスト全問の対策を網羅~
2025年5月からはダウンロードにて2025年度本試験傾向に合った新作問題のご提供を開始! - 英単語集の定番がより使いやすく大改訂!『速読英単語 必修編[改訂第8版]』
- 生徒の「数学的に表現する力」を伸ばす添削指導 ~添削指導の時間を確保できずにお困りの先生方へ~
- 【学校向け】Z会の実力テストから見える「模試になると点数が取れなくなる」生徒の課題
Contact
小学校~高校の先生・職員の方
【東京営業所】
月〜金 午前9:00〜午後5:30
(年末年始・土日祝日を除く)
(年末年始・土日祝日を除く)
Fax:03-5280-0071
【大阪営業所】
月〜金 午前9:00〜午後5:30
(年末年始・土日祝日を除く)
(年末年始・土日祝日を除く)
Fax:06-6195-8560
【書籍に関するお問い合わせ】
月〜金 午前9:00〜午後5:30
(年末年始・土日祝日を除く)
(年末年始・土日祝日を除く)
Fax:055-989-1436
【Webからのお問い合わせ】
大学の先生・職員の方/法人の方
月〜金 午前10:00〜午後5:30
(年末年始・土日祝日を除く)
(年末年始・土日祝日を除く)
Fax:03-5280-0071
【大学の先生・職員の方】
【法人の方】
【取材のご依頼】
